「胃が痛い」「胃に不快感がある」などの症状は、日常的に起こりやすいため、受診をためらったり、我慢したり、放置する方もいるかもしれません。
しかし、それらの症状に胃がんが隠れている恐れもあり、軽視は危険です。
本記事では、胃がんの概要・初期症状・自覚症状や、胃がんになりやすい方の特徴・原因などを詳しく解説します。
胃がんに関する知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

胃がんとは?

胃がんとは、胃の細胞が何らかの原因でがん化する病気です。
日本人の罹患数の3位、死亡数4位に位置しており、男性の11人に一人、女性の24人に一人の確率で罹患するといわれています。※1
胃の最も内側にある粘膜から発症して粘膜下層、筋層、漿膜へと広がり、リンパ節や肝臓、肺、骨などのさまざまな部位に転移する恐れがあります。
多くの場合、早期の胃がんは根治が可能です。しかし、自覚症状に乏しく、胃がん特有の症状がないため、受診が遅れるケースも少なくありません。
はじめに、胃がんの種類や5年生存率を紹介します。
胃がんの種類
胃がんには、分化型胃がん・未分化型胃がん・スキルス胃がんの3つの種類があり、がん細胞の形態に基づき分類されます。
| 分化型胃がん | 未分化型胃がん | スキルス胃がん | |
|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 胃粘膜に腫瘍や潰瘍を形成する | がん細胞がパラパラと散らばる | 胃壁が硬く厚くなり、腹膜播種が起こる |
| 発症頻度 | 60~70% | 20~30% | 10%程度 |
| 好発年齢・性別 | 高齢者の男性に多い | 若年者の女性に多い | 若年者の女性に多い |
| 進行速度 | 穏やか | 速い | 非常に速い |
| 早期発見 | 可能 | 困難 | 困難 |
胃がんのなかで最も多いタイプは、胃粘膜の細胞ががん化する分化型胃がんです。70~80歳の高齢者に好発し、男女比は2:1で男性がかかりやすい傾向にあります。※2
がんが腫瘍や潰瘍を形成するため肉眼で確認しやすく、発見されやすいことが特徴です。
一方、未分化型胃がんは広範囲にわたって散らばるように広がります。そのなかでも胃壁に浸潤するように広がるスキルス胃がんは、進行速度が速いうえに発見が困難です。
胃がんの5年生存率
胃がん全体の5年生存率は、66.6%(男性:67.5%、女性:64.6%)です。※3
次に、ステージ別の5年生存率を紹介します。
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | |
|---|---|---|---|---|
| 5年生存率 | 82.0% | 59.7% | 37.5% | 6.2% |
ステージ1は、がんが胃粘膜、もしくは粘膜下層に留まっており、リンパ節への転移がほぼない状態です。
手術でがんそのものを切除でき、胃の機能を温存できることから5年生存率は80%を超えます。
しかし、がんが固有筋層や漿膜下層まで浸潤したり、リンパ節への転移が複数あったり、進行ステージが2~3になると生存率は急激に低下します。
また、ステージ4はがんが他の臓器にも広がり、根治治療が困難です。そのため、5年生存率は非常に厳しい数値になります。
胃がんに初期症状はある?

大半の胃がんは、胃の粘膜層に留まってゆっくり進行する特性があり、初期症状は現れにくいといわれています。
また、症状があっても胃がん特有のものではないため、日常的な不調と軽視して医療機関の受診が遅れるケースも少なくありません。
早い段階で胃がんを見つけ出して適切な治療につなげるには、定期的な胃がん検診が重要です。
厚生労働省の「平成29年度地域保健・健康増進事業報告」によると、胃がんがん検診の受診者の6.78%が精密検査となり、1.50%の方から胃がんが発見されました。※4
何らかの症状がある際はもちろん、健康状態に異常がなくとも2年に1回は胃がん検診を受けましょう。
胃がんが進行した場合の自覚症状

胃がんが進行した場合、下記の自覚症状が現れます。
- 胃の痛み・不快感
- 食欲不振・体重減少
- 吐き気・胸焼け
- 食べ物が飲み込みにくい
- 黒色便(血便)
思い当たる症状がある方は、軽度でも内科・消化器内科を受診して然るべき検査を受けましょう。
胃の痛み・不快感
胃がんの代表的な症状は、胃の痛み・不快感です。
胃・みぞおちの周辺に、シクシクとした沁みる感覚の痛みや、キリキリと刺されるような痛み、ズキズキと波打つ痛みなどが現れ、腹部全体に重み・張りなどの不快感が生じます。
胃の痛み・不快感は、胃炎をはじめ、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、機能性ディスペプシア、逆流性食道炎、胆石症・胆のう炎、膵炎などの幅広い病気で引き起こされる症状です。
また、ストレス、疲労・睡眠不足、暴飲暴食などでも悪化する可能性があることから、はじめから胃がんを疑う方は少ないでしょう。
症状がなかなか改善しない、または長引く場合は、軽度であっても医師に相談しましょう。
食欲不振・体重減少
食欲不振は、がんの診断時に約半数、進行がんでは70%認められる「がん悪液質」の症状の一つです。とくに、胃がん・膵臓がんで生じる頻度が高いといわれています。※5
主な原因は、がん細胞が作り出す「サイトカイン」と呼ばれる物質です。胃がんの進行に伴い、サイトカインの分泌量が増えると脳の食欲を刺激する神経の働きが抑制されます。
食事が食べられず、筋肉が減るうえに、エネルギーの消費量が増して体重が減少します。
また、がんにより本来の胃の機能が低下して栄養が吸収しづらくなることで、体重が減少するとも考えられています。
原因不明の食欲不振や体重減少がある場合は、できる限り早く原因を追究しましょう。
吐き気・胸焼け
胃がんが進行すると、胃のなかに内容物が溜まったり、胃酸が逆流して食道に達したり、食物の通過が妨げられて吐き気・胸焼けが生じるケースが多いです。
酸っぱいものがこみ上げてくる、げっぷが頻繁に出るなど、逆流性食道炎のような症状が現れます。
これらの症状は、他の消化器系の病気や一般的な不調との区別が難しく、見過ごされがちです。
空腹時でも吐き気・胸焼けを伴い、次第に症状が強くなるときは、放置せずに医療機関で検査を受けることが大切です。
食べ物が飲み込みにくい
胃がんが食道に広がり狭窄を引き起こすと、食べ物がつかえたり、飲み込みにくさを感じたり、食事が困難になる場合があります。
とくに、胃の入り口~上部にがんが発生した場合、食べ物を食道から胃にスムーズに運べなくなることで、嚥下困難が生じやすくなります。
さらにがんが大きくなると、拡張性が悪化してすぐ満腹になり、食事の摂取量が減って十分な栄養が摂れずに体力が低下するケースも少なくありません。
黒色便(血便)
黒色便(血便)は、がんが出血したときに起こる症状です。血液が消化管を通過する際に胃酸により酸化されて、タール便と呼ばれる真っ黒に変色した便が出ます。
また、出血量が多い場合は血便・下血が伴い、吐血となって現れることもあります。
慢性的な出血が原因で貧血になり、胃がんが発見されるケースも少なくありません。
胃がんになりやすい方の特徴・原因

胃がんになりやすい方の特徴・原因を紹介します。
該当する方は、とくに症状がなくとも定期的に検査を受けて、胃がんの早期発見を目指しましょう。
ピロリ菌の感染
ピロリ菌とは、「ヘリコバクター・ピロリ菌」と呼ばれる胃の粘膜に生息する細菌です。持続感染により慢性的な炎症を引き起こし、萎縮性胃炎を経て胃がんを誘発させます。
ピロリ菌の感染者は5倍、過去に感染歴がある方は10倍ほど、胃がんのリスクが高くなることがわかっています。※6
ピロリ菌の感染が認められても、除菌治療をおこなえば胃がんのリスクを減らすことが可能です。
一般的に、胃酸の分泌を抑制する薬剤と2種類の抗生物質を1週間服用すれば、約8割は除菌に成功するといわれています。※7
そして、除菌後も定期的な検査によるフォローアップが大切です。
1次除菌の効果がなかった場合、2次除菌をおこなう可能性があり、また、継続的に胃の状態をチェックすれば、ピロリ菌の再熱・再感染が早期に発見できます。
喫煙
喫煙による胃がんのリスクは、男性で1.8倍、女性で1.2倍です。※8
喫煙本数が多いほどリスクは上昇し、1日あたりのタバコの本数が20本未満で1.41倍、20~24本で1.98倍、25本以上で2.15倍まで高まります。※9
なお、禁煙をすれば10年後には胃がんのリスクは半分に下がることが報告されています。※10
また、他人のタバコの煙を吸い込む受動喫煙も、胃がんのリスクを高める要因の一つです。タバコを吸う習慣がある方は禁煙をし、受動喫煙を避ける環境を心がけましょう。
塩分の過剰摂取
塩分の過剰摂取は、胃の粘膜にダメージを与えて炎症を引き起こし、胃がんのリスクを約2倍高めるといわれています。※11
とくに、塩分濃度が10%あるいくら・塩辛・練りウニを食べる方は、最大で3.5倍にまでリスクが上昇します。※12
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準2020年版」によると、1日の塩分摂取量の基準は、男性で7.5g未満、女性で6.5g未満です。※13
塩分の摂り過ぎに注意し、胃がん予防に努めましょう。
胃がんの検査方法

ここで、胃がんの主な検査方法を紹介します。
- 内視鏡検査
- X線検査(バリウム検査)
- 血液検査
次章では、それぞれの検査内容を詳しく解説します。胃がんの検査を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
内視鏡検査
内視鏡検査は、胃がんの発見に最も有効といわれる検査です。
口(経口)または鼻(経鼻)から先端に小型カメラを搭載した細長いスコープを挿入して、胃の内部の映像をモニターに映し出してリアルタイムで観察します。
胃粘膜の色や形状が高画質で確認でき、腫瘍・潰瘍や隆起・凹みなどを捉えることが可能です。
疑わしい病変があった際は、組織を採取して病理検査が実施できる点も、内視鏡検査の強みです。
内視鏡検査を受けるときは、前日の夕食を20時頃までに済ませてアルコールの摂取を控えましょう。検査当日は基本的に絶食で、水のみ摂取できます。
内視鏡が喉を通過する際、強い嘔吐反射が起こり苦しく感じることがありますが、近年では、苦痛を軽減するために鎮静剤を使用する医療機関も増えています。
鎮静剤を使用した場合、効果が切れるまで1~2時間程度の安静が必要です。
X線検査(バリウム検査)
X線検査(バリウム検査)は、胃がんによる死亡率の減少が科学的に証明されている検査の一つです。
発泡剤で胃を膨らませてからバリウム(造影剤)を飲み、仰向けとうつ伏せ、左右にX線を照射して胃の形・大きさをより正確に抽出し、がんを含む病変の有無を観察します。
なお、過去にバリウムによるアレルギー症状がみられた方は、検査が受けられない可能性があります。検査を受ける前に医療機関に相談しましょう。
X線検査は、内視鏡検査と同様に検査当日は絶食が原則です。検査後は、バリウムをスムーズに体外に排出するために下剤を服用します。
万が一、異常が確認された場合は、内視鏡検査と病理検査をおこなったうえで診断を確定します。
血液検査
胃がんのリスク検査(ABC検診)は、血中のピロリ菌抗体の測定と、胃粘膜の萎縮の程度を評価する血清ペプシノーゲン検査(PG検査)を組み合わせた血液検査です。
判定結果は、下記のとおりです。
- A群:胃がんのリスクは極めて低い
- B群:多少の胃がんのリスクがある
- C群:胃がんのリスクが高い
- D群:非常に胃がんのリスクが高い
A群は、ピロリ菌の感染と胃粘膜の萎縮がなく、健康的な胃といえます。B群は、ピロリ菌の感染が陽性であり除菌治療が推奨されます。
C群の場合、ピロリ菌の感染と胃粘膜の萎縮があり、胃の粘膜が弱っていることから内視鏡検査の受診がおすすめです。
D群は非常に胃の粘膜が弱っている状態であるため、すみやかに内視鏡検査を受けることが重要です。
胃がんの治療方法

胃がんの治療方法には、下記の3つがあります。
- 内視鏡治療
- 外科手術
- 化学療法
次章で詳しく紹介します。
内視鏡治療
内視鏡治療は、がんが粘膜層または粘膜下層に留まっており、リンパ節への転移がない早期胃がんに適応される治療法です。
がんのタイプやサイズに応じて、次の術式を検討します。
- ポリペクトミー
- 内視鏡的粘膜切除術(EMR)
- 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
10~15mm以内の茎のある隆起型は、日帰り手術のポリペクトミーが可能です。
スネアと呼ばれるワイヤーを病変の根元にかけ焼き切ったり、根元の細胞を壊死させたり、がんを切除・回収します。
2cm未満の隆起型や1cmまでの陥凹型の胃がんには、内視鏡的粘膜切除術(EMR)が有用です。
がんの粘膜下層に生理食塩水を注入し、隆起させてからスネアで締め上げ、高周波電流で切除します。
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)とは、粘膜下層を剥離して病変を切り離す術式です。潰瘍を伴う2cmを超えるがんにでも適応ができ、再発がほぼないことが特徴です。
外科手術
外科手術は、胃の一部、またはすべてを切除してがんを治療する方法です。がんの大きさ・場所、深達度、転移の状態に応じて、下記の手法を選択します。
- 胃全摘術
- 噴門側胃切除
- 幽門側胃切除術
- 幽門保存胃切除術
胃を半分以上残すことが難しい場合には、胃全摘術がおこなわれます。胃を食道や十二指腸と隔離してすべて切除するため、食道と小腸を吻合する再建術が必要です。
胃の上部に限局するがんには、入り口(噴門)側を切除する噴門側胃切除が、胃の下部に対するがんには出口(幽門)側を取り除く幽門側胃切除術が実施されます。
ともに、胃の2/3~1/2が温存できることが大きなメリットです。
幽門保存胃切除術では、胃の中部のみを切除して残胃をつなぎ合わせることで、胃の機能温存が可能です。ただし、がんが胃の出口から4cm以上離れている場合にのみ適応されます。
化学療法
胃がんの切除率を上げるために、術前に化学療法を用いるケースが多いです。
S-1の内服とシスプラチンの点滴を組み合わせ、がんを小さくしてから手術を実施することが一般的です。
また、術後はS-1を内服したり、ドセタキセルを点滴したり、再発防止の補助化学療法を継続します。
そのほか、手術が困難な進行がんに対しては、複数図の抗がん剤を2~3週間ごとに内服・点滴し、がん細胞の縮小と症状の緩和を目指します。
胃がんの早期発見にマイクロCTC検査がおすすめ

マイクロCTC検査では、血中のがん細胞そのものをキャッチできることから、胃がんを含む全身のがんの早期発見につながります。
そのため、次の方におすすめです。
- 高精度・高品質のがんリスク検査を受けたい方
- 検査を受ける時間がない方
- 気軽に自身のがんリスクを調べたい方
ここからは、マイクロCTC検査の魅力を紹介します。
マイクロCTC検査の仕組み
マイクロCTC検査は、がん細胞の性質に着目した先進的な血液検査です。
がん細胞は、血管から栄養や酸素を取り込む際、血中に漏れ出して体内を循環していますが、大半は免疫細胞の攻撃により死滅します。
しかし、一部の間葉系がん細胞は周囲の組織に浸潤・転移して、全身のさまざまな臓器に影響を与えます。
マイクロCTC検査では、悪性度の高い間葉系がん細胞のみを捉えることが可能です。
米国MDアンダーソンがんセンターが開発したCSV抗体を用いた独自の検出方法により、特異度94.45%を誇る高精度でがん細胞のタイプと個数を明らかにします。※14
また、国内に民間初となる検査センターを設けている点もマイクロCTC検査の特徴の一つです。
迅速な検査体制を整えて高品質な検査精度を実現し、納得感が得られる検査を提供しています。
検査は1回5分の採血のみ
マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで全身のがんリスクがわかる血液検査です。
従来の検査で全身をくまなく調べる場合、複数の検査を組み合わせる必要があり、半日~1日もの時間を要します。
また、検査のために専門の施設や遠方の専門病院を受診したり、結果説明を聞きに再度受信したり、手間がかかります。
仕事・家事が忙しく検査を受ける時間がない方にとっては、受診のハードルは高いといえるでしょう。
マイクロCTC検査であれば、近隣の提携クリニックで気軽に受けられ、短時間で検査が終了するため、通勤途中や買い物のついでに自身のがんリスクが調べられます。
そして、検査結果はWebで確認でき、結果説明の来院は不要です。
気軽・手軽に検査が受けやすく、定期的に活用できる点もマイクロCTC検査の魅力の一つです。
料金・クリニック概要
マイクロCTC検査の料金は、1回198,000円(税込)です。全国176件のクリニックで導入しており、都合のよいエリアで検査が受けられます。※15
クリニック検索から検査予約、問診票の記入、検査費用の事前支払いまでWebで完結し、また、検査結果もマイページから確認できます。
アフターフォローが充実しているため、万が一のときも安心です。
がん細胞が検出された方は、マイクロCTC検査センター長、および代々木ウィルクリニックの太田医師による無料相談が受けられます。
基本的に無料相談は対面での対応となり、遠方の方のみオンライン面談が可能です。
無料相談の主な内容は、下記のとおりです。
- 検査結果の説明
- 受けるべき精密検査
- 専門医・医療機関の紹介
また、相談後に画像診断や内視鏡検査などを受診してもがんが発見されなかった場合、再度無料で相談できます。
胃がんに関するよくある質問
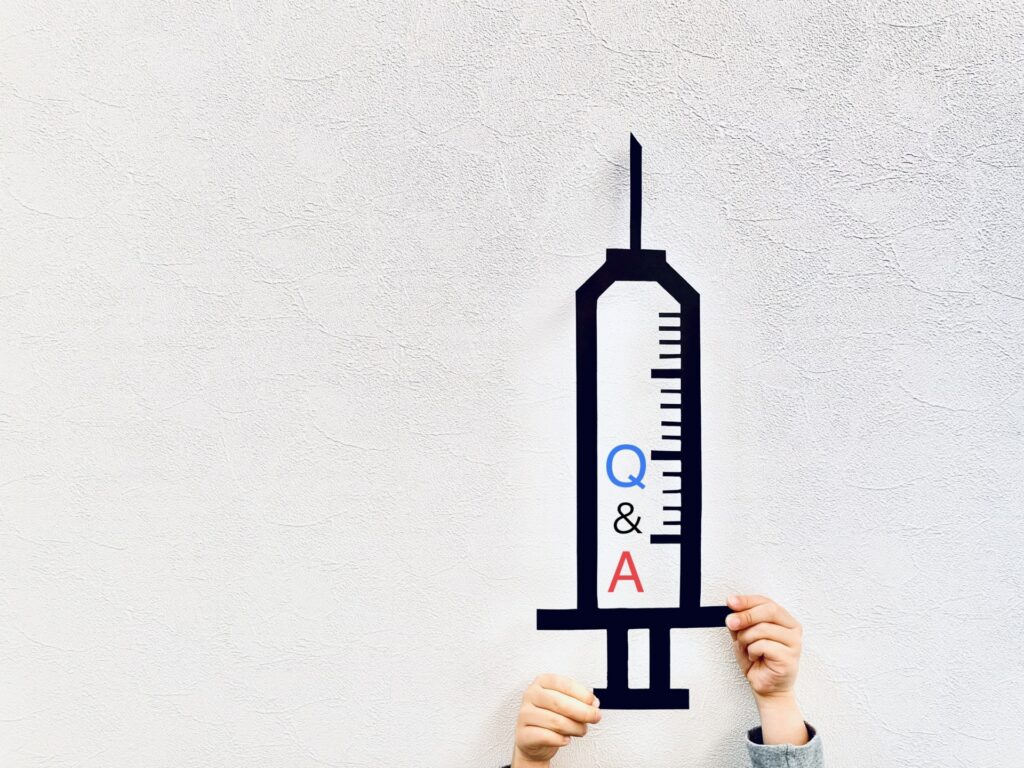
最後に、胃がんに関するよくある質問を紹介します。
- 胃がんの末期症状
- 胃がんとげっぷ・おならの関係
- 胃がんの予防方法
同じ疑問を抱いている方は、ぜひ解決の参考にしてださい。
胃がんの末期症状は?
胃がんが進行すると、全身のあらゆる臓器に転移してさまざま症状が引き起こされます。
胃がんの末期症状には、次のようなものがあります。
- お腹の張り・むくみ
- 腹部・背中・胸などの激しい痛み
- 強い倦怠感や黄疸
体の水分調節機能が低下し、腹水が溜まることでお腹の張りやむくみが生じます。そして、肺や骨に転移すると、腹部や背中、肺などに激しい痛みが伴います。
また、強い倦怠感や黄疸は、肝臓へ転移した際に起こる症状です。
そのほか、がんが脳に広がると感覚・運動・認知・言語・視野などの障害が現れます。
胃がんになるとげっぷ・おならが増える?
胃がんになると、従来の胃の働きが低下してガスが溜まったり、胃と腸の接続部位が狭まったりと、げっぷの回数が増えるケースがあります。
胃がんとおならの回数は直接関係ありません。しかし、胃がんによる消化不良でおならが頻繁に出るとも考えられます。
げっぷとおならには、他の病気が隠れている可能性があるため、明らかに頻度が増えた場合は医療機関に相談しましょう。
胃がんを予防する方法は?
胃がんの予防には、次のことが大切です。
- ピロリ菌の検査・除菌治療
- 禁煙
- 食生活の改善
- ストレスの軽減
まずは、胃がんの最大のリスク因子であるピロリ菌の検査を受けて、陽性の場合はすみやかに除菌治療をおこないましょう。
そして、喫煙習慣がある方は禁煙外来や禁煙補助薬などを上手に活用して、禁煙しましょう。
また、塩分濃度の多い食品や暴飲暴食を控えて、野菜・果物を積極的に摂取するよう、食生活を見直すこともポイントです。
そのほか、ストレスは胃にダメージを与える恐れがあります。ストレス軽減を目指して、適度な休息・運動を取り入れましょう。
まとめ
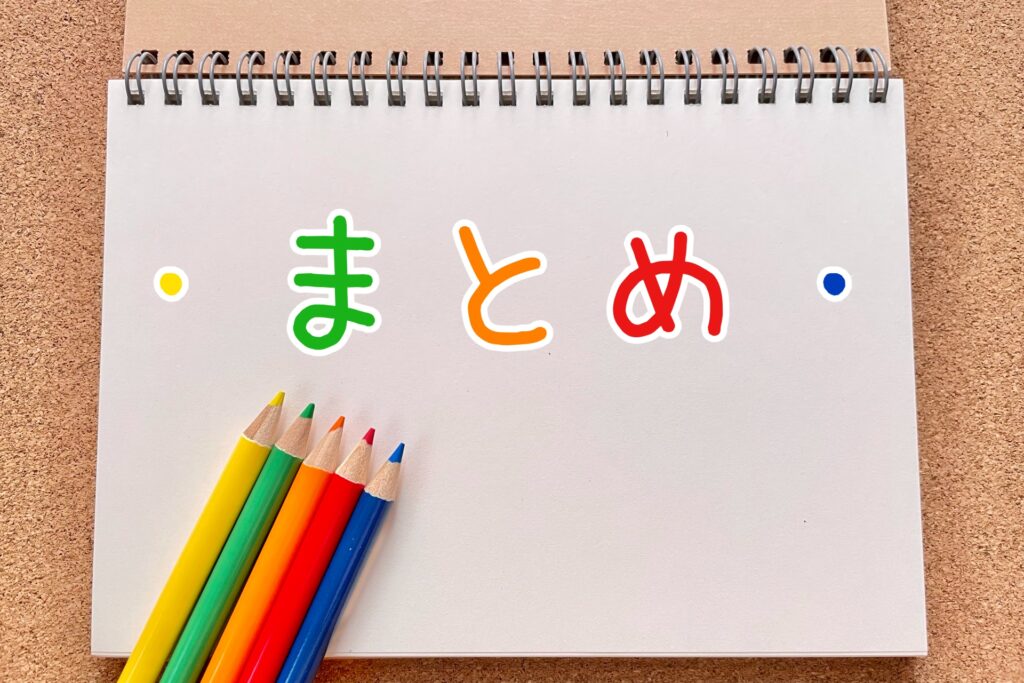
本記事では、胃がんの初期症状・自覚症状を中心に解説しました。
胃がんは初期症状が現れにくく、特有の症状がないため、気が付かないうちに進行している場合があります。
胃の痛み・不快感をはじめ、食欲不振・体重減少、吐き気・胸焼けなどが続く際は、症状を放置せずに内科・消化器内科を受診しましょう。
胃がんをはじめ、全身のがんリスクを手軽かつスピーディーに把握したい方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで血中のがん細胞を高精度で検出します。
定期的にマイクロCTC検査を活用して、がんの早期発見・早期治療につなげましょう。
〈参考サイト〉
※1:国立がん研究センター がん統計|最新がん統計
※2、※3:国立がん研究センター|がん統計 胃
※4:厚生労働省|平成29年度地域保健・健康増進事業報告の概況
※5:日本緩和医療学会|がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン(2017年版)
※6:国立がん研究センター|がん対策研究所 ヘリコバクター・ピロリ菌感染と胃がん罹患との関係
※7:大塚製薬|ピロリ菌の検査と除菌治療
※8:国立がん研究センター|がん対策研究所 喫煙と胃がんリスク
※9:ファイザー すぐ禁煙.jp|タバコはさまざまながんと関連しています
※10:国立がん研究センター|がんの発生や治療へのたばこの影響
※11、※12:国立がん研究センター|がん対策研究所 食塩・塩蔵食品摂取と胃がんとの関連について
※13:厚生労働省|日本人の食事摂取基準2020年版
※14、※15:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査
