胃がんは、50代以降のとくに男性に多いがんです。そのため、「20代は胃がんと無縁」「女性は胃がんにならない」と考えている方も少なくありません。
しかし、胃がんのなかには、20代を含む若年層や女性に多くみられる進行性の「スキルス胃がん」が存在します。
本記事では、20代でも胃がんになる可能性をはじめ、スキルス胃がんの原因・症状、受けるべき検査方法や治療法などを詳しく解説します。
生涯のうち、男性の11人に1人、女性の24人に1人が胃がんになるといわれています。20代の方も胃がんに関する知識を深めて万が一のときに備えましょう。※1
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

20代でも胃がんになる?
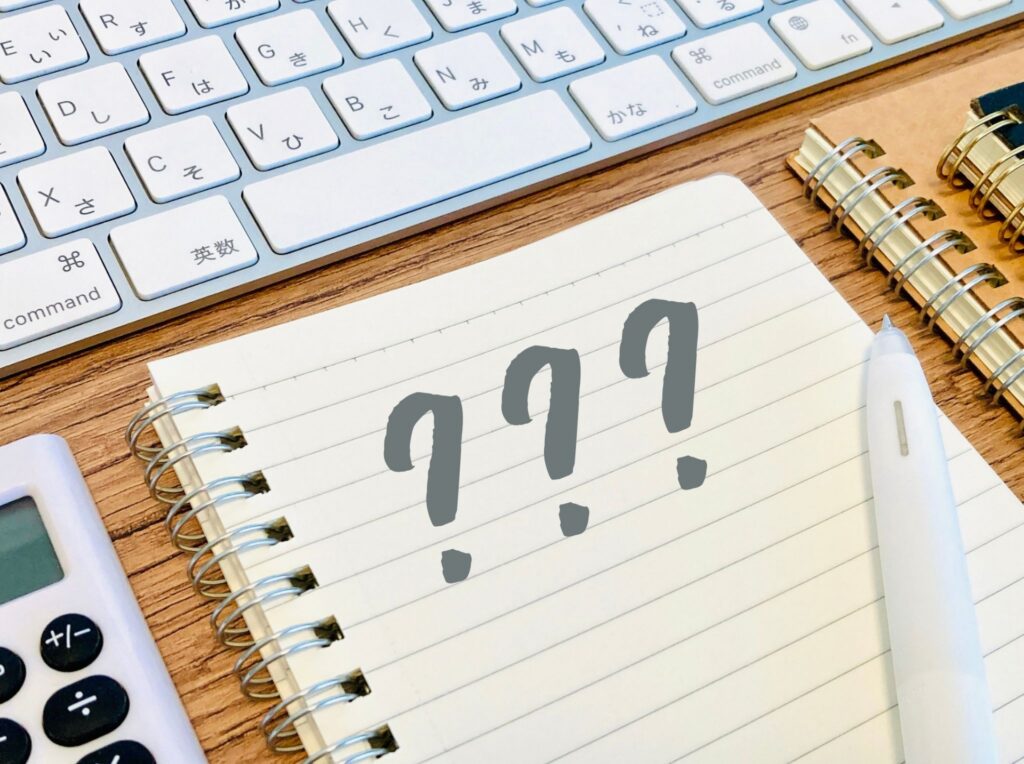
一般的に、胃がんの発症リスクは50代から徐々に高まり、60代・70代でピークを迎えます。しかし、20代の若年層にも多く発症するタイプの胃がんがあるため、油断は禁物です。
はじめに、20代で胃がんになる確率と、若年層に多く発症するスキルス胃がんの概要を紹介します。
一般的な胃がんの確率は低い
多くの胃がんは、50代から徐々に増え始めて、高齢になるほど罹患リスクが高まる傾向にあります。2020年度の年代別罹患数は、下記のとおりです。
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罹患数 | 101人 | 595人 | 2,126人 | 5,913人 | 20,431人 | 42,744人 |
20代の罹患率は0.3~1.3%程度であり、一般的な胃がんになる確率は非常に低いといえます。
スキルス胃がんは20代でも発症する
スキルス胃がんとは、進行スピードが非常に速い難治性のがんです。発症頻度は胃がん全体の7~15%程度ですが、20代・30代の若年層に多く発症します。
胃粘膜の表面に腫瘤や潰瘍を形成する一般的な胃がんと異なり、胃の組織の広範囲に浸み込み、胃壁を硬く厚くしながら進行します。
初期症状がほぼなく、病変を肉眼で捉えにくいことから、診断時にはすでに腹膜に転移があり、根治治療できないケースも少なくありません。
20代でも発症する胃がんの原因・症状

20代でも発症する確率が高い胃がんは、スキルス胃がんです。
次章では、スキルス胃がんの原因・症状を詳しく紹介します。
原因
胃がんの原因として、次のものが考えられています。
- ヘリコバクター・ピロリ菌
- 遺伝
- 喫煙
- 過度な飲酒
- 塩分濃度が高い食品の過剰摂取
ヘリコバクター・ピロリ菌は、スキルス胃がんを含む胃がんの最大の原因です。
感染者や過去に感染した経験がある方の胃がんのリスクは、5~10倍ほど高くなることがわかっています。※2
胃がんのなかには、遺伝性びまん性胃がん(HDGC)と呼ばれるCDH1遺伝子の異常によって引き起こされるものがあります。
第1近親者(両親や兄弟姉妹)または第2近親者(祖父母など)に1人以上の胃がんの家族歴がある方は注意が必要です。
また、喫煙は1.6倍、過度な飲酒は1.29倍、胃がんのリスクを上昇させます。※3※4
そのほか、いくら・塩辛などの塩分濃度が高い食品は、最大で3.5倍胃がんリスクを高めます。※5
症状
大半の胃がんは初期症状に乏しく、進行に伴い下記の症状が現れます。
- 胃痛・不快感
- 食欲不振・体重減少
- 吐き気・胸焼け
- 血便・貧血
胃がんの代表的な自覚症状は、胃痛・不快感です。「シクシク」「キリキリ」「ズキズキ」などの鈍い・鋭い・波打つ痛みが現れ、胃・みぞおち全体に不快感が生じます。
食欲不振・体重減少は、「がん悪液質」によるものです。進行がんの70%でみられる症状で、サイトカインの影響を受けて食欲が抑制され、エネルギー消費量が増えます。※6
また、がんが大きくなると消化機能の低下や運動機能に異常をきたし、吐き気・胸焼けが現れるケースも少なくありません。
そのほか、がんから出血していると、血便や下血が出て慢性的な貧血が起こります。
20代でも受けるべき胃がんの検査方法

ここで、20代でも受けるべき胃がんの主な検査方法を紹介します。
- X線検査(バリウム検査)
- 内視鏡検査(胃カメラ)
- 血液検査
何らかの症状があり、医師が必要と判断した検査は保険適用で受けられますが、健康管理を目的とした場合は自由診療となり、完全実費です。
次章では、それぞれの検査内容を詳しく解説します。症状の有無にかかわらず胃がんの検査を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
X線検査(バリウム検査)
X線検査(バリウム検査)は、胃の形・大きさを正確に抽出できる検査で、「上部消化管X線検査」または「上部消化管造影検査」と表記される場合もあります。
胃を膨らませる発泡剤と、胃を白く写し出して病変を視覚的に確認するためのバリウム(造影剤)を飲み、X線を多方面から連続して照射しながら撮影します。
検査時間は5~10分程度と短いです。また、比較的安く検査が受けられます。基本的に痛み・苦痛はありませんが、前日および当日の食事制限と、検査後の下剤服用が必要です。
また、X線検査のみでは確定診断につながらないことから、疑わしい病変が発見された場合は内視鏡検査(胃カメラ)をおこないます。
内視鏡検査(胃カメラ)
内視鏡検査(胃カメラ)とは、超小型カメラを搭載した内視鏡を用いて胃の粘膜・凹凸や色調変化を直接観察できる検査です。「上部消化管内視鏡検査」とも呼ばれています。
約80%の胃がん死亡率減少効果があります。また、疑わしい病変をその場で採取して生検ができるため、確定診断が可能です。※7
検査は絶食でおこないます。所要時間は15分、生検をおこなう場合は30~1時間程度です。
口や鼻からスコープを挿入する際、苦痛や嘔吐反射が起こるケースが多いですが、鎮静剤を使用して眠ったような状態で検査を受けることも可能です。
鎮静剤の使用後は1~2時間安静にし、自動車・自転車などの運転は終日避ける必要があります。
血液検査
胃がんの血液検査には、主にリスク検査(ABC検診)があります。
リスク検査(ABC検診)では、ピロリ菌抗体の感染有無と、血清ペプシノーゲン検査(PG検査)を調べて胃粘膜の萎縮の程度を評価します。
判定結果は、下記のとおりです。
| 分類 | 胃の状態 | 判定結果 |
|---|---|---|
| A群 | 健康な状態 | 胃がんのリスクは極めて低い |
| B群 | ピロリ菌感染あり | 多少の胃がんのリスクがある |
| C群 | ピロリ菌感染と胃粘膜の萎縮がある | 胃がんのリスクが高い |
| D群 | 胃粘膜の萎縮が進行している | 非常に胃がんのリスクが高い |
A群は、胃の状態が健康で胃がんリスクはほぼないといえます。B群は、ピロリ菌の感染があるため除菌治療が必要です。
ピロリ菌の感染と胃粘膜の萎縮がみられるC群は、胃がんのリスクが高いことから内視鏡検査(胃カメラ)を受診しましょう。
D群は胃がんのリスクが非常に高いです。内視鏡検査の結果に応じて治療が必要になる場合があります。
20代で胃がんになった場合の治療法
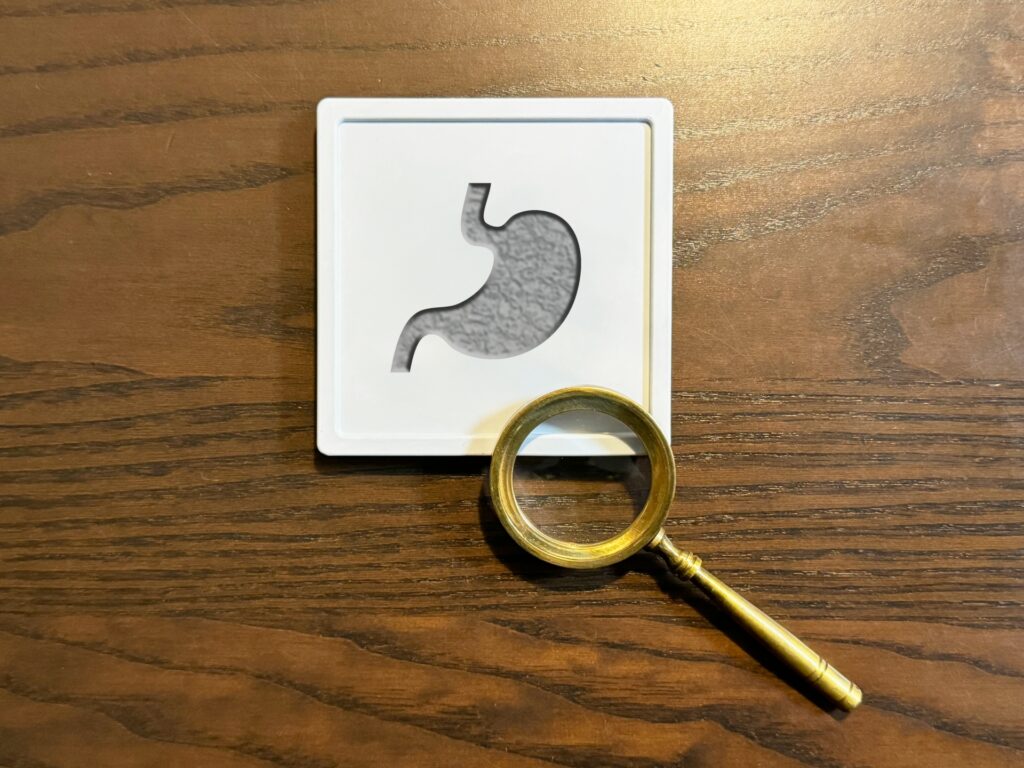
20代で胃がんになった場合、主な選択肢として下記の治療法があります。
- 内視鏡治療
- 外科手術
- 化学療法
- 放射線治療
次章から、それぞれの治療法を詳しく解説します。
内視鏡治療
次の状態に該当する場合、内視鏡治療が適応されます。
- がんが胃の粘膜層または粘膜下層に留まっている
- リンパ節への転移がない
さらに、がんの大きさやタイプにより下記の術式を選択します。
- ポリペクトミー
- 内視鏡的粘膜切除術(EMR)
- 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
10~15mm以内の茎のある隆起型には、スネアと呼ばれるワイヤーを病変の根元にかけてがんを切除・回収するポリペクトミーをおこないます。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)とは、がんの粘膜下層に生理食塩水を注入し、隆起させてから高周波電流で切除する術式です。2cm未満の隆起型や1cmまでの陥凹型が適応です。
2cmを超えるがんに対しては内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)をおこない、粘膜下層を剥離して病変を切り離します。
外科手術
外科手術では、がんの大きさ・場所、深達度、転移の状態に応じて胃の一部、またはすべてを切除します。
- 胃全摘術
- 噴門側胃切除
- 幽門側胃切除術
- 幽門保存胃切除術
胃を半分以上残すことが難しい場合には、胃全摘術が必要です。胃と食道や十二指腸を隔離して切除する必要があるため、術後は食道と小腸を吻合します。
噴門側胃切除は胃の入り口(噴門)側を切除し、幽門側胃切除術は胃の出口(幽門)側を取り除く手法で、ともに胃の2/3~1/2の温存が可能です。
また、胃の中部のみを切除する幽門保存胃切除術では、残った胃をつなぎ合わせて胃の機能を温存します。
化学療法
化学療法には、胃がんの切除率を上げたり、胃がんの再発を抑えたり、複数の目的があります。また、がんによる症状の緩和にもつながります。
術前化学療法では、S-1の内服とシスプラチンの点滴を組み合わせてがんを小さくし、術後補助化学療法の場合、S-1とドセタキセルでがんの再発防止が可能です。
がんによる痛み・苦痛を和らげるためには、複数の抗がん剤を2~3週間ごとに内服・点滴します。
放射線治療
放射線治療は、次の場合に検討します。
- 手術ができない
- 化学療法が効かない
- 胃がんが再発した場合
がんの種類・病状、全身の状態によって異なりますが、放射線治療は1回15~40分を週5回の頻度でおこなうことが一般的です。また、治療期間は4~8週間程度かかります。
放射線治療の効果を高めるために、化学療法を併用する場合があります。
20代の胃がんの早期発見にマイクロCTC検査がおすすめ

マイクロCTC検査は、20代の胃がんをはじめ、全身のがんリスクがわかる画期的な血液検査です。
血中に漏れ出したがん細胞そのものを捕捉して個数を明示するため、従来のがん検査では見つけにくい小さながんや、無症状な早期がんの発見につながります。
ここからは、マイクロCTC検査の特徴を紹介します。
早期発見・早期治療が重要
がんの進行スピードは、種類・ステージ・個人差により大きく異なります。下記は、一般的な胃がんの進行目安です。
| がんの状態 | 進行スピード | |
|---|---|---|
| 早期がん | 1cm未満 | 年単位 |
| 進行がん | 2cm以上に成長 | 半年単位 |
| 末期がん | 遠隔転移あり | 1か月単位 |
1つのがん細胞が1cmの大きさになるには、10~15年ほどの長い期間が必要です。
しかし、1cmのがんは1年半程度で2cmに成長し半年単位で進行するため、早期がんの段階で発見・治療ができる時間は1~2年程度と非常に短いです。※8
がんが進行すればするほど治療における身体的・肉体的・精神的な負担が大きくなり、生存率も低下します。
がんから命を守るためには、早期発見・早期治療が非常に重要ですが、従来の画像検査では1cm未満のがんを確認できずに見落とすケースが少なくありません。
一方、マイクロCTC検査は、がんのサイズにかかわらず、血中のがん細胞そのものを直接捉えて1個単位で検出します。
定期的にマイクロCTC検査を活用して、がんの早期発見・早期治療を目指しましょう。
検査は採血のみで負担が少ない
マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで全身のがんリスクがわかる体の負担が少ない検査です。
従来の全身のがん検査には、時間がかかる、費用が高額になる、副作用や被ばくリスクがあるといったデメリットがありました。
CT・MRI・PECなどの検査には、発見が不得意ながんがあり、複数の検査を組み合わせることから半日~1日の時間を要して費用も高額になります。
また、造影剤(バリウム)によるアレルギー反応やショック症状、放射性物質の検査薬(18F-FDG)による被ばくのリスクが伴います。
マイクロCTC検査の場合、5~10ml程度の採血した血液から全身のリスクが判明でき、体の負担は一切かかりません。
万が一、がん細胞が検出された場合、マイクロCTC検査のセンター長かつ代々木ウィルクリニックの太田医師に無料で相談できます。
全国のクリニックで検査可能
マイクロCTC検査は、全国の提携クリニックで導入しており、居住地・勤務地など都合のよい場所での検査が可能です。また、引っ越し先・転勤先でも同様の検査が受けられます。
ここで、マイクロCTC検査の流れを紹介します。
- クリニック検索・予約
- 検査(採血)
- 検査結果の確認
マイクロCTC検査は完全予約制です。マイクロCTC検査の公式サイトにアクセスして受診するクリニックと日時を選択しましょう。
会員登録をおこない、個人情報と問診票を入力して予約を確定させます。
検査当日は身分証明書を持参のうえ、予約時間の10分ほど前に来院しましょう。受付を済ませた後、医療機関の指示に従い採血を受けて終了です。
1週間前後で検査結果が確定します。登録先のメールアドレスに通知が届いたらマイページにログインし、内容を確認しましょう。
20代の胃がんに関するよくある質問
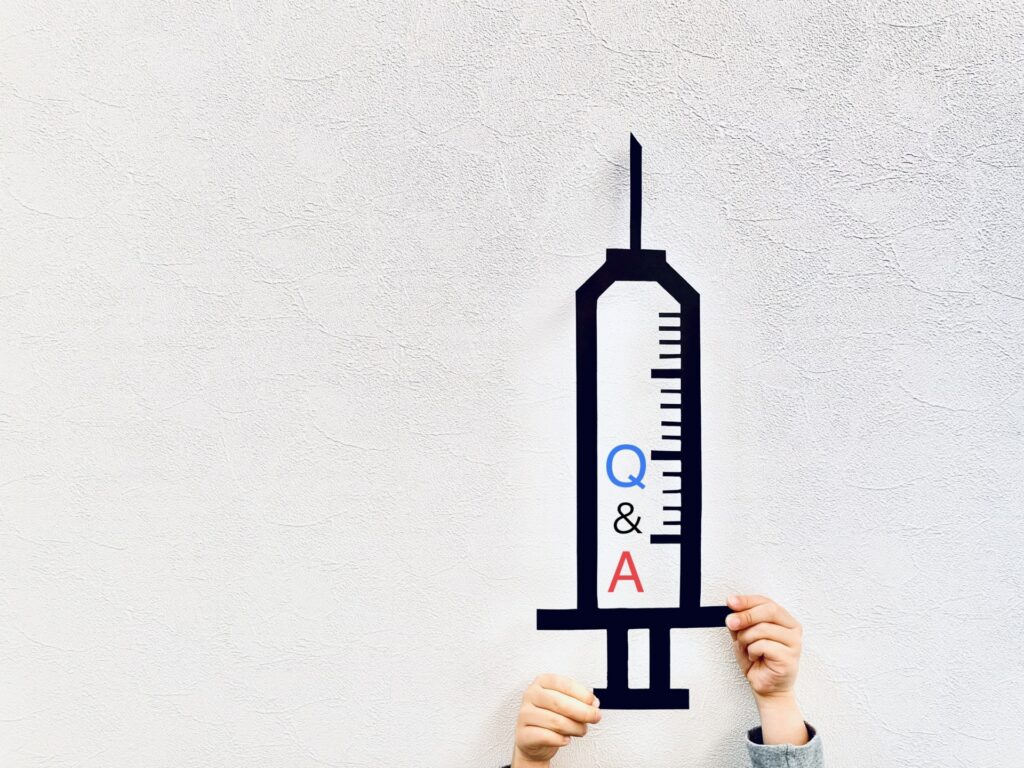
最後に、20代の胃がんに関するよくある質問を紹介します。
- 20代胃がんの男女比率
- スキルス胃がんの5年生存率
- スキルス胃がんは予防方法
同じ疑問を抱いている方は、ぜひ参考にしてください。
20代の男性と女性で胃がんになりやすいのはどちら?
一般的に、胃がん全体の男女比は2:1で、男性の方が発症しやすい傾向にあります。しかし、20代の場合、女性の罹患数は男性を上回っています。
| 20~24歳 | 25~29歳 | |
|---|---|---|
| 男性(罹患数) | 9人 | 38人 |
| 女性(罹患数) | 13人 | 41人 |
また、スキルス胃がんは、1.5:1で女性の割合が多いことがわかっています。※9
スキルス胃がんの5年生存率は?
スキルス胃がんの5年生存率は、手術が可能な段階で発見されても15~20%程度であり、遠隔転移を伴う場合はステージ4に該当するため、6%を下回ります。※10※11
一般の胃がんの5年生存率(66.6%)と比べると、非常に低い数値です。
スキルス胃がんは、早期発見が難しいうえに進行スピードが速く、腹膜に転移しやすいことから、根治治療が困難なケースも少なくありません。
スキルス胃がんは予防できる?
スキルス胃がん特有の予防法は確立されていませんが、一般的な胃がんと同様に、次のことが発症予防につながると考えられています。
- ピロリ菌の除菌治療を受ける
- 禁煙をし、節酒を心がける
- 塩分濃度が高い食品を控える
ピロリ菌が陽性判定の場合、除菌治療をおこない胃がんのリスクを下げましょう。また、禁煙・節酒などの生活習慣の改善も重要です。
そのほか、塩分や刺激物の摂り過ぎに注意し、野菜・果物の摂取量を増やしてバランスのよい食生活を心がけましょう。
そして、とくに症状がなくとも定期的に検査を受けることが大切です。
まとめ
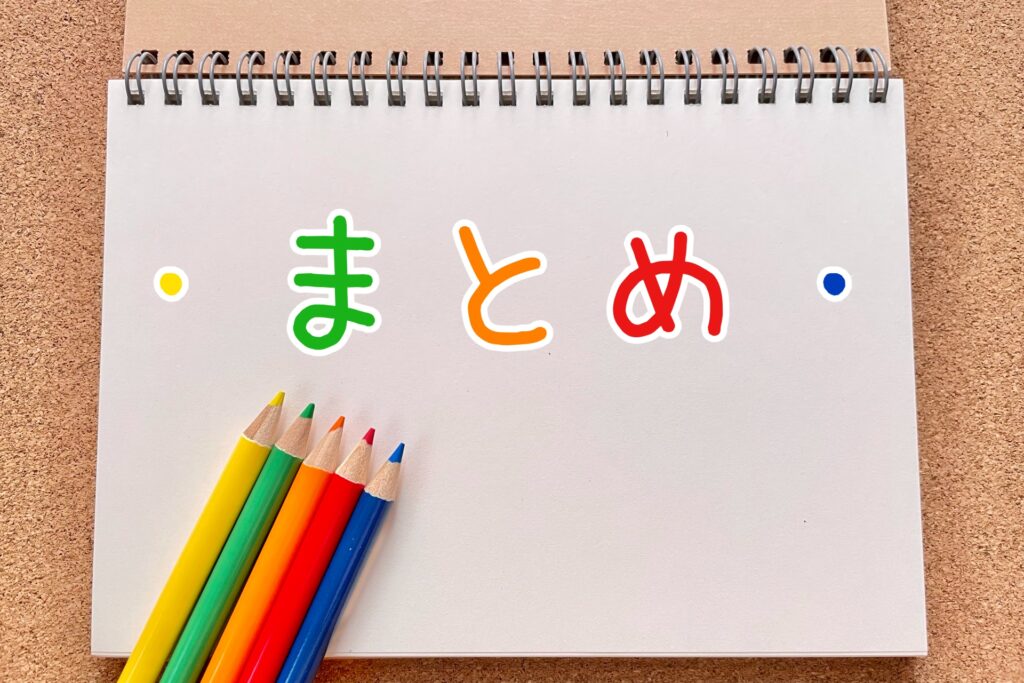
本記事では、20代でも発症するスキルス胃がんの原因・症状・治療法を中心に解説しました。
進行スピードが速く、腹膜に転移しやすいスキルス胃がんは、20代を含む若年層や女性でも多く発症します。
初期症状がほぼないうえに肉眼では捉えにくいことから、発見が遅れて手遅れになるケースも少なくありません。
スキルス胃がんを含む、全身のがんの早期発見にはマイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は1回5分の採血のみで、増殖の過程で血中に漏れ出したがん細胞をキャッチするため、無症状な早期がんや発見が困難なタイプのがんの発見にもつながります。
20代のうちから定期的にマイクロCTC検査を受診し、がんの早期発見・早期治療を目指しましょう。
〈参考サイト〉
※1:国立がん研究センター がん統計|最新がん統計
※2:国立がん研究センター|がん対策研究所 ヘリコバクター・ピロリ菌感染と胃がん罹患との関係
※3:国立がん研究センター|がん対策研究所 喫煙と胃がんリスク
※4:国立がん研究センター|がん対策研究所 日本人における飲酒と胃がんリスク
※5:国立がん研究センター がん対策研究所|食塩・塩蔵食品摂取と胃がんとの関連について
※6:日本緩和医療学会|がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン(2017年版)
※7:胃がん検診文献レビュー委員会|胃がん検診エビデンスレポート2014年度版
※8:がん対策推進企業アクション|早期がんを発見できる時間
※9:札幌医科大学学術機関リポジトリ|スキルス胃癌の検討
※10:がん情報サイト「オンコロ」|スキルス胃がんの基礎知識
※11:がん情報サービス|院内がん登録生存率集計結果閲覧システム 胃がん(胃癌)
