抗がん剤治療は、がんの根治、再発・転移の防止などを目的でおこなわれる治療法です。
血液を介して全身の広範囲に治療効果を発揮しますが、正常な細胞にも影響を与えるため、さまざまな副作用を引き起こす可能性があります。
本記事では、抗がん剤治療の概要や副作用の原因・種類・期間、副作用を軽くする方法などを詳しく解説します。
抗がん剤治療に関する知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

抗がん剤治療とは?

抗がん剤治療とは、抗がん剤を用いた治療法のことで、がんの根治、進行・転移・再発を防ぐ目的でおこなわれます。
はじめに、抗がん剤治療の目的や種類、副作用が起こる原因を紹介します。
抗がん剤治療の目的
抗がん剤治療は、がんの種類や進行度、全身の健康状態などに応じて、次の目的でおこなわれます。
- がん細胞の死滅
- 再発・転移の防止
- がんによる症状緩和
がん細胞を破壊・縮小する作用がある抗がん剤は、手術の治療効果を向上させるために術前に使用する場合があります。
また、微小ながん細胞の根絶にも役立つことから、術後の再発・転移の防止にも有効です。手術で取り切れず体内に残存したがん細胞を、抗がん剤を用いて完全に排除します。
一方、がんの根治が困難なケースでは、がん細胞の増殖を抑えて進行を遅らせたり、がんによる症状を和らげたり、延命を目的とした抗がん剤治療を実施します。
抗がん剤の種類
抗がん剤には、下記の種類があります。
- 細胞障害性抗がん薬
- 分子標的薬
- 免疫チェックポイント阻害薬
細胞障害性抗がん薬には、がん細胞の合成・分裂を妨げて増殖を阻害する作用があります。
アルキル化薬、白金化合物、代謝拮抗薬、トポイソメラーゼ阻害薬、抗がん抗生物質の5つの種類があり、必要に応じて複数の薬剤を組み合わせて投与します。
分子標的薬とは、がんの発症・増殖にかかわる特定の分子(タンパク質や遺伝子)に直接作用する薬です。
そして、免疫チェックポイント阻害薬は、免疫の働きを回復させてがん細胞に対する攻撃を強化させる免疫療法の一つです。
複数の阻害薬やほかの抗がん剤を組み合わせることで、高い治療効果が期待できます。
副作用が起こる原因
抗がん剤治療に用いる細胞障害性抗がん薬は、がん細胞の増殖を妨げて死滅を促す薬剤ですが、正常な細胞にも作用するためさまざまな症状が引き起こされます。
とくに、活発に細胞分裂をする口腔粘膜、消化管粘膜、骨髄、毛根などの組織は、薬剤の影響を受けやすいです。
分子標的薬も同様に、標的とする分子はがん細胞のみならず正常な細胞にも存在しており、薬剤が攻撃して副作用が生じるケースも少なくありません。
免疫チェックポイント阻害薬は、細胞障害性抗がん薬と分子標的薬より副作用が少ないといわれています。
しかし、免疫が活性化しすぎると自身の細胞や組織を破壊し、「免疫関連有害事象(irAE)」と呼ばれる症状が現れることがあります。
いずれも副作用が強い場合は、それぞれの症状の軽減を図る支持療法をおこない、治療の継続を目指します。
抗がん剤治療の主な副作用

抗がん剤治療の主な副作用は、下記のとおりです。
- 嘔吐・吐き気
- 脱毛
- 下痢・便秘
- 口内炎
- 皮膚障害
- 倦怠感
- 手足のしびれ
- 感染症
次章では、それぞれの副作用の概要をはじめ、発現時期や対処法などを詳しく紹介します。
嘔吐・吐き気
嘔吐・吐き気は、抗がん剤治療の最も代表的な副作用です。
消化管の粘膜や脳の神経(嘔吐中枢)が刺激されて、1日に何度も嘔吐したり、強い吐き気が生じたりと、大きな身体的・精神的な負担となります。
抗がん剤による嘔吐・吐き気には、発現する時期で分類される3つのタイプがあり、症状の生じやすさ(催吐リスク)に応じた制吐療法がおこなわれます。
| タイプ | 時期 |
|---|---|
| 急性期嘔吐 | 抗がん剤投与直後~24時間 |
| 遅発期嘔吐 | 抗がん剤投与後24~120時間(2~5日目) |
| 予期性嘔吐 | 時期に関係なく、抗がん剤治療で嘔吐した記憶から誘発される |
多くの場合、急性嘔吐は抗がん剤治療前に制吐薬を投与すれば予防できます。万が一、吐き気を感じた際は内服薬や座薬で症状の改善ができるため、我慢せず医師に相談しましょう。
また、複数の制吐薬を併用して長時間効果を持続させて、遅発期嘔吐を防ぐことも可能です。
抗がん剤治療や嘔吐への不安・恐怖などから誘発される予期性嘔吐に対しては、抗不安薬や行動療法で症状を和らげます。
脱毛
脱毛は、高頻度で発現する抗がん剤治療の副作用の一つです。
抗がん剤は毛根にある毛母細胞にダメージを与えて、毛髪のみならず眉毛・まつ毛、体毛などの脱毛を引き起こします。
抗がん剤投与開始の2~3週後に毛が抜け始めて、治療後3~6か月程度で発毛に向かうケースが多いです。
治療中は頭皮への刺激が強いパーマやカラーリングは避け、帽子、スカーフ、バンダナなどを活用して紫外線対策や頭皮のケガ予防を心がけましょう。
また、普段と変わらない生活を送りたい方や、治療をしながら仕事を続ける方は、あらかじめウィッグを準備しておくとよいでしょう。
とくに、頭皮への刺激が少なく、通気性がよい医療用ウィッグがおすすめです。自治体により、医療用ウィッグの購入・レンタルにかかる費用を補助する制度があります。
下痢・便秘
抗がん剤治療による下痢には、2つタイプがあります。
- 早発性下痢:治療開始直後~24時間以内に発症
- 遅発性下痢:治療開始後10~14日目に発症
早発性下痢の原因は、過剰な腸の蠕動運動です。抗がん剤は腸の働きを調整する副交感神経を刺激し、水分や食物の消化・吸収に影響を与えて下痢を引き起こします。
遅発性下痢は、抗がん剤により腸の粘膜が傷ついて起こる下痢です。投与後数日経ってから現れることが特徴です。
白血球が減少している時期と重なるため、炎症を引き起こしたり、感染症を併発したり、重症化の恐れがあります。
ともに、抗コリン薬や腸管運動抑制薬、収斂薬、吸着薬、整腸薬などを併用すれば、症状の予防・改善が可能です。
一方、抗がん剤が自律神経やホルモンに作用すると、腸の働きを抑制して便秘を引き起こしやすくなります。
積極的に食物繊維が豊富な食材を取り入れて、こまめな水分補給を心がけましょう。
口内炎
抗がん剤治療に伴う口内炎の発生頻度は、30~40%と比較的高い副作用です。※1
主な原因は、抗がん剤の直接的な作用や白血球減少による口腔内の局所感染です。投与後数日~10日目は、口唇、ほおの内側の粘膜、舌のふちなどに口内炎が生じやすくなります。
軽度から中等度の場合は、アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬、中等度以上の痛みには麻薬系鎮痛薬を用いて症状を緩和します。
抗がん剤による口内炎の予防・軽減には、下記が有効です。
- 含嗽剤(うがい薬)とブラッシングによる口腔ケア
- 保湿ジェル・クリームなどによる乾燥予防
また、喫煙は口内炎を悪化させるため、タバコを吸っている方は禁煙しましょう。
皮膚障がい
抗がん剤により皮膚のバリア機能低下、乾燥、炎症などが起こると、下記の副作用が生じやすくなります。
- 発疹・紅斑
- 皮膚の乾燥
- 色素沈着
- 爪の変化
- 手足症候群
一部の抗がん剤は、皮膚表面や汗に排出されるため、発疹・紅斑が現れて痛み・かゆみが伴う場合があります。
また、皮脂腺や汗腺の分泌を抑えられることで乾燥したり、メラニン色素の生産が亢進してシミや黒ずみができたりと、さまざまな変化が現れます。
皮膚障害が出ているときはできる限り紫外線を避け、外出時は日焼け止めクリームを塗り、帽子・日傘、UV手袋などを活用しましょう。
そのほか、爪に白い帯状の横断線がある、手足がむずむずする・痛いなどの症状がある際は、医師に相談して適切な治療を受けましょう。
倦怠感
だるい、疲れやすいなどの倦怠感は、抗がん剤治療を受けている方の多くが経験する副作用です。
抗がん剤治療による倦怠感は、がんそのものの症状や貧血症状、治療による体力の消耗、疲労・ストレス・不眠など、複数の要因が重なっていると考えられています。
倦怠感のピークは抗がん剤投与後2~3日を迎え、徐々に改善に向かいますが、治療を重ねるごとに強くなる傾向にあります。
倦怠感の対策・予防には、自身の活動と休息のパターンを知ることが大切です。倦怠感が現れる時期と強さ、変化などを記録して休息のタイミングを調整しましょう。
また、栄養・水分の補給やリラクゼーションを取り入れる、適度な運動なども倦怠感の軽減につながるでしょう。
手足のしびれ
抗がん剤治療中の手足のしびれは、末梢神経障害によるものです。はじめに手先・足先から発症し、治療回数とともに症状は強くなるといわれています。
手足がビリビリする、感覚がおかしい、力が入らないなど、症状の現れ方はさまざまですが、転倒・ケガを代表とする日常生活での危険防止が最優先です。
階段では手すりにつかまって昇降時の転倒・転落を防ぎ、足のしびれが強いときはエレベーターを使用しましょう。
ハイヒールやサイズの小さい靴は、しびれを悪化させる可能性があることから、柔らかい素材のゆったりとした靴がおすすめです。
手がしびれて感覚が鈍い場合は、家事中の火傷やケガに注意が必要です。手袋を活用して熱いものは触らないように心がけましょう。
感染症
抗がん剤治療中は、血液細胞を正常につくれない骨髄抑制と呼ばれる状態です。
そのため、白血球が減少したり、免疫力が低下したり、風邪やインフルエンザ、胃腸炎、膀胱炎などの感染症にかかるケースも少なくありません。
感染症の予防には、うがい・手洗い、口腔ケア、皮膚の保護などの対策をおこないましょう。また、病原体に応じた適切な治療を受けることも大切です。
抗がん剤治療の副作用はいつまで続く?

ここからは、抗がん剤治療の副作用が続く期間と、副作用を軽くする方法を紹介します。
自身や家族が抗がん剤治療中の方は、ぜひ参考にしてください。
副作用が続く期間
抗がん剤治療による副作用は、個人差や薬剤の種類・量にもよりますが、一般的に投与開始後~数週間でピークを迎え、徐々に回復するといわれています。
しかし、一部の副作用は、治療後も発現する場合や長期間残るケースがあります。
過度な不安や恐怖を抱くと身体的・精神的の負担が大きくなるため、焦らずリラックスしながら症状が改善するのを待ちましょう。
副作用を軽くする方法
抗がん剤治療の副作用の軽減には、次の方法が効果的です。
- 適切な食事
- 十分な休息
- 適度な運動
- ストレス管理
また、近年では副作用を抑える薬や症状を緩和させる漢方など、さまざまな支持療法があります。副作用が強い場合は、医師・薬剤師に相談して適切な処置を受けましょう。
マイクロCTC検査で抗がん剤治療の効果を確認

マイクロCTC検査は、血中のがん細胞そのものを1個単位で検出するため、全身のがんの早期発見はもちろん、抗がん剤治療の効果の確認にも有効です。
ここからは、マイクロCTC検査の特徴を詳しく解説します。
マイクロCTC検査の特徴
マイクロCTC検査とは、血中のがん細胞を直接捉えて全身のがんの早期発見につなげる画期的な検査です。
がん細胞は、増殖に必要な栄養・酸素を血管から取り込む際、血中に漏れ出します。
マイクロCTC検査では、米国「MDアンダーソンがんセンター」が開発した抗体を用いた独自の検査手法を導入しており、血中のがん細胞を1個単位で捉えることが可能です。
がん細胞の検出においては、特異度94.45%と非常に高い精度を実現しています。※2
そのため、マイクロCTC検査にてがん細胞の個数の減少が確認できれば、抗がん剤治療は効果的におこなわれていると判断できます。
一方でがん細胞の個数が変わらない、または増えている場合は、治療の効果が不十分であり、治療方針の変更や薬剤の調整が必要といえるでしょう。
抗がん剤治療中・治療後は、マイクロCTC検査を活用して定期的に治療効果を把握しましょう。
検査は1回5分の採血のみ
マイクロCTC検査は、1回5分の採血で全身のがんリスクが調べられます。そして、事前の準備が不要なことから、忙しい方でも気軽に検査が受けられます。
一般的に、全身のがん検査を受けるには半日~1日程度の時間を要し、検査内容によっては食事制限や薬剤の投与などが必要です。
また、検査設備が整った遠方の医療機関を受診したり、結果説明のために再び来院したりと、非常に手間がかかります。
マイクロCTC検査の場合、全国の提携クリニックで検査が可能で、検査の予約から検査結果の確認までWebで完結します。
スピーディかつ体の負担が少ない検査を気軽に受けたい方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
がん再発の早期発見も可能
マイクロCTC検査では、従来の検査に比べて非常に早くがん再発の予兆を確認できます。
CT・MRI・PETなどの検査は、画像に写りにくい1cm未満の小さながんの発見は困難です。また、体の奥に位置する臓器のがんに対しても、発見が遅れるケースが少なくありません。
マイクロCTC検査であれば、血中のがん細胞そのものをキャッチして個数を明示するため、がん再発の早期発見に役立ちます。
がん細胞が検出された方は、代々木ウィルクリニックの院長およびマイクロCTC検査センター長の太田医師による無料相談が受けられることから、万が一のときも安心です。
マイクロCTC検査の無料相談の概要は、下記のとおりです。
- 相談方法:対面(遠方の方のみオンライン面談が可能)
- 相談時間:最大30分(平日9~12時、13~18時)
- 予約方法:代々木ウィルクリニック(03-5990-6184)
検査結果の説明はもちろん、専門医や医療機関の紹介にも対応しています。
抗がん剤治療の副作用に関するよくある質問
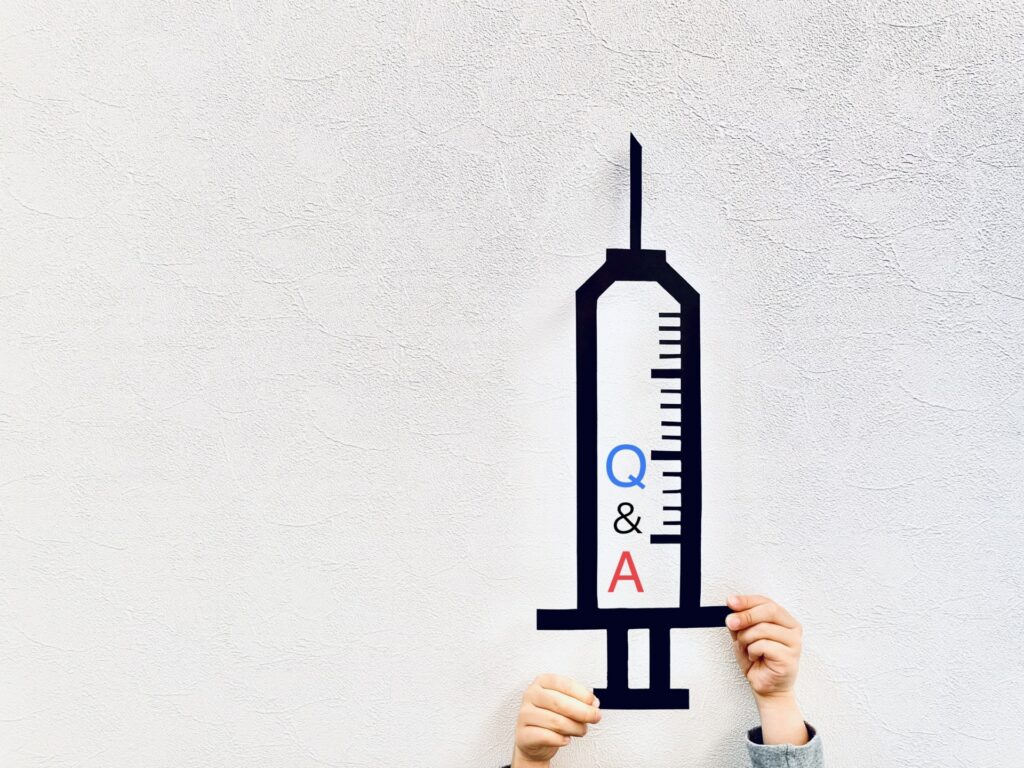
最後に、抗がん剤治療の副作用に関するよくある質問を紹介します。
同じ疑問を抱いている方は、解決のヒントに活用ください。
副作用が出やすい方と出にくい方がいる?
抗がん剤治療の副作用には個人差がありますが、下記に該当する方は比較的副作用が出やすいといわれています。
- 高齢者や体力が低い方
- 生活習慣が乱れている方
- 既存歴がある方
高齢者は、加齢に伴う代謝・排出の機能低下により、抗がん剤が体内に長く留まって副作用が強く現れるケースが多いです。
元々の体力が低い方は、抗がん剤の影響を受けやすく、副作用が強くなる傾向です。
また、栄養バランスの悪い偏った食生活や過度な飲酒、喫煙、運動不足・睡眠不足など、不規則な生活習慣も副作用のリスクを高めます。
そのほか、心臓・肝臓・腎臓に既存歴がある方、特定の物質や薬に対するアレルギーがある方も、強い副作用が出る可能性があります。
回数を重ねると副作用が強くなる?
抗がん剤治療の回数を重ねると抗がん剤が体に蓄積されるため、副作用が強くなると考えられています。
とくに、末梢神経がダメージを受けると手足のしびれ・痛みが強くなり、治療後も症状が改善しないケースが少なくありません。
また、治療における体力の消耗により、疲労が蓄積して倦怠感やだるさなどが強くなります。
重度の副作用がある場合、抗がん剤治療の変更・中止が可能です。副作用が強くなってきたと感じた際は、医師・薬剤師に相談しましょう。
抗がん剤治療中にやってはいけないことは?
抗がん剤治療中の注意点は、下記のとおりです。
- 生肉・生魚・グレープフルーツを食べない
- 新薬やサプリメントを服用しない
- 飲酒・喫煙を控える
抗がん剤治療中は著しく免疫力が低下しており、サルモネラ菌や大腸菌による食中毒のリスクが増えます。生の肉や魚は治療が終了するまで控えましょう。
グレープフルーツに含まれるフラノクマリン類は、抗がん剤の分解を阻害して血中濃度を高め、強い副作用を引き起こす恐れがあります。
多くの抗がん剤は肝臓で処理されるため、肝臓に負担をかける飲酒を控え、また、治療効果を低下させてがんの再発や二次がんのリスクを高める喫煙もやめましょう。
そのほか、過度な紫外線のばく露に注意し、病人との接触を避けることも大切です。
まとめ

本記事では、抗がん剤治療による副作用を中心に解説しました。
抗がん剤はがん細胞のみならず、正常な細胞にもダメージを与えてさまざまな副作用を引き起こします。
無理なく治療を継続するためには、適切な食事や十分な休息を心がけ、運動とリラクゼーションを取り入れて副作用の軽減を目指しましょう。
抗がん剤治療の効果の判定には、マイクロCTC検査がおすすめです。マイクロCTC検査は、血中のがん細胞を直接キャッチして個数を1個単位で明示します。
1回5分の採血のみで体に負担がかからないことから、定期的に治療効果の確認や再発の早期発見などに活用できます。
〈参考サイト〉
※1:厚生労働省|重篤副作用疾患別対応マニュアル 抗がん剤による口内炎
※2:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査
