抗がん剤治療は長期にわたるケースが多いことから、治療にかかる費用が心配な方もいるでしょう。
がんの種類や進行度に応じて、薬剤の種類や治療期間などが異なるため、治療費用が大きく変動します。
本記事では、抗がん剤治療の概要・目的・副作用を詳しく解説したうえで、保険適用の可否や治療費用の負担が軽減する方法を紹介します。
治療に専念するために、できる限り経済的な不安を少なくしたい方は、ぜひ参考にしてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

抗がん剤治療とは?

抗がん剤治療とは、がん細胞のDNA合成や細胞分裂を妨げて増殖を抑制する薬剤を用いた治療法です。
がんのステージや全身状態などにより、根治をはじめ、再発・転移の防止、がんによる症状の緩和など、さまざまな目的でおこなわれます。
手術や放射線治療が局所的な治療であるのに対し、抗がん剤治療はより広範囲に作用するため、全身療法に分類されます。
抗がん剤治療は単独の薬剤を使用したり、数種類の薬剤を組み合わせたり、また、ほかの治療法と併用するケースも少なくありません。
はじめに、抗がん剤治療の目的や副作用を紹介します。
抗がん剤治療の目的
抗がん剤治療は、がんのステージや全身状態に応じて次の目的でおこなわれます。
- 根治
- 再発・転移の防止
- 症状の緩和
一部のがん(白血病や悪性リンパ腫など)は、抗がん剤治療のみで根治できます。
また、ほかの治療の効果を高めるために、補助的に抗がん剤治療を併用して根治を目指す「集学的治療」をおこなうケースもあります。
手術と抗がん剤治療を組み合わせた場合、手術前に抗がん剤を用いてがんを縮小させれば、切除範囲が狭まり、治療効果の向上が可能です。
そして、手術後の抗がん剤投与により、肉眼で確認できない微小ながん細胞を完全に根絶させて、再発・転移を防止します。
そのほか、抗がん剤ががん細胞の増殖・成長を抑えることで、がんによる症状の緩和が期待できます。
抗がん剤治療の副作用
抗がん剤は、正常な細胞にも作用するため、さまざまな副作用が現れます。
- 吐き気・嘔吐
- 脱毛
- 下痢・便秘
- 倦怠感
- 口内炎
- 皮膚障害
- 手足のしびれ
抗がん剤による吐き気・嘔吐には、投与後すぐに現れる急性期嘔吐や、投与後2~5日目に発現する遅発期嘔吐、時期に関係なく嘔吐した記憶から誘発される予期性嘔吐があります。
脱毛は、抗がん剤治療の代表的な副作用の一つです。脱毛の程度は使用する薬剤により異なりますが、一般的に治療が終了してからも3~6か月後まで発毛しません。
腸の蠕動運動が活発になると下痢、腸の働きが抑制されると便秘になります。
また、抗がん剤は血球を作っている骨髄に有害な影響を与えるため、赤血球や白血球の減少も頻繁に発生する副作用です。
疲労や筋力低下が生じて倦怠感が現れる場合や、免疫力の低下により口内炎や皮膚障害が伴うケースがあり、そして感染症の発症リスクも増加します。
そのほか、末梢神経が損傷すると手足のしびれが生じることから、転倒・ケガに注意が必要です。
抗がん剤治療の費用は種類・期間で異なる

抗がん剤治療の費用は、使用する薬剤の種類・用量をはじめ、治療期間や入院または通院の期間により大きく異なります。
抗がん剤の薬剤を選択する際には、がんの種類・ステージ、全身の状態のほか、ライフスタイルや希望などを総合的に考慮して決めることが重要です。
使用する薬剤が先発医薬品(新薬)の場合、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の1/4を支払う必要があります。※1
そして、複数の薬剤を併用する場合は、さらに費用が高額になります。
下記は、肺がんを例にした抗がん剤治療の費用です。
| 治療法 | 期間・回数 | 医療費 | 3割負担額 |
|---|---|---|---|
| 術後薬物療法(抗がん剤単独) | 1年間 | 約18~23万円 | 約5~7万 |
| プラチナ併用療法 | 3~4週間 | 約3~20万円 | 約1~6万円 |
| プラチナ・分子標的薬併用療法 | 3週間 | 約40~45万円 | 約12~14万円 |
| 分子標的治療薬 | 4週間 | 約8~75万円 | 約2~23万円 |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | 1回 | 約31~56万円 | 約9~17万円 |
また、治療費とは別に入院期間が長ければ入院基本料や食事代、通院回数が増えるほど診察料・検査料・交通費などの費用の負担が増えます。
抗がん剤治療の費用は保険適用される?
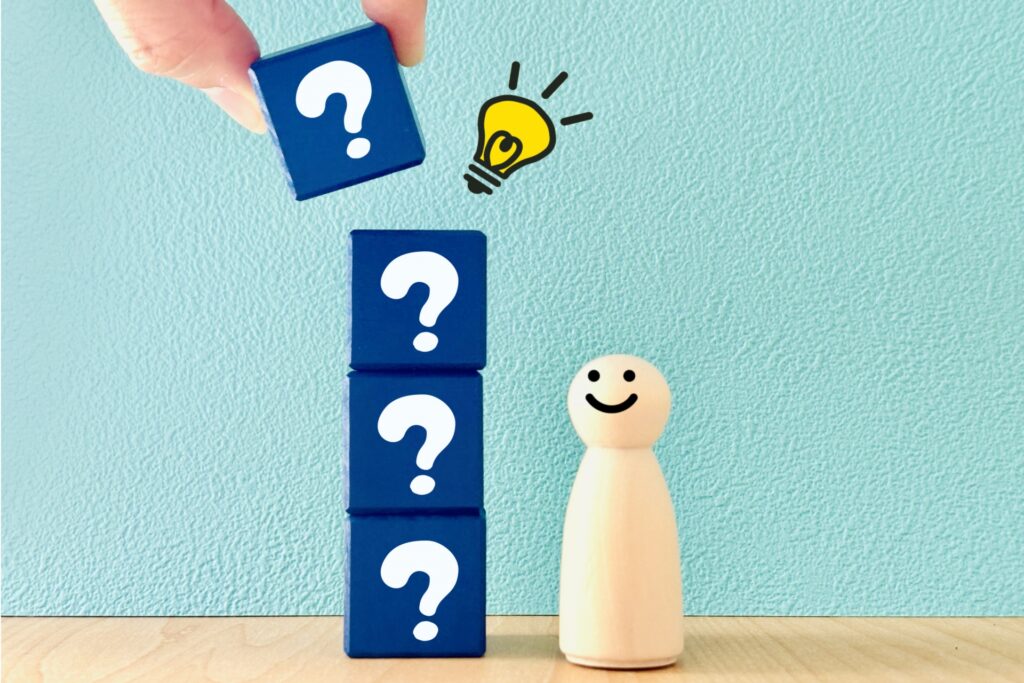
多くの抗がん剤治療は公的保険が適用されますが、一部、保険適用外の自由診療扱いになる場合もあります。
自由診療の費用は完全自己負担となり、高額になるケースも少なくありません。
次章で詳しく解説します。
基本的には保険適用される
大半の抗がん剤治療は、保険診療の対象として公的な健康保険が適用されます。治療費の自己負担は75歳以上で1割、70~74歳までで2割、70歳未満は3割負担となります。
健康保険の適用範囲は、下記のとおりです。
- 薬剤の費用
- 診察費用・検査費用
- 入院基本料
厚生労働省が承認した薬剤(抗がん剤)に限り、保険適用です。調剤薬局で調剤・処方してもらう場合も、調剤技術料や薬学管理料などにも保険が適用されます。
また、診察をはじめ、血液検査、CT検査、X線検査などの費用や、入院における部屋代やベッド代、医療機器の使用料を含む入院基本料も適応対象です。
一方、下記は保険対象外なため、実費となります。
- 医療機関までの交通費
- 食事代や消耗品
- 差額ベッド代
未承認の場合は全額自己負担
抗がん剤治療に、未承認薬・適応外薬を使用する場合があります。
米国(FDA)や欧州(EMA)などの承認は受けているものの、日本人に対する安全性・有効性が十分に確立できず承認されていないため、費用は完全自己負担です。
一般的に、未承認薬・適応外薬を抗がん剤治療に用いる際、本来保険が適用される薬剤、診察・検査、入院にかかる費用はすべて実費になり、経済的な負担は大きくなります。
現在、FDAまたはEMAが承認済みの未承認薬・適応外薬の抗がん剤は、65剤あるといわれており、薬剤費のみで1か月の費用が100万円以上かかるケースも少なくありません。※2
未承認薬・適応外薬は、「十分な治療効果が得られない」「予期せぬ副作用が現れる」などのリスクがあることから、万が一の対応についても事前に医師と話し合いましょう。
抗がん剤治療の費用負担を軽減する方法

ここで、抗がん剤治療の費用負担を軽減する方法を紹介します。
- 高額療養費制度
- 医療費控除
- 傷病手当金
- がん保険
次章では、それぞれの方法を詳しく解説します。
高額療養費制度
高額医療費制度とは、医療機関や薬局で支払った費用が1か月の上限額を超えたとき、超えた金額が支給される制度です。
上限額は、年齢や所得により大きく異なります。また、1年に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、さらに上限額が引き下がります。
個人で1回分の支払額が上限額に満たなくても、複数の受診や同一世帯内で合算できる「世帯合算」が可能です。
高額療養費制度の対象は、保険診療分の自己負担額のみです。自由診療や先進医療、未承認薬を用いた臨床試験に対しては、制度を利用できません。
また、入院時の食事代や差額ベッド代なども対象外です。
制度を利用する際は、加入先の公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽなど)に交付申請書を提出しましょう。
医療費控除
医療費控除は、1年間で支払った医療費の合計が10万円を超える場合、課税対象の所得が控除されて税金の一部が還付される所得控除の一つです。
抗がん剤治療においては、保険診療・自由診療にかかわらず利用できます。
薬剤をはじめ、診察・治療、入院、通院の費用や、治療・療養に必要な医薬品の購入費、医療用器具の購入費やレンタル費用などが対象です。
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
まず、1月1日~12月31日までの期間で、納税者本人または生計を一にする親族にかかった医療費の合計額を算出します。
次に、高額療養費や入院費給付金などで補てんされる金額と、10万円(総所得200万円未満は総所得×5%)を差し引き、確定申告書に記載して必要書類とともに提出します。
還付金は、申請から1~2か月程度で受け取ることが可能です。
傷病手当金
傷病手当金は、病気・ケガにより働けないときに、本人や家族の生活を保障するために設けられた制度です。
仕事を休み始めた日から連続する3日間を待機期間とし、4日目から最長1年6か月まで、給与の約2/3が支給されます。
原則、会社員や公務員などで健康保険に加入している方が対象です。自営業や個人事業主などで国民健康保険の加入者は、傷病手当金を受け取れません。
また、休業中も給与が全額支払われる場合や、障害厚生年金または障害手当金、休業補償給付などを受けている際は、支給額の一部または全部が調整されます。
傷病手当金は、勤務先に長期間の休業が必要な旨を報告したうえで、加入先の傷病手当金支給額申請書と必要書類を提出し、問題がなければ2週間~1か月程度で受け取れます。
がん保険
保険会社のがん保険には、抗がん剤治療を受けた際に給付金が支払われる特約があります。
また、先進医療特約を付帯していれば、厚生労働省が定める先進医療の技術料と同額を受け取ることが可能です。
そのほか、抗がん剤治療に関連するさまざまな特約があります。
- がん診断一時金特約
- がん入院特約
- がん通院特約
- がん保険料払込免除特約
がん診断一時金特約は、がんと診断された際に受け取れて、今後の治療費に活用できることが強みです。
また、がんによる通院や入院に関する特約では、契約時に設定した日額をもとに算出した給付金が支払われます。
がん保険料払込免除特約は、がんと診断された、または特定の手術・治療を受けて労働制限がある場合、保障を継続しながらも保険料払込が免除されるため、治療に専念できます。
高額な抗がん剤治療の費用を払えない場合の対処法

抗がん剤治療は長期化する傾向にあり、ほかの治療法より治療費が高額になりがちです。
しかし、高額療養費制度や医療費控除などは、申請から給付金の受け取りまで時間がかかるため、費用が払えず治療の継続が困難になるケースも少なくありません。
次章では、抗がん剤治療の費用を払えない場合の対処法を紹介します。
高額療養費貸付制度を活用する
高額療養費貸付制度とは、高額療養費で払い戻される予定金額の8割を無利子で借りることが可能です。
申し込みには、下記が必要です。
- 医療機関の医療費請求書(保険点数が明記されたもの)
- 高額医療費貸付金借用書
- 高額療養費支給申請書
高額療養費の支給は少なくとも3か月程度かかるため、抗がん剤治療の費用が払えない際は貸付制度を活用して当座の医療費に充てましょう。
医療ローンを利用する
医療ローンは、銀行や信販会社などの金融機関で取り扱っている商品です。用途は医療関連に限られており、抗がん剤治療にも利用ができます。
ほかのローンと同様に審査があり、信用情報や収入、返済能力などが確認されます。
審査を通過した場合は、借りる前に返済計画を立てて無理のない範囲で利用しましょう。
治療後のがん再発が不安な方にマイクロCTC検査がおすすめ

マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで全身のがんリスクがわかる画期的な検査です。
血中のがん細胞をキャッチして個数を1個単位で明示するため、治療後のがん再発の早期発見にも役立ちます。
そのほか、がんの進行度の確認や治療効果の評価にも有用です。
ここからは、マイクロCTC検査の概要と特徴を紹介します。
マイクロCTC検査の仕組み
マイクロCTC検査は、増殖の過程で血中に漏れ出すがん細胞の性質に着目した血液検査です。
がん細胞は、酸素や栄養を求めて血管に浸潤して血中を巡ることがわかっています。
血中のがん細胞は、免疫細胞の攻撃により消滅するため発症に至らないケースが多いです。
しかし、一部の間葉系がん細胞は、周囲の組織に浸潤・転移する能力を獲得しており、全身のさまざまな臓器に影響を与えます。
マイクロCTC検査は、悪性度が高い間葉系がん細胞のみを1個単位で検出し、がんの発症・再発・転移の予兆を早期に発見します。
高精度・迅速な検査体制を実現
マイクロCTC検査は、全米のがん治療におけるBest Hospitals No.1の「MDアンダーソンがんセンター」が開発したCSV抗体を利用し、高精度を実現しています。※3
悪性度が高い血中のがん細胞を特異度94.45%で捉えるため、結果に大きな信頼・納得感が得られます。※4
また、国内に民間初となる自社検査センターを設けていることも、マイクロCTC検査の特徴の一つです。
血液検体は、海外に輸送すると品質が劣化し、正確な分析・診断ができない恐れがあります。
マイクロCTC検査の場合、血液検体は採血後すぐに国内の検査センターに到着し、AI分析と専門の検査技師による解析を迅速に実施しています。
高精度・高品質なマイクロCTC検査を定期的に活用して、いち早くがんを見つけましょう。
全国のクリニックで受診可能
マイクロCTC検査は、全国の提携クリニックで導入しており、自宅・勤務先の近隣や外出先などで気軽に受診ができます。
また、全国で同様の高精度な検査が受けられることから、転勤や引っ越しの際も安心です。
検査予約から結果確認までWebで完結するため、仕事が忙しい方や家事・育児で時間の確保が難しい方でも受診しやすいでしょう。
そして、充実したアフターフォローもマイクロCTC検査の魅力です。
がん細胞が検出された方には、マイクロCTC検査センター長、および代々木ウィルクリニックの太田医師による無料相談を実施しています。
検査結果の詳しい説明をはじめ、精密検査の案内や専門の医師・医療機関の紹介などに対応し、受診者の不安の軽減に取り組んでいます。
抗がん剤治療の費用に関するよくある質問
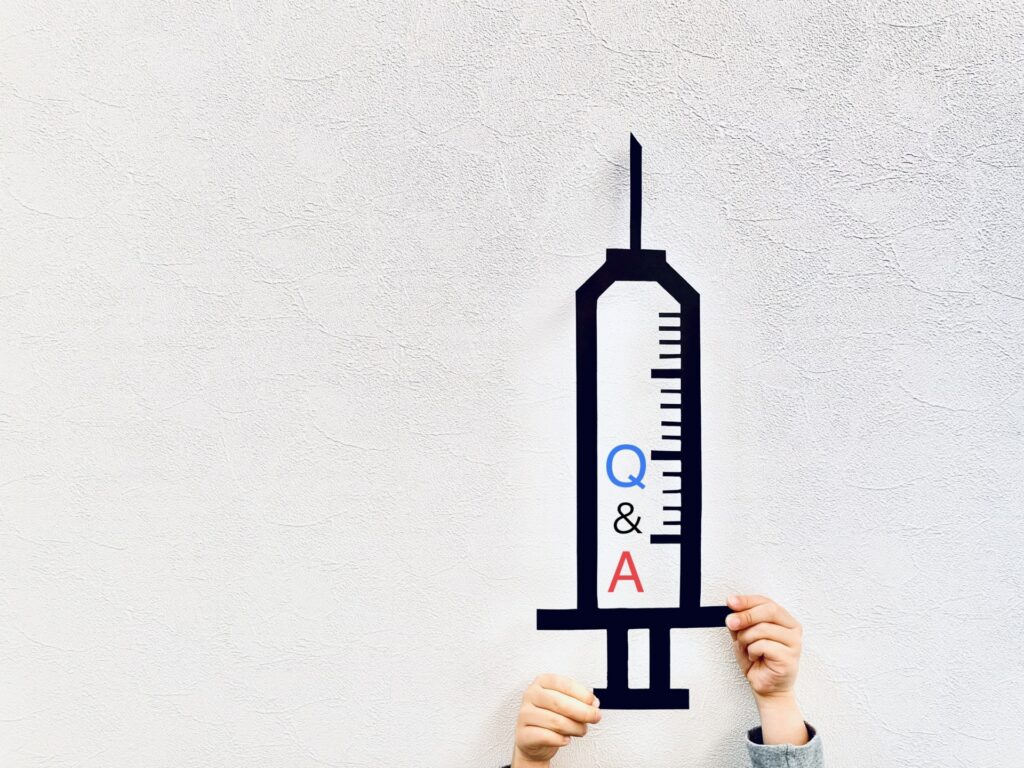
最後に、抗がん剤治療の費用に関するよくある質問を紹介します。
これから抗がん剤治療を受ける方、または検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
抗がん剤治療の費用の内訳は?
抗がん剤治療にかかる費用内訳をまとめました。
- 薬剤料(投薬料含む)
- 診察料
- 検査料(血液検査、CT・X線・エコーなどの検査)
- 入院基本料
- 調剤薬局で支払う費用(調剤技術料・薬学管理料・薬剤料・特定保険医療材料料含む)
そのほか、通院における交通費、診断書や証明書の作成料、入院する際の日用品・消耗品の費用などが発生します。
また、個室や2人部屋などを利用した場合の差額ベッド代、副作用で脱毛した際のウィッグ代金などがかかることを見込んでおきましょう。
抗がん剤治療は入院が必要?
抗がん剤治療の初回の1サイクルは、入院が必要になるケースが多いです。
一般的に、抗がん剤治療は薬剤の用量・用法、治療期間が示された「レジメン」と呼ばれる治療計画をもとにおこなわれます。
抗がん剤を注射または点滴で投与する場合、投与日と休薬日を組み合わせた周期(サイクル)を繰り返します。
一般的に、抗がん剤治療の1サイクル目は、体調変化や副作用の観察・対応のため、入院が必要です。その後は、薬剤によっては通院で診察・検査を実施したうえで薬剤の投与を受けます。
しかし、状態の悪化や強い副作用がみられた、感染症・合併症が起こったなどの場合、入院が必要となります。
ホルモン療法とは?
ホルモン療法は、体内のホルモンの分泌を抑制してがん細胞の増殖・成長をコントロールする治療法です。
おもに、ホルモン受容体陽性の乳がんや子宮体がん、男性ホルモンに依存性をもつ前立腺がんなどに対しておこなわれます。
正常な細胞にもダメージを与える抗がん剤治療と比べて、副作用が少ないことがホルモン療法の特徴です。
しかし、心血管、血栓症、脂質代謝異常、糖尿病などの疾患発症リスクが上昇する可能性があります。
まとめ
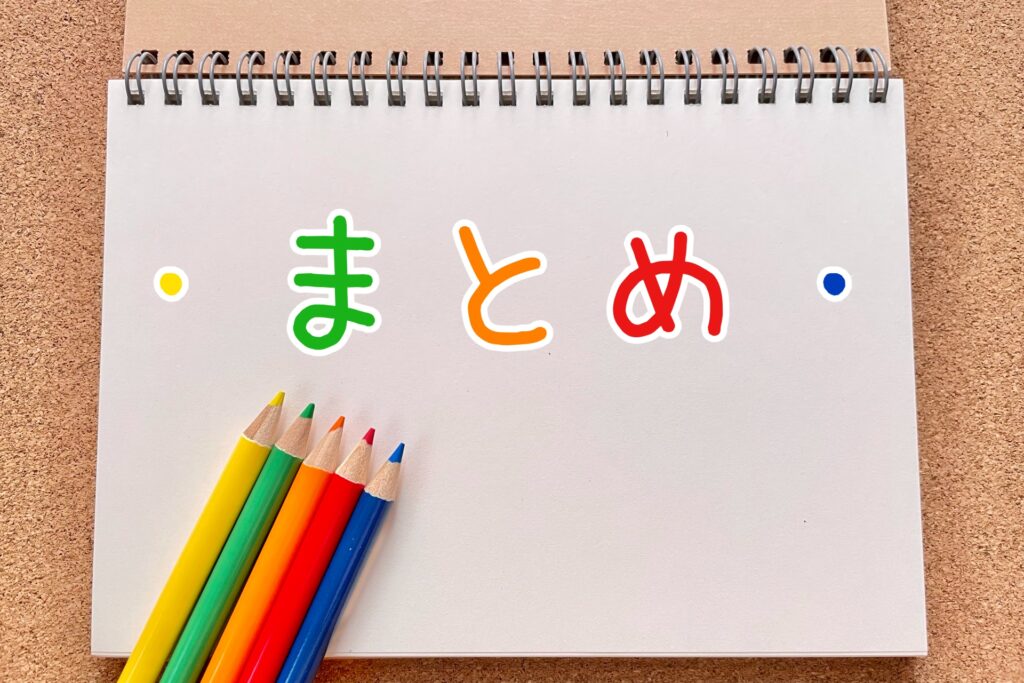
本記事では、抗がん剤の治療費用に関する情報を中心に解説しました。
抗がん剤治療は、がんの種類や進行度に応じて薬剤の種類や治療期間などが異なり、費用が大きく変動します。
通常、公的医療保険が適用されますが、日本で未承認の薬剤を使用する場合は全額自己負担となり、費用は非常に高額になります。
費用負担を軽減するには、高額療養費制度、医療費控除、傷病手当金などの公的制度や、がん保険の活用が有効です。
また、費用を払えない場合は、高額療養費貸付制度や医療ローンも検討しましょう。
治療後のがん再発が不安な方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
1回5分の採血のみで、血中を循環する悪性度の高いがん細胞を特異度94.45%で検出します。※5
定期的に活用すれば、全身のがんリスクはもちろん、再発・転移の予兆が早期に把握できるため活用してみてはいかがでしょうか。
〈参考サイト〉
※1:厚生労働省|後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
※2:国立がん研究センター|海外承認済み、国内未承認の抗がん剤リスト更新
※3:U.S. News & World Report|Best Hospitals for Cancer in the U.S.
※4、※5:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査
