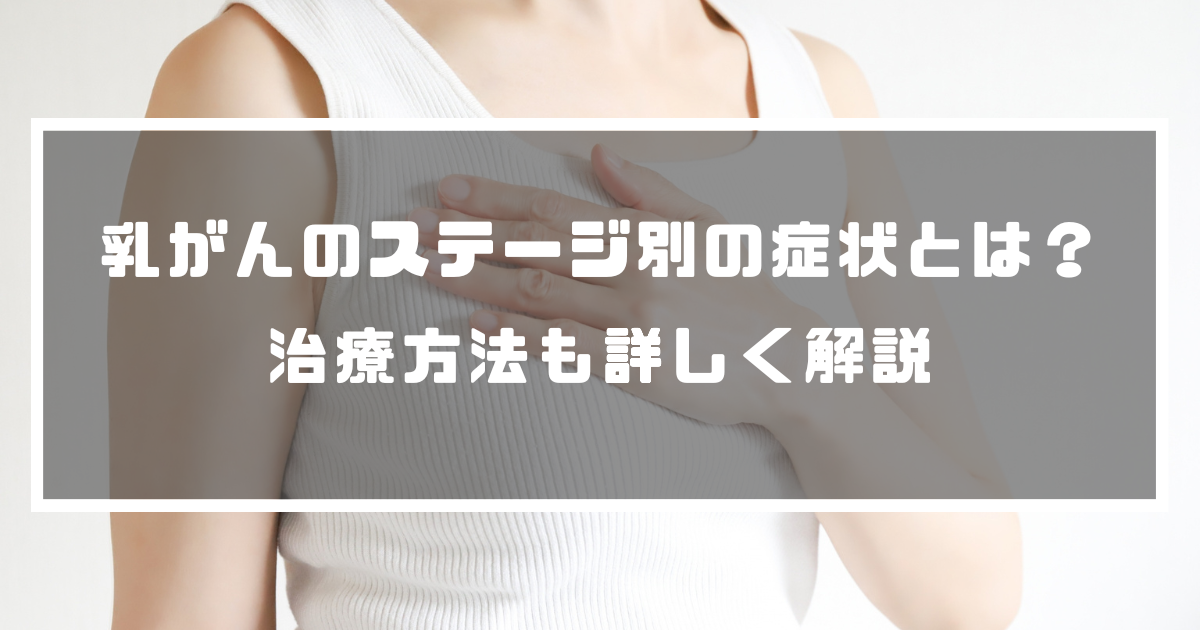乳がんは日本女性のがんのなかで最も罹患数が多く、比較的若い世代から罹患者数が増す特徴があります。
近年では乳がんになる方がさらに増え、日本女性の約9人に1人が乳がんと診断されると報告されています。
乳がんの発見や治療が遅れた場合、治療による身体への負担が増すほか、乳房を失うリスクも高まるでしょう。
本記事では乳がんの特徴やステージ(病期)、検査方法や治療法などについて解説します。
乳がんについて不安がある方や、乳がんを早く見つけるための検査方法について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

乳がんとは

乳がんとは乳腺と呼ばれる組織にできるがんです。
女性の罹患率が圧倒的に高いものの、男性にも罹患するケースがあり、治療方針や予後は男女で共通しています。
乳がんの好発部位は乳房にある乳腺の一部、乳汁の通り道である乳管です。乳汁を作る組織である腺房の集まり、小葉にて乳がんが発生するケースもあります。
乳がんは早期発見により適切な治療をおこなえば、命にかかわる可能性を抑えられます。
まずは乳がんの特徴と症状について解説します。
非浸潤がんと浸潤がん
乳がんは、がんの広がりの度合いにより非浸潤がんと浸潤がんに分類されます。
非浸潤がんは乳管や小葉の内部のみに確認できる乳がんです。
初期に発見できる乳がんの多くは非浸潤がんです。非浸潤がんでは適切な治療や手術により完治が見込めることに加え、ほかの組織やリンパ節への転移は非常に稀とされています。
一方、乳がんの進行にともない、がん細胞が乳管や小葉からがん細胞が飛び出すことを浸潤と呼びます。
浸潤を起こしたがんは浸潤がんとなり、がん細胞がリンパ管や血管に入り込んで転移を起こすリスクが高まります。
浸潤がんになる前に乳がんを発見するため、定期的ながん検診とセルフチェックを欠かさないようにしましょう。
乳がんの症状
がん検診で乳がんを早期に発見した場合には、乳がんによる自覚症状がないことも多いでしょう。
しかし乳がんの進行にともない、乳房や胸の周囲に次のような変化が生じる場合があります。
- 乳房や脇の下のしこり
- 脇の下の腫れ
- 乳房の痛みや違和感
- 乳房の形や皮膚の変化
- 乳頭からの分泌物
- 乳頭や乳輪のただれ
- 乳頭や乳房のくぼみ
主な自覚症状は乳房のしこりであり、しこりの硬さや形状はさまざまです。
乳頭から分泌物が出たり、ただれや陥没を起こしたりする場合もあります。
脇に副乳と呼ばれる乳腺がある方の場合には、脇の下に乳がんができ、しこりを生じる場合もあります。
乳房や乳頭に加え、脇をはじめとする胸の周辺の状態もチェックすべきでしょう。
関連記事
乳がんの検査方法

乳がんを診断するための検査方法には、視触診、マンモグラフィ検査、乳房エコー検査、穿刺吸引細胞診などがあります。
ここではそれぞれの検査の特徴について解説します。
視触診
視診では、乳房の異状なふくらみや、ただれ、くぼみ、乳頭からの分泌物、乳房の形の左右差などをチェックします。
触診は、目で見てわからないしこりを探すためにおこなわれます。乳房内にしこりがないかどうか、脇周辺のリンパ節が硬くなる、増大していないかなどを、医師が手で触れて確認するものです。
マンモグラフィ検査
マンモグラフィ検査は、がんをはじめとする病変の位置や性状を確かめる乳房専用のX線検査です。
マンモグラフィ検査では乳房を板で挟んで圧迫し、乳腺組織と脂肪組織を均等に広げたうえで撮影します。
撮影時にはできる限り重なりなく引き伸ばすことで、微細な変化や異常をより鮮明に捉えられます。
検査の精度を上げるための乳房への圧迫により、痛みを感じる場合もあるでしょう。
マンモグラフィ検査は乳がんでよくみられる石灰化の発見にとくに役立ちますが、一方でX線の使用により被ばくのリスクがある点には注意が必要です。
乳房エコー検査
乳房エコー検査では、乳房内の病変やしこりの性状や大きさ、脇の下のリンパ節などへの転移の有無を超音波により調べます。
視診や触診でわかりにくい病変部位も、乳房エコー検査であれば見つけやすいでしょう。
マンモグラフィ検査では病変部位と乳腺が同じ白色で表示されるため、病変の特定が難しい場合があります。
一方で乳房エコー検査では、異常のある部位が黒く映り、正常な乳腺は白く映るため、病変部位を特定しやすいメリットがあります。
さらに乳房エコー検査ではX線を使用しないため、被ばくの影響が懸念される妊娠中の方でも安心して受けられるでしょう。
穿刺吸引細胞診
検査からしこりが見つかり、より詳細な検査が必要と判断された場合には穿刺吸引細胞診がおこなわれます。
穿刺吸引細胞診は、一般的な採血の針よりも細い注射針を病変部位に刺して、同部位にある細胞を採取する検査です。
基本的に局所麻酔は使用せず、痛みは腕から採血する程度とされています。
吸引した細胞が顕微鏡で詳しく調べられたのち、診断の確定に進みます。
関連記事
乳がんのステージ(病期)

乳がんには病気の進行の程度を数値で表したものとしてステージ(病期)があります。
ステージにより治療方針が変わるため、適切なステージの決定は非常に重要です。
乳がんのステージは主に次の3つの要素で決まります。
- 腫瘍のサイズ
- リンパ節への転移の有無
- 多臓器への転移(遠隔転移)の有無
それぞれのステージの特徴について解説します。
ステージ0
ステージ0の乳がんは非浸潤がんであり、最もステージの低い初期の段階です。
非浸潤がんは乳管や小葉の内部のみに確認できる状態のため、腫瘍もしこりとして認識できない小さなものであることが多いでしょう。
非浸潤がんではほかの組織への転移は非常に稀とされており、リンパ節転移や遠隔転移のないものがステージ0に分類されます。
ステージI
ステージⅠから上のがんでは浸潤が見られ、腫瘍のサイズが大きくなるほか、転移の可能性が出てきます。
しかしステージⅠでは腫瘍が2cm以下の比較的小さな段階であり、リンパ節転移も遠隔転移も基本的には見られません。
ステージII
ステージⅡは、腫瘍の大きさによりⅡAとⅡBの2つに分類されます。
ほかの臓器への遠隔転移は見られないものの、次のような腋窩リンパ節への転移の可能性がある点に注意が必要です。
| ステージ | 転移や腫瘍の状態などの特徴 |
| ⅡA | ・腫瘍の大きさが2cm以下、腋窩リンパ節に転移(固定や癒着なし) ・腫瘍の大きさが2~5cm、転移なし |
| ⅡB | ・腫瘍が2~5cm、腋窩リンパ節に転移(固定や癒着なし) ・腫瘍が5cm以上、転移なし |
転移がある場合もない場合も、より腫瘍の大きいものがステージⅡBに分類されます。
ステージⅢ
ステージⅢの乳がんはさらにⅢA、ⅢB、ⅢCの3つに分類されます。リンパ節への転移が見られることが多いものの、ほかの臓器への遠隔転移は見られません。
| ステージ | 転移や腫瘍の状態などの特徴 |
| ⅢA | ・腫瘍が5cm以下、腋窩リンパ節に転移(固定や癒着あり) ・腫瘍が5cm以下、内胸リンパ節に転移 ・腫瘍が5cm以上、腋窩リンパ節か内胸リンパ節に転移 |
| ⅢB | ・リンパ節への転移の有無にかかわらず、がんが胸壁に固定されている ・がんが皮膚に出たり皮膚が崩れたり、むくんだりする ・しこりがない炎症性乳がんである |
| ⅢC | ・腋窩リンパ節と内胸リンパ節の両方に転移がある ・鎖骨の上か下のリンパ節に転移がある |
乳がんのステージⅢでは、しこりが急激に大きくなる、乳房の見た目が変化する、痛みが増える、などの症状が現れる場合もあります。
ステージⅣ
乳がんが骨や肝臓、肺、脳などのほかの組織へ遠隔転移している場合、ステージⅣに分類されます。
がんの大きさやリンパ節転移の有無にかかわらず、遠隔転移があればすべてステージⅣとなる点に注意が必要です。
乳がんの治療法

乳がんの治療は、乳癌診療ガイドラインを基本として、乳がんのステージや患者の生活状態や状態にあわせておこなわれます。
主な乳がんの治療法は次のとおりです。
- 外科手術
- 放射線治療
- ホルモン療法
- 化学療法
- 分子標的療法
- ラジオ波熱焼灼療法
それぞれの治療法について詳しく解説します。
外科手術
主にステージ0~ⅢAの乳がんに対しておこなわれる治療法です。
術式には主に次のようなものがあり、いずれの方法でも術後の生存率に違いはないとされています。
| 手術法 | 特徴 |
| 乳房部分切除術 | ・腫瘍とその周囲の正常な乳腺を切除 ・乳房の温存が可能 ・再発防止のために術後の放射線照射が必要 |
| 乳房切除術 | ・乳頭乳輪を含めた全乳房を切除 ・術後の放射性照射の必要がない |
| 乳頭乳輪温存乳房切除 | ・乳頭乳輪および皮膚を残して乳腺のみを切除 ・乳房再建の追加により見た目を保ちやすい |
腫瘍の大きさや広がり、患者自身の希望を総合的に判断して術式が決まります。
放射線治療
放射線治療は、乳房周辺の再発である局所再発を防ぐためにおこなわれる治療法です。
乳房部分切除術により残存した乳房や、乳房周囲のリンパ節に照射します。
また、骨や脳などへの遠隔転移が見られる症例に対しては、症状の緩和のために照射する場合もあります。
ホルモン療法
乳がんの術後には、再発を予防するためにホルモン治療をおこなう場合があります。
乳がんは、女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロンなどの刺激の受けやすさにより、複数のサブタイプに分類されます。
ホルモン受容体が陽性であり、女性ホルモンの刺激を受けやすい乳がんであるルミナルタイプには、女性ホルモンの刺激を抑えるホルモン療法が有効です。
エストロゲンを増やすメカニズムが閉経前と閉経後で異なるため、月経の有無により異なる薬剤でのホルモン療法がおこなわれます。
化学療法
乳がんのサブタイプのひとつであるルミナルタイプのうち、腫瘍の増殖力が高いルミナルBタイプには、多くの場合、ホルモン療法に加えて抗がん剤を用いた化学療法がおこなわれます。
さらにホルモン感受性が陰性の、HER2型やトリプルネガティブと呼ばれるタイプの乳がんにも、化学療法は効果的です。
化学療法は乳がんの術後に、再発の予防や病気の進行を抑える目的でおこなわれますが、脱毛や倦怠感、神経障害、骨髄の機能の抑制などの副作用が生じる点に注意が必要です。
化学療法は、腫瘍を小さくしたり化学療法の効果を判定したりする目的で、手術前におこなわれる場合もあります。
分子標的療法
分子標的療法は、がん細胞が増殖するために必要な特有の因子を狙い撃ちする治療法です。
一般的な抗がん剤は、がん細胞と正常細胞のいずれも攻撃するため、正常細胞のなかでも増殖が盛んな髪の毛や消化管の細胞などがダメージを受け、脱毛や吐き気をはじめとする副作用が起こります。
しかし分子標的治療ではがん細胞の増殖に関係するたんぱく質に作用するため、一般的な抗がん剤よりも少ない副作用で大きな効果が期待できるとされています。
分子標的療法は、標的の分子に対応する薬がある場合にのみ受けられる点に注意が必要です。
ラジオ波熱焼灼療法(RFA)
ラジオ波熱焼灼療法は、細い針状の電極を差し込んでラジオ波帯の電流を流し、発生する熱を利用してがん細胞を死滅させる治療法です。
手術による乳房切除よりも見た目を保ちやすく、さらに患者への身体的負担を比較的抑えやすいことがラジオ波熱焼灼療法のメリットです。
ラジオ波熱焼灼療法は、治療成績が乳房切除に劣らないこと、乳房を切らないために整容性が優れていることが臨床試験により証明され、切らない治療として2023年12月に保険適用となりました。
腫瘍が1.5cm以下の乳がんで、かつリンパ節やほかの組織への転移がない場合、ラジオ波熱焼灼療法による治療が可能です。
乳がんステージ(病期)ごとの治療方法

乳がんにおいて選択される治療法は、ステージにより大きく異なります。
ここからは各ステージにおける治療方針について解説します。
ステージ0
ステージ0の乳がんでは、手術による腫瘍部位の切除がおこなわれます。
乳房部分切除術では術後の再発防止のため、放射線治療が必要です。
また、転移の可能性を調べるため、センチネルリンパ節生検をおこなう場合もあります。
センチネルリンパ節は、乳がんが転移する際に最初に到達するリンパ節です。
センチネルリンパ節への転移がなければ、ほかのリンパ節にも転移していない可能性が高いと考えられるため、リンパ節の摘出の必要性を決めるための検査として有効です。
ホルモン受容体が陽性のルミナルタイプの乳がんでは、術後にホルモン療法薬を用いた薬物療法がおこなわれる場合もあります。
ステージI~ⅢA
ステージⅠ~ⅢAの乳がんでも同様に、手術による腫瘍周辺の部位の切除がおこなわれます。
腫瘍が小さい場合には乳房部分切除術が可能ですが、腫瘍が大きかったり広がったりしている場合には、乳房全切除術が必要です。
術前に薬物療法をおこなうことで、乳房部分切除術をおこなえるレベルにまで腫瘍を小さくできる可能性もあります。
また、術後にも転移を防ぐため、放射性治療や薬物療法をおこなう場合があります。
腋窩リンパ節への転移がある場合には、リンパ節郭清と呼ばれるリンパ節の切除術も必要です。
ステージⅢB~Ⅳ
ステージⅢB~Ⅳの治療は、がん細胞の性質や体の状態、本人の希望などを考慮したうえでおこなわれます。
ホルモン療法薬や抗がん剤などを用いた薬物療法が主ですが、ステージⅢBやⅢCでは薬物療法の効果に応じて、手術や放射線療法を組みあわせる場合もあるでしょう。
ステージⅣでは、ほかの組織へ転移したがんの症状を和らげる治療もあわせておこないます。
症状の緩和に効果的であると判断されれば、ステージⅣにおいても手術や放射線療法が追加されます。
がんの早期発見には「マイクロCTC検査」

乳がんの早期発見に役立つ検査として、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査では、1回5分の採血のみで乳がんをはじめとする全身のがんリスクについて明確に調べられます。
ここからは、マイクロCTC検査の特徴について解説します。
悪性度の高いがん細胞を捉える
マイクロCTC検査では、採血により血液中に漏れ出した間葉系がん細胞そのものを高い精度で検出します。
間葉系がん細胞は他の臓器に転移したり組織に浸潤したりする性質があるため、がん細胞のなかでも悪性度が高いがん細胞とされています。
マイクロCTC検査では間葉系のがん細胞の個数や、がん細胞が存在する身体の位置までわかるため、全身のがんリスクを明確化できます。
悪性度の高いがん細胞を早い段階で捕捉できるマイクロCTC検査で、がんを早期に発見し、治療へつなげましょう。
1回5分の採血のみで検査できる
マイクロCTC検査は1回5分の採血のみで、全身のがんリスクをチェックできます。
検査にかかる時間が短いため、仕事や家事、育児などで忙しい方でもスキマ時間を活用して精度の高い検査を受けられます。
採取する血液も少量で済むため侵襲性が低く、痛みや違和感を抑えやすい方にもおすすめです。
また、マイクロCTC検査を受けられるクリニックは、北海道から沖縄まで全国に約140件あります。
現住所の都道府県、あるいは隣県での検査が可能であるため、泊りがけで検診の予定を立てる必要もありません。
検査にかかる時間や検査による身体への負担が気になる方は、ぜひマイクロCTC検査を試してみましょう。
検査後のアフターフォローも充実
マイクロCTC検査は検査後のアフターフォローも充実しています。
マイクロCTC検査でがん細胞が検出された方は、マイクロCTC検査センター長である、代々木ウィルクリニックの太田医師による相談を無料で受けられます。
遠方に住んでいる方はオンラインでの面談もできるため、クリニックまで通う必要もありません。
充実したアフターフォローをあわせて受けたい場合にも、マイクロCTC検査はおすすめです。
まとめ
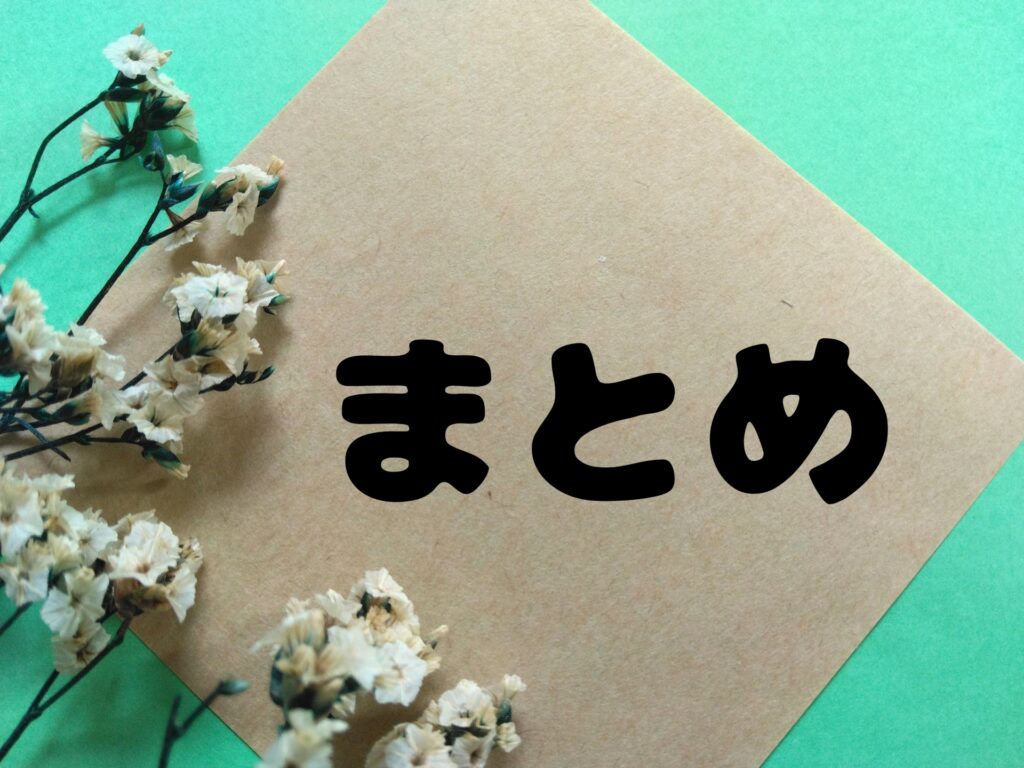
乳がんは女性の罹患率が圧倒的に高く、近年ではさらに罹患率の増加が見られています。
乳がんのステージが進むと治療による身体への負担も大きくなり、乳房を失う可能性も高まるため、がん検診やセルフチェックによる、ステージが低い段階での早期発見が重要です。
定期的ながん検診を受けるとともに、しこりや痛み、乳房の変形などの気になる症状がある方は、早めに受診して検査を受けましょう。
乳がんを含む全身のがんリスクを手軽かつ高い精度で調べたい方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
1回5分で全身のがんリスクをチェックできるため、がんの発症に不安のある方や、より検査を短時間で済ませたい方はぜひ試してみましょう。
<参考文献>
国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ|乳がんについて
国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ|乳がん 治療
国立がん研究センター|早期乳がんに対するラジオ波焼灼療法による切らない治療が薬事承認・保険適用を取得 先進医療制度下で実施した医師主導特定臨床研究の成果を活用