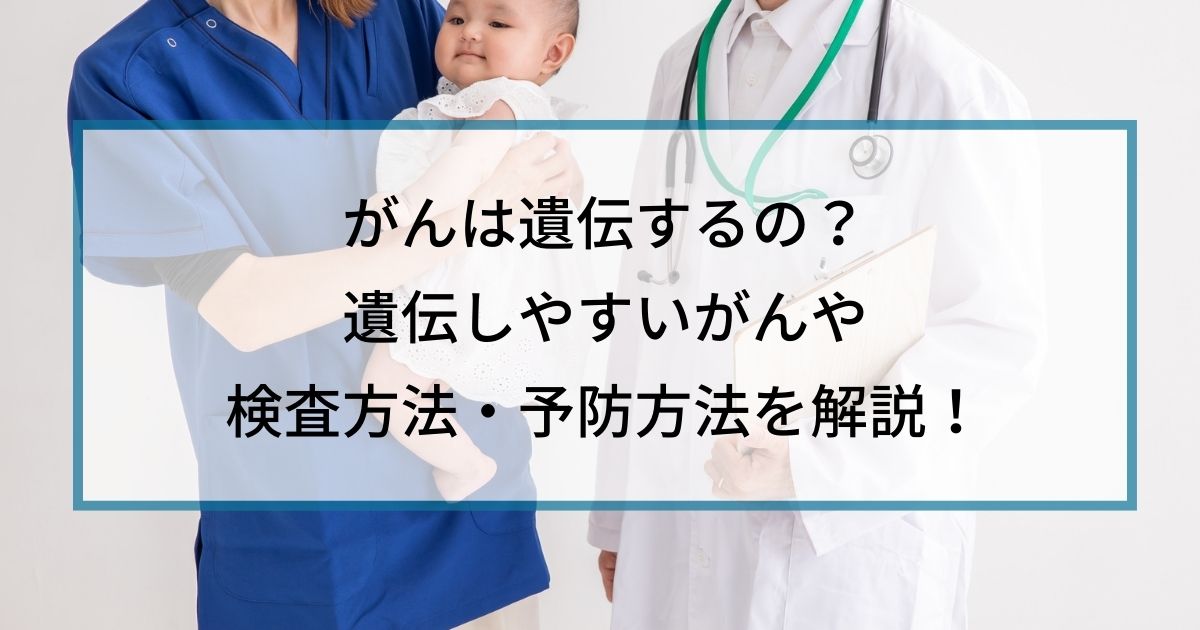家族のがんの発症を機に自身もがんになりやすいと考えている方もいるのではないでしょうか。
がんは、2人に1人が生涯で発症するといわれています。
正常な遺伝子が変化して発症する病気ですが、がんの発症と遺伝には一部関係性が認められています。
本記事では、がんの遺伝に関して次の内容を解説します。
- がんと遺伝の関係
- 遺伝しやすいがんの種類
- 遺伝性のがんを調べる方法
- がんを予防する方法
本記事を一読すれば、がんの発症に関する仕組みや予防方法まで、深く理解できるようになるでしょう。
がんの発症に対する不安を取り除くために、本記事の内容をぜひ参考にしてみてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

がんは遺伝するのか?

がんは遺伝すると考えられがちですが、がんが遺伝するわけではなく、体質が遺伝するケースがあるのみで、すべてのがんは遺伝しません。
がんの発生は、遺伝子に変化が起こり、遺伝子が正常に機能しなくなる要因で発生します。
遺伝子が正常に機能しなくなる要因に、一部、がんになりやすい体質の遺伝に起因するケースがあり、がんが遺伝すると誤って認識されているわけです。
多くのがんは遺伝しない
先述したとおり、多くのがんは遺伝しない傾向にあります。いずれのがんも、生まれたあとに後天的な遺伝子の変化が生じて発症しているためです。
もちろん、遺伝子に後天的な変化が生じたあとも、がん細胞に変化した遺伝子自体は遺伝しません。
なお、後天的な遺伝子の変化に伴うがんの発症における原因は、主に環境要因が引き金となります。
がんの発症に起因する主な環境要因は、次のとおりです。
がんの発症に起因する主な環境要因
- たばこ
- 紫外線
- 食生活
- 加齢
- アスベスト
環境要因は、それぞれ発生する状況が異なるため、自身の生活背景によってがんの発症リスクが変わっているといえるでしょう。
生まれながらの遺伝子変異は、次の世代ヘ遺伝の可能性がある
生まれながらに遺伝子変異を起こしやすい体質(がんになりやすい体質)は、次の世代へ遺伝する可能性があります。
がんの発症が、遺伝子変異を起こしやすい体質の遺伝に起因する割合は、がん患者全体の5~10%程度です。
遺伝子変異が起こりやすい体質の遺伝によりがんが発症するケースは、全体のがんを発症している患者数の中では、少なく感じる方もいるでしょう。
しかし、実際に遺伝子変異が起こりやすい体質は、約50%で遺伝します。
子どもは親からの遺伝子を受けついでいるため、遺伝子に環境要因以外で変異が認められた場合は、高い確率で遺伝子変異を起こしやすい体質が遺伝していると判断できます。
また、体質が遺伝するのは、がんを発症した親の子どもではなく、孫にあたる世代で遺伝するケースが多い傾向にあるでしょう。
したがって、早い段階で遺伝子検査を受診して体質遺伝をチェックしておき、事前の予防や健康対策でリスクをおさえておく必要があります。
遺伝性腫瘍とは?

遺伝性腫瘍とは、がんの原因が環境要因ではなく、変異しやすい遺伝子の遺伝に起因して発症したがんです。
環境要因に起因するがんの発症に比べると、発症の割合は少ないものの、予期せぬ際に発症するリスクがあるため、遺伝性腫瘍の特徴をおさえておくとよいでしょう。
遺伝性腫瘍の特徴は、次のとおりです。
遺伝性腫瘍の特徴
- がん抑制遺伝子が生まれつき変異している
- 一般の方よりもがんになりやすい
- 全体のがん患者の中の1割程度
- がんそのものが遺伝するわけではない
がん抑制遺伝子が生まれつき変異している
がん抑制遺伝子は、正常な細胞の変異によるがんの発症を抑制する遺伝子であり、父親と母親から一つずつ受け継いだ染色体二つが補いあってがんを抑制します。
しかし、遺伝性腫瘍が遺伝した場合は、生まれたときから片方の染色体が変異した状態のため、実質的には染色体一つでがんを抑制する必要があります。
ただし、生まれつき片方の染色体のみでも、もう片方の正常な遺伝子ががんの発症を抑制する機能を担うため、すぐにがんが抑制できず遺伝性のがんが発症するわけではありません。
最終的に残っていた正常ながん抑制遺伝子の機能を有した染色体が変異し、がんの抑制機能が低下した結果、がんを発症するとされています。
一般の人よりもがんになりやすい
遺伝性腫瘍が遺伝した場合は、一般の方よりもがんになりやすいといわれています。
一般の方よりもがんになりやすい要因は、本来、がんの発症を抑制する正常ながん抑制遺伝子が一つしかないためです。
遺伝性腫瘍が遺伝していない一般の方は、がん抑制遺伝子が二つともがんの発症抑制に正常に機能するため、遺伝的な要因から、がんになるリスクはありません。
遺伝性腫瘍が遺伝している方は、遺伝的要因のリスクの高さに加えて、環境要因によるがんの発症リスクも上乗せされます。
したがって、がんの発症が環境要因のみにしか起因しない一般の方と比べると、遺伝性腫瘍が遺伝している方のがんになりやすい確率は高いといえるでしょう。
全体のがん患者の中の1割程度
遺伝性腫瘍が遺伝している場合におけるがんの発症は一般の方よりも高めですが、がんの発症の背景全体からみると、遺伝性腫瘍による発症率は1割程度になります。
参考までに、一部に遺伝性腫瘍が認められている代表的ながんである新規乳がん患者と新規卵巣がん患者における遺伝性腫瘍の割合をみてみましょう。
| 全体の患者数(年間) | 遺伝性腫瘍数 | |
|---|---|---|
| 新規乳がん患者 | 約6万人 | 約1,800~3,000人(約3~5%) |
| 新規卵巣がん患者 | 約9,000人 | 約900人(約10%) |
年間の新規乳がん患者と新規卵巣がん患者全体における遺伝性腫瘍の割合は、乳がんが約3~5%、卵巣がんが約10%と1割程度です。
がんそのものが遺伝するわけではない
遺伝性腫瘍とはいっても、がんそのものが遺伝するわけではなく、正常ながん抑制遺伝子が変異した染色体が遺伝します。
したがって、がんの遺伝によりリスクが高くなるわけではなく、がん抑制遺伝子が変異しているかどうかで遺伝性腫瘍のリスクが変化するといえるでしょう。
なお、遺伝性腫瘍は同じ変異遺伝子の遺伝が認められても、異なるがんを発症する可能性があります。
そのため、発症したがんが異なっていても、遺伝子検査により染色体の変異が見られた場合は、遺伝性のがんの発症といえるでしょう。
がん(遺伝性腫瘍)が遺伝する仕組み
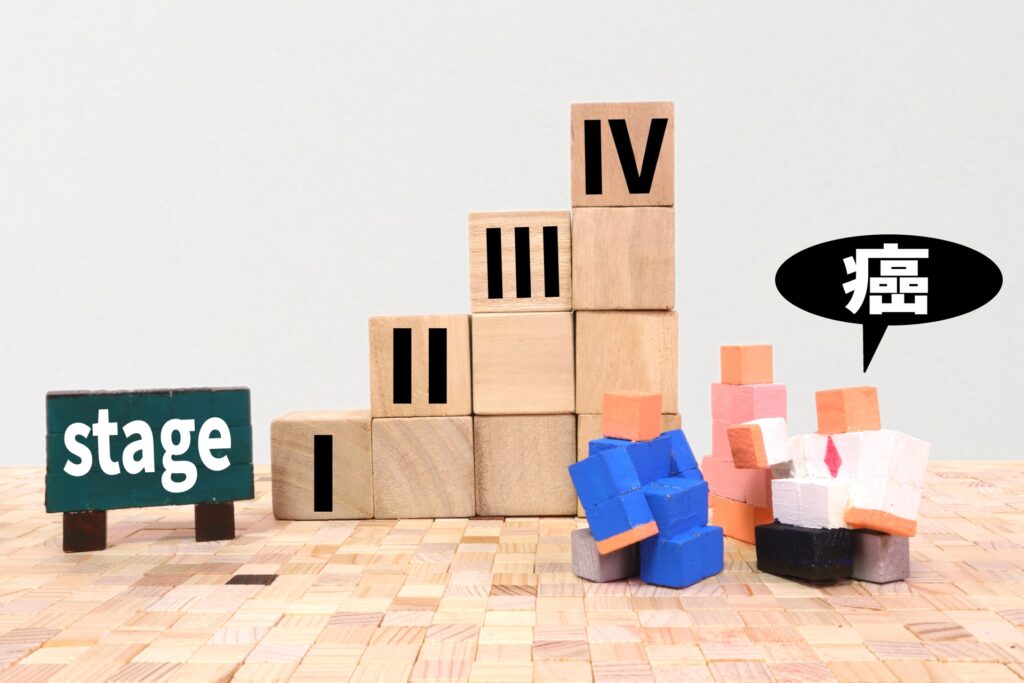
次に、がんが遺伝する仕組みを解説します。
人間の細胞は、遺伝性が生じない体細胞と遺伝性を生じる生殖細胞に分類されます。筋肉や骨などの体細胞は、生まれたあとに変異が起こっても遺伝しません。
一方で、遺伝性を生じる生殖細胞である精子や卵子に変異が認められた場合は、発生した変異ともども遺伝する可能性があります。
父親と母親のいずれか、または両方に生殖細胞の染色体に変異が認められている場合には、子どもに遺伝するリスクが高いといえるでしょう。
なお、父親と母親のいずれも染色体に異常がない場合は、当然子どもには遺伝しません。
しかし、正常な染色体を引き継いだ場合であっても、生まれたあとに引き継いだ染色体が変異する場合があります。
生まれたあとに変異した染色体を含む生殖細胞は、次の世代の子どもへと遺伝される可能性が出てくるでしょう。
遺伝しやすいがんの種類

遺伝しやすいがんには、次の9つのがんがあげられます。
遺伝子やすいがん
- 大腸がん(家族性大腸腺腫症)
- 大腸がん(リンチ症候群)
- 乳がん、卵巣がん
- 泌尿器がん
- 脳腫瘍
- 内分泌系腫瘍
- 眼のがん(網膜芽細胞腫)
- 皮膚がん(遺伝性黒色腫)
- 骨軟部肉腫(リー・フラウメニ症候群)
大腸がん(家族性大腸腺腫症)
大腸がん(家族性大腸腺腫症)は、大腸がんのなかでも比較的若い年齢で発症するがんです。
一般に10代のうちからポリープが出現し、多くの場合、20~60歳までに大腸がん(家族性大腸腺腫症)を発症するでしょう。
| 原因となる遺伝子 | APC |
|---|---|
| 遺伝率 | 約50% |
| 発症しやすいがん | 大腸腺腫、デスモイド腫瘍、胃・小腸ポリープ、軟部腫瘍 |
大腸がん(リンチ症候群)
大腸がん(リンチ症候群)は、すべての大腸がんの2~5%を占め、若年層で発症する遺伝性の大腸がんです。
主な特徴には、多臓器がんや大腸多発がんの同時発症があげられます。
リンチ症候群の遺伝子変異が遺伝すると、大腸がんの発症率は約80%となるでしょう。
| 原因となる遺伝子 | MLH1、MSH2、MSH6、PMS2 |
| 遺伝率 | 約50% |
| 発症しやすいがん | 子宮体がん、腎盂・尿管がん、卵巣がん、胃がん、小腸がん、膵臓がん、胆道がん、脳腫瘍 |
乳がん・卵巣がん
乳がんや卵巣がんは、血縁者のなかに数人の発症が認められている場合、遺伝性の可能性が高いとされるがんの一種です。
主な特徴に、40歳未満という若年での発症や乳がんと卵巣がん両方の発症が見られる場合があげられるでしょう。
| 原因となる遺伝子 | BRCA1、BRCA2 |
| 遺伝率 | 約50% |
| 発症しやすいがん | 乳がん、卵巣がん、前立腺がん、膵臓がん |
泌尿器がん
泌尿器がんは、前立腺や膀胱、腎細胞など泌尿器官に関するがんを総称したものをいいます。
| 原因となる遺伝子 | BRCA2、HOXB13、ATM |
| 遺伝率 | 約50% |
| その他に発症しやすいがん | 前立腺がん、膀胱がん、腎盂がん、尿管がん、腎細胞がん |
脳腫瘍
脳腫瘍は、頭蓋骨のなかの脳に関係する部位に発症するがんを総称したがんをいいます。
脳腫瘍の多くは、脳細胞の突発的な遺伝子の変異により発症します。
遺伝性の腫瘍は脳以外でも発症する可能性があるため、脳腫瘍を発症した場合には全身の検査が必要となるでしょう。
| 原因となる遺伝子 | NF1、NF2、SMARCB1 |
| 遺伝率 | 約50% |
| その他に発症しやすいがん | 神経鞘腫、神経膠腫、下垂体腺腫、聴神経腫瘍 |
内分泌系腫瘍
内分泌系腫瘍は、内分泌系細胞に関係する腫瘍をいいます。
主に、肺や消化管、膵臓などから発症する特徴があります。
| 原因となる遺伝子 | MEN1、RET |
| 遺伝率 | 約50% |
| その他に発症しやすいがん | 副甲状腺腫瘍、甲状腺髄様がん、下垂体腫瘍、褐色細胞腫 |
眼のがん(網膜芽細胞腫)
眼のがん(網膜芽細胞腫)は、網膜に生じる腫瘍をいいます。
乳幼児の発症例が多くの割合を占めており、瞳孔に光が反射し白く見える症状が網膜芽細胞腫の特徴です。
| 原因となる遺伝子 | RB1 |
| 遺伝率 | 約50% |
| 発症しやすいがん | 網膜芽細胞腫 |
皮膚がん(遺伝性黒色腫)
皮膚がん(遺伝性黒色腫)は、皮膚のメラニン細胞に生じた腫瘍をいいます。
主に黒色調の色素斑が特徴的で、一見するとほくろのようにも見え、顔や体幹、上肢から下肢に至るまで発症する部位はさまざまです。
| 原因となる遺伝子 | BRAF、NRAS、KIT |
| 遺伝率 | 約50% |
| その他に発症しやすいがん | 皮膚がん |
骨軟部肉腫(リー・フラウメニ症候群)
骨軟部肉腫(リー・フラウメニ症候群)は、常染色体優性遺伝に起因する遺伝症候群の一種です。
生まれたときから、遺伝により変異しやすいTP53を引き継いでいるため、さまざまながんを発症しやすい特徴があるでしょう。
| 原因となる遺伝子 | TP53 |
| 遺伝率 | 約50% |
| 発症しやすいがん | 骨肉腫、乳がん、脳腫瘍、副腎皮質腫瘍 |
がんが遺伝性か調べる方法

発症したがんの原因が遺伝性かどうか調べる方法を3つ紹介します。
- がん遺伝子パネル検査
- 血液検査
- 唾液検査キット
本項で紹介する検査は、それぞれ必要な検体や時間、費用が異なるでしょう。
なお、検査をおこなううえでは、いずれも正常な細胞の遺伝子とがん細胞の遺伝子を比較した検査が必要です。
がん遺伝子パネル検査
がん遺伝子パネル検査とは、がん細胞の遺伝子の変化を調べ、発症しているがんの特徴を明確にする検査です。
検査は、がんの組織や血液を使用しておこないます。
がん遺伝子パネル検査をおこなうには保険診療、自由診療、研究でおこなわれる検査のいずれかです。
なお、保険診療で検査を受ける対象となるがんは、次の2点です。
- 標準治療がない固形がん
- 局所的な進行、転移、標準治療が終了している固形がん
また、検査では治療につながる情報が得られない場合は、治療につながる可能性は低いといえるでしょう。
保険診療による検査費用の目安は、検査費用が132,000円程度、検査結果の説明費用が36,000円程度となります。
血液検査
血液検査は、採血した血液からDNAを抽出して、変異した遺伝子を調べます。一般の血液検査のようにさまざまな情報を一度に調べる検査ではありません。
したがって、自覚症状やがんの家族歴、発症しているがんなど情報を駆使して調べる遺伝子を絞り込む必要があります。
血液検査をおこなううえでは、ある程度の遺伝子の絞り込みが大切といえるでしょう。
一般的な血液検査とは異なるため、目安となる費用は60,000~70,000円程度です。
唾液検査キット
自宅でも簡単に遺伝子の変化を調べたい方に向けて、唾液検査キットと呼ばれる検査方法もあります。
唾液検査キットを活用すれば、唾液を専用の検査キットに入れて送るのみで、遺伝子検査が可能となるでしょう。
遺伝性腫瘍のみでなく、生活習慣から基礎代謝量まで幅広い情報を350項目以上にわたって把握できます。
検査にかかる費用の目安は、20,000~30,000円程度です。
遺伝性のがんを予防する方法

染色体の変異がある方は、遺伝性のがんを必ず発症するわけではありません。
しかし、生涯で何らかのがんを発症する可能性は高いと言えます。
そこで本項では、遺伝性のがんの発症リスクを予防する方法を3つ紹介します。
検診を怠らない
遺伝性のがんを予防するためには、まずはがんを早期発見できるように定期的にがん検診を受診しましょう。
すべてのがんは、早期発見と早期治療で予後が大きく変化します。
大腸がん、胃がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの5つは、各自治体で無料もしくは格安でがん検診がおこなえるようにクーポンも配布されています。
遺伝子に変異がある方は、がんを発症する可能性が高いため定期的な検診を活用し、健康を守っていきましょう。
がんになりやすい生活習慣をしない
がんになりやすい生活習慣を避ける心掛けも、がんを予防するためには大切です。
なお、がんになりやすい生活習慣の改善は、遺伝していない方でもがんの予防につながるでしょう。
とくに、がんになりやすい生活習慣のなかでも、次の5つには注意が必要です。
がんになりやすい生活習慣
- 喫煙
- 飲酒
- 肥満(BMI値)
- 身体活動量が少ない
- バランスの悪い食事
がんを予防するためにも、適度な運動やバランスの取れた食事などから生活習慣を整えましょう。
担当医や遺伝カウンセラーのアドバイスを受ける
がんの発症を疑っている方のなかには、インターネットや雑誌、友人からの情報で病気を判断する方もいます。
しかし、いずれの情報も信頼性に欠けており、生死を左右するがんの発症有無の判断に使用するべきではありません。
遺伝性腫瘍の発症に疑いを感じたときは、遺伝子やがんに関する専門の知識を持っている専門家から相談しましょう。
がん検診はマイクロCTC検査がおすすめ

がん検診は、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査とは、採血で血液内にある悪性度の高いがん細胞の有無を確認し、体内のがんの発症を調べる検査です。
マイクロCTC検査は、ほかの検査と併用すると、高い確率でがんの発生を特定できるでしょう。
5分の血液検査で全身のがんリスクがわかる
マイクロCTC検査は1回5分の採血で、がんの発症が調べられます。
がん検診でおこなうCT検査やMRI検査でも全身を調べられますが、初期のがんは見落とされる場合があります。
一方、マイクロCTC検査では、初期の悪性度の高いがん細胞を、直接的に捉えられるため、がんの発症の有無を簡易的かつ高確率で発見できるでしょう。
血液中のがん細胞を捉えるため、他の検査よりも確実性が高い
マイクロCTC検査は、血液中のがん細胞を捉えるため、ほかの検査よりもがんを発見する確率が高い検査方法です。
マイクロCTC検査は悪性度の高いがん細胞に反応します。
悪性度の高いがんは、がん細胞から血管に溢れだして全身に移動する性質があるため、悪性度の高いがんを対象とするマイクロCTC検査に高い確率で反応するでしょう。
マイクロCTC検査によって、血液中の悪性度の高いがんを早期に発見できたあとは、CT検査やMRI検査、レントゲン検査などでがんが発症している部位を特定していきます。
部位が特定できたところで、がんの早期治療をおこなえば、より根治性が高められます。
PETやCTなどに比べて費用が安価
マイクロCTC検査は、PET検査やCT検査に比べて検査費用が安い傾向にあり、1回あたりのマイクロCTC検査の費用は、198,000円(税込)です。
PETやCT主体のがん検査をおこなうと検査時間が約6時間かかるばかりか、検査費用として約250,000円以上を負担しなければいけません。
検査時間の短さから精度の高さ、経済面にいたるまで、いずれの視点から判断してもマイクロCTC検査がおすすめといえるでしょう。
関連記事
まとめ

がんの発症要因の多くが環境要因が原因であり、染色体の変異の遺伝による場合は1割程度と低いです。
なお、変異した遺伝子が遺伝した場合は、約50%の確率で遺伝性腫瘍を発症する可能性があります。
仮に遺伝性腫瘍を発症しない場合でも、変異した遺伝子を保持していると、がんの発症リスクは一般の方と比較して高いといえるでしょう。
また、家族内に特定のがんを多く発症している方や、若いうちにがんを発症した方がいる場合は、遺伝性腫瘍による可能性が考えられます。
自身にがんが発症しているか不安があるときは、安価で精度の高い検査を短時間で受けられるマイクロCTC検査がおすすめです。
定期的ながん検診や日々の生活習慣の改善により、がんの予防をはじめ、早期発見、治療につなげていきましょう。
<参考文献>
※1 大阪府がん診療連携協議会|がんゲノム医療部会ポータルサイトHP|遺伝性腫瘍関連情報
※2 厚生労働省健康局がん・疾病対策課|第1回がんに関する全ゲノム解析等の推進に関する部会|日本における 遺伝性腫瘍の遺伝学的検査の現状