近年では、がんに対するさまざまな治療法が誕生し、がん治療の新しい時代を迎えています。
免疫療法は、手術療法・放射線療法・化学療法に続く、第4の治療法です。現在、多くの医療機関が実施しており、研究開発も進められています。
しかし、がん免疫療法には保険診療・自由診療の両方が存在するため、有効性・安全性に加え、治療費を心配する方もいるでしょう。
本記事では、がん3大治療法の概要をはじめ、がん免疫療法の仕組みや保険適用の治療法、高額医療費制度・医療費控除について詳しく解説します。
自身や家族のがん治療の選択肢として免疫療法を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

がんにおける3大治療法

がんの治療法は3大治療法と呼ばれ、がんのステージや体の状態などに応じて、単独または組み合わせておこなわれます。
がんの3大治療法は下記のとおりです。
- 手術療法
- 放射線療法
- 化学療法
がんの3大治療法は科学的根拠に基づいた有効性が認められており、多くの場合、保険が適用されます。また、高額療養費制度の利用も可能です。
はじめに、それぞれの治療法を詳しく紹介します。
手術療法
手術療法は、がんやがんが発症した部位を可能な限り切除する治療法です。
体内にがん細胞が残らないよう、がん周囲の正常なリンパ節や臓器も同時に切除するケースが多く、正常な機能や外観が損なわれた場合には再建手術をおこないます。
手術療法は、早期のがんに対する最も有効な治療法です。がんを完全に切除できれば9割以上は根治ができ、再発のリスクを大幅に減少させることが可能です。
ある程度進行していても、切除が可能な状態であれば手術療法が選ばれます。
しかし、手術療法は身体的な負担が大きいため、日常生活や社会復帰に影響が出る可能性が高いです。
そのため、腹腔鏡下手術・内視鏡治療・ロボット支援下手術など、低侵襲な方法を採用する医療機関が増えています。
また、がんのある部分のみを切除する縮小手術により、機能を温存して術後のQOL維持につなげています。
放射線療法
放射線療法とは、手術療法と同じく局所的な治療法です。
がんのある部分にX線を照射してがん細胞の破壊、増殖を抑制して、完治または症状の緩和を目指します。
一部、放射線物質を体内に挿入する方法や、飲み薬・静脈注射などで投与する場合があります。
また、再発防止のためにほかの治療法と併用するケースも少なくありません。
放射線療法は、ステージ0~4までの幅広い病期に適応できますが、大量の放射線被ばくにより正常な細胞がダメージを受けて次のような副作用が生じます。
- 倦怠感
- 食欲不振
- 貧血
- 皮膚障害
放射線療法中や治療直後には、倦怠感・食欲不振・貧血を代表とする全身の副作用が現れ、照射した部位により、脱毛や皮膚障害などの局所的な症状が現れるケースが多いです。
そのほか、治療終了後の数か月~数年後の晩期には、2次がんが発生するリスクが高くなります。
化学療法
薬物療法は、注射・点滴・内服などで薬剤を全身に行き渡らせてがん細胞を破壊する治療法です。
がんの根治をはじめ、進行抑制や症状の緩和、転移・再発の防止など、さまざまな目的でおこなわれます。
薬物療法で使用する主な薬剤は、下記のとおりです。
- 細胞障害性抗がん薬
- 分子標的療法
- 内分泌療法
細胞障害性抗がん薬とは、がん細胞が分裂、増殖するプロセスを妨げる薬剤です。
異なる作用をもつ複数の抗がん剤を組み合わせることで、より広範囲のがん細胞にアプローチができますが、吐き気・嘔吐や脱毛などの副作用が生じやすいデメリットがあります。
分子標的療法は、がん細胞の増殖に関わる特有のタンパク質・血管・DNAに作用して増殖を阻害します。
抗がん剤に比べて副作用が少ない点がメリットですが、治療中に薬剤耐性が生じるケースが少なくありません。
内分泌療法は、ホルモンの分泌や働きを妨げてがん細胞の増殖を抑える手法です。乳がんや前立腺がんなど、特定のがんにのみ効果が期待できます。
新しいがん治療「免疫療法」とは?
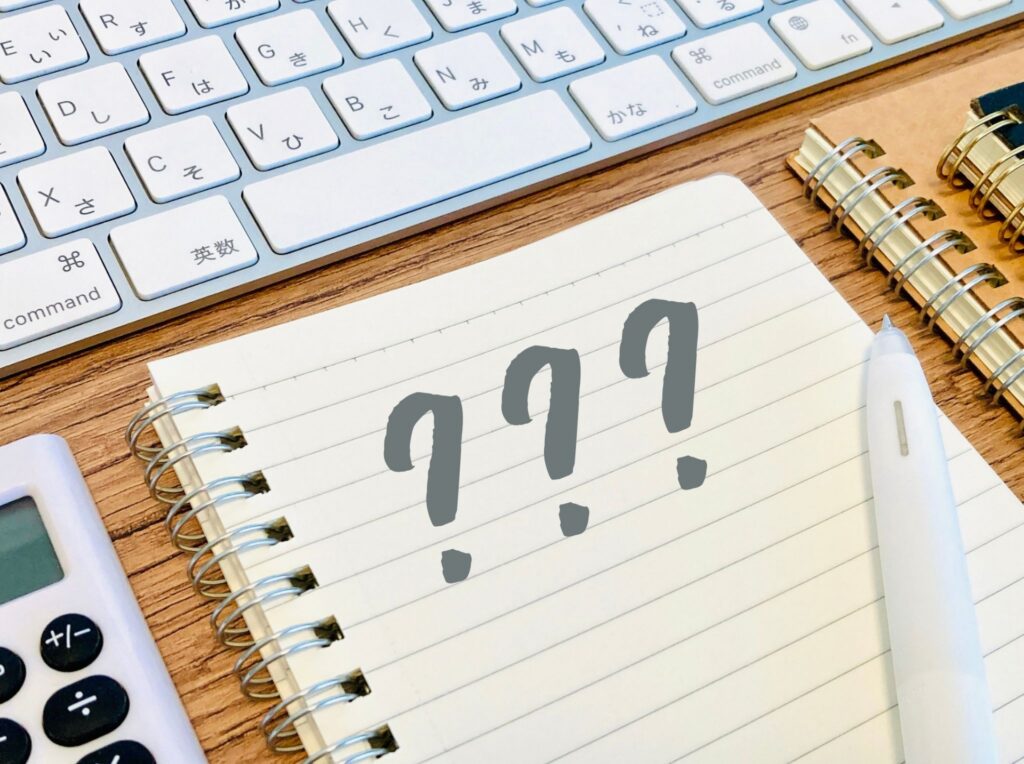
免疫療法とは、本来、体内に備わっている免疫の力を利用し、がん細胞を攻撃して増殖・進行を抑制する治療法です。
従来のがん3大治療法に次ぐ新たな治療法として、多くの医療機関が導入しており、現在でも研究開発が進んでいます。
次章では、がん免疫療法の概要・種類などを詳しく解説します。
免疫の働きでがんを攻撃
免疫とは、細菌・ウイルスなどの有害な物質を攻撃したり、変異した細胞を排除したり、健康維持に欠かせない体の仕組みです。
免疫には、生まれつきもっている自然免疫と病原体や異物と接触して抗体を産生する獲得免疫の2つの種類があり、互いに作用して体を病気から守ります。
免疫機能を担う免疫細胞は多種多彩で、チームを組んでがん細胞と戦うことがわかっています。
がん細胞と戦う免疫細胞の種類・役割は、下記のとおりです。
| 種類 | 役割 |
|---|---|
| T細胞(キラーT細胞・ヘルパーT細胞) | がん細胞を攻撃する |
| マクロファージ | がん細胞を貪食して消滅させる |
| NK細胞(ナチュラルキラー細胞) | 体内をパトロールして、がん細胞を見つけ次第攻撃する |
| 樹状細胞 | がん細胞の目印を認識し、ほかの免疫細胞に情報を伝える |
免疫細胞の力を高めてがん細胞の増殖・進行を抑制する治療法を、がん免疫療法といいます。
免疫療法の種類
主な免疫療法は、下記のとおりです。
- 免疫チェックポイント阻害薬
- サイトカイン療法
- CAR-T細胞療法
免疫チェックポイント阻害薬は、免疫細胞がもつ自己を攻撃しないための抑制機能を解除する薬剤です。
がん細胞は、免疫細胞のブレーキを利用して攻撃から逃れる性質をもっています。薬剤を用いてブレーキを解除すれば、がん細胞への攻撃力を回復させることが可能です。
サイトカイン療法では、免疫細胞が産生するタンパク質(サイトカイン)を活性化させる薬剤を投与し、がん細胞への攻撃力を高める手法です。
CAR-T細胞療法とは、血中のT細胞を取り出して遺伝子の改変をおこない、体内に戻す手法です。がん細胞を死滅させて再発を防ぐ効果が期待できます。
がん免疫療法の費用は保険適用される?

がんの免疫療法には、公的な保険が適用されるものと、自由診療で受けるものがあります。
次章では、それぞれの免疫療法について詳しく解説します。免疫療法の選択に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
効果が証明された免疫療法のみ対象
免疫療法は、国が有効性・安全性を認めた治療法・薬剤に限り保険が適用されます。下記は、保険適用が可能な薬剤と対象のがん種です。
| 免疫療法 | 薬剤 | 対象のがん種 |
|---|---|---|
| 免疫チェックポイント阻害薬 | ニボルマブ | 非小細胞肺がん、腎細胞がん、頭頸部がん、胃がん |
| ペムブロリズマブ | 非小細胞肺がん、ホジキンリンパ腫、尿路上皮がん | |
| イピリムマブ | 皮膚がん | |
| デュルバルマブ | 肺がん、肝細胞がん、胆道がん | |
| アテゾリズマブ | 肺がん、肝細胞がん、非小細胞肺がん、尿路上皮がん | |
| アベルマブ | 尿路上皮がん | |
| サイトカイン療法 | インターフェロン(IFN) | 腎細胞がん、血液がん、脳がん、皮膚がん |
| インターロイキン2(IL-2) | 腎臓がん | |
| CAR-T細胞療法 | キムリア、イエスカルタ、ブレヤンジ | 血液がん(悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫) |
従来の治療法と併用する場合や、複数の免疫療法を組み合わせる際にも保険が適用されます。また、通院費・入院費にも保険が適用されるケースが多いです。
自由診療を受ける際は注意が必要
近年では、さまざまなクリニックが自由診療での免疫療法を提供しています。
しかし、保険適用外の自由診療は、公的制度に基づく臨床試験や治験などで作用を実証していないため、医療として確立されていません。
効果や安全性は保証されず、費用も非常に高額です。
自由診療の免疫療法を受けようと考えている方は、担当医やがん相談支援センターなどに相談しながら慎重に検討しましょう。
がん免疫療法は高額医療費制度・医療費控除の対象になる?
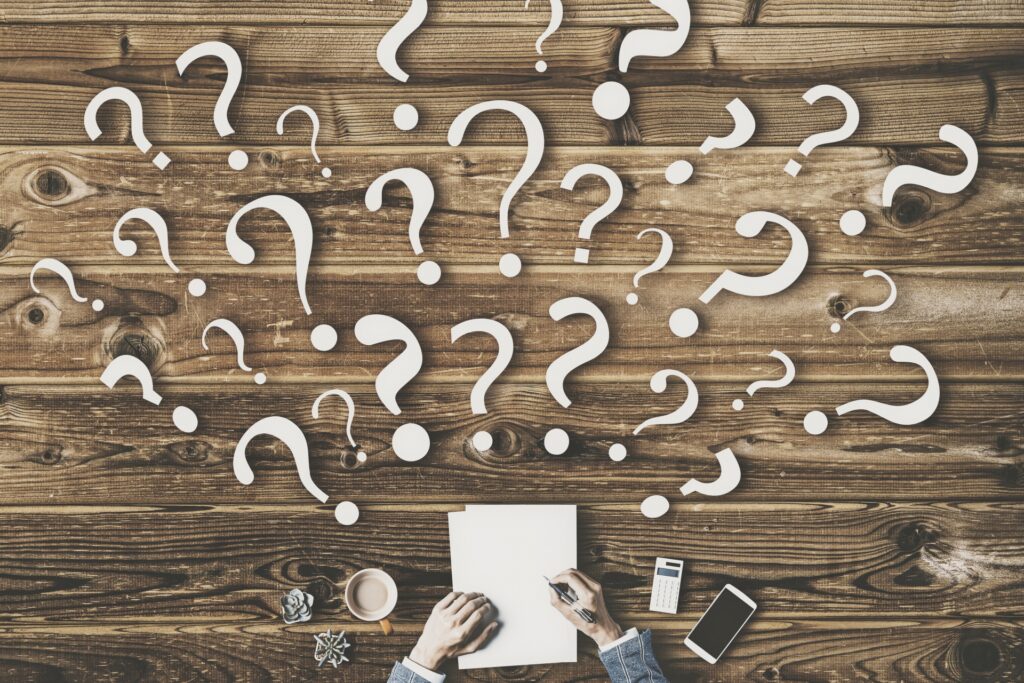
がん免疫療法は、一部で高額医療制度が利用でき、また、大半は医療費控除の対象となります。
高額医療費制度とは、医療機関や薬局で支払う医療費が1か月で上限額を超えたとき、超えた金額が公的医療保険から支給される制度です。
1年に3回以上、自己負担額が上限額に達した場合、4回目から多数該当となり上限額がさらに引き下がります。
一方、医療費控除は所得控除の一つです。1年間の基準額を超えた自身や家族の医療費を税務署に申告すると、課税対象の所得から控除されて税金の一部が還付されます。
ともに、高額な医療費を支払った際の経済的な負担の軽減につながり、治療内容によっては2つの制度の併用が可能です。
次章では、がん免疫療法は高額医療費制度・医療費控除の対象になるのかを詳しく解説します。
高額療養費は保険診療分のみ
高額療養費の対象は、保険診療分の自己負担額のみです。
保険診療のがん免疫療法を受けた場合、診察費・検査費、入院・手術などの治療費、薬剤費は高額療養費として計上できます。
しかし、保険診療でも入院時の食費・差額ベッド代は対象外です。
また、公的医療保険が適用されない自由診療や先進医療、未承認薬を用いた臨床試験に対しても、高額療養費制度は利用できません。
一般的に、高額療養費は事後に手続きをしますが、一時的に医療費の立て替えが難しい場合、事前に限度額適用認定証を申請すれば、自己負担限度額のみの支払いで済みます。
医療費控除の対象になる
がん免疫療法は、医師から診断を受けて治療が必要と判断された状態であれば、保険診療・自由診療にかかわらず、医療費控除の対象になります。
一方、任意の健康診断や人間ドックの費用、ビタミン剤・体力増強剤などの治療に関連しない医薬品の購入費は対象外です。
医療費控除を受ける際は、治療費をはじめ、通院費・往診費、入院時の費用などの自己負担額の明細書・通知書を確定申告書に添付して税務署に提出します。
申請から1~2か月程度で、指定口座に還付金が振り込まれます。
セカンドオピニオンにマイクロCTC検査がおすすめ

マイクロCTC検査は、血中を循環するがん細胞をキャッチして全身のがんリスクを判定する血液検査です。
従来の検査より非常に早い段階で、転移・浸潤する能力をもつ悪性度の高いがん細胞のみを特異度94.45%で検出します。※1
そのため、がんの超早期発見を目指す方はもちろん、がん検診で異常を指摘された方や医師からがんの再発を示唆された方などのセカンドオピニオンにも有効です。
また、がん細胞の個数が把握できることから、治療効果の確認にも役立ちます。
ここからは、マイクロCTC検査の概要を紹介します。
全身のがん細胞を高精度で補足
マイクロCTC検査では、米国の「MDアンダーソンがんセンター」が開発したCSV抗体を用い、血中のがん細胞を特異度94.45%の高精度で捉えることが可能です。※2
従来の検査では発見が難しい小さいがんや、画像に写りにくい部位のがんの発見にもつながります。
また、正確な結果を出すために迅速な検査体制を整えていることも、マイクロCTC検査の特徴の一つです。
採血後すぐに分析・解析ができるよう、国内に自社検査センターを設けており、AIと専門の検査技師によるダブルチェックをおこないます。
悪性度の高いがん細胞を1個単位で検出するため、非常に満足度が高いがんリスク検査といえるでしょう。
アフターフォロー制度が充実
マイクロCTC検査には、医師による無料相談が受けられるアフターフォロー制度があります。
がん細胞が検出された場合、マイクロCTC検査センター長および代々木ウィルクリニックの太田医師に無料で相談できます。
無料相談の概要は、次のとおりです。
- 相談方法:電話(遠方の方はオンライン面談に対応)
- 受付時間:9~12時・13~18時の間で最大30分
- 主な内容:検査結果の説明、受診すべき検査・専門医・医療機関などの紹介
相談後、画像診断や内視鏡検査を受けてもがんが発見されなかった場合、再度、無料相談が可能です。
万が一のとき一人で悩まず医師に相談できるため、検査結果に対する不安は軽減するでしょう。
検査の流れ・費用
ここで、マイクロCTC検査の流れと費用を紹介します。
- クリニック予約
- 個人情報・問診票の入力
- 検査(採血)
- 検査結果の確認
マイクロCTC検査は、全国の提携クリニックで導入しています。まずは、公式サイトで受診したいクリニックを選び、採血・検査予約をタップして希望の日時を選択しましょう。
次いで、ログインまたは新規会員登録をおこない、個人情報と問診票を入力して予約を確定させます。
当日は、予約時間の10分前までには来院しましょう。検査は1回5分の採血のみで終了し、事前の食事制限や薬剤の投与は一切ありません。
検査結果はWebで閲覧が可能です。検査後、1週間程度で登録しているメールアドレスに通知が届きます。マイページにログインして結果を確認しましょう。
マイクロCTC検査の料金は、1回198,000円(税込)です。※3
がん免疫療法の費用や保険適用に関するよくある質問
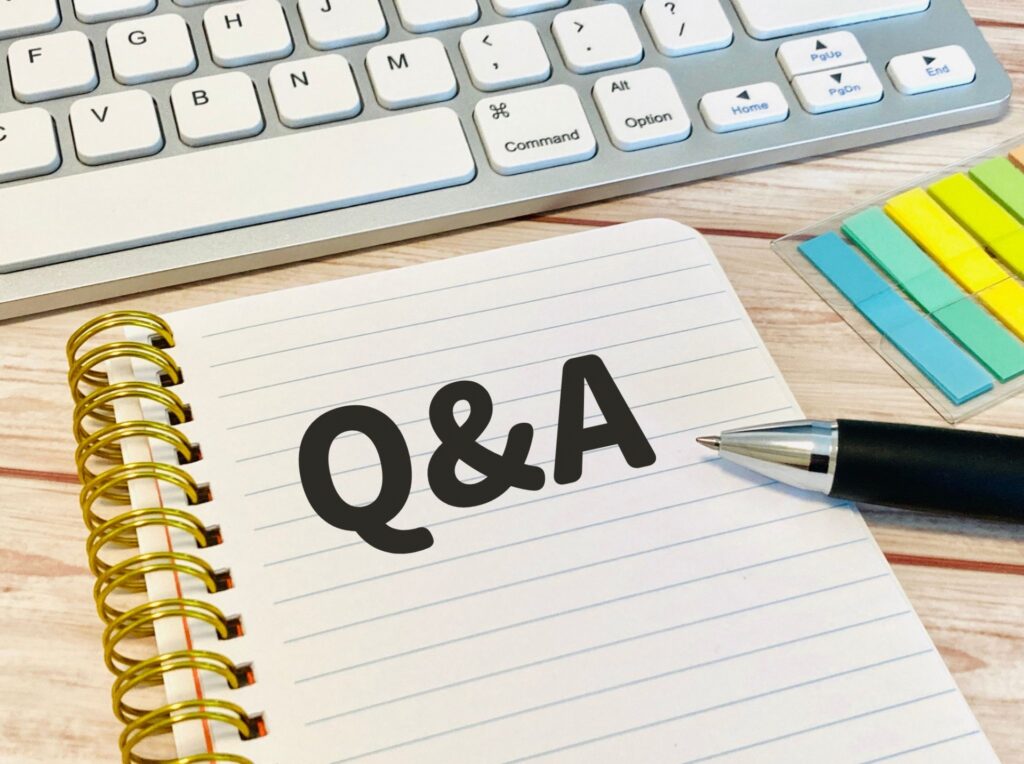
最後に、がん免疫療法の費用や保険適用に関するよくある質問を紹介します。
同じ疑問を抱いている方は、ぜひ参考にしてください。
がん保険の給付対象になる?
がん保険には、公的医療保険制度の対象となる治療・入院・通院・手術などの際に支払われる給付金があります。
がん免疫療法に関しても、保険診療に限り給付金が受け取れるケースが多いです。
一方、先進医療を自己負担で受けた場合や、厚生労働大臣の承認済みの医療機関においての自由診療にも、給付金が支払われる特約を付加したプランもあります。
がん免疫療法を受ける前に、自身が加入しているがん保険を確認しましょう。
光免疫療法とは?
光免疫療法とは、薬剤とレーザー光を組み合わせて、がん細胞をピンポイントで破壊する治療法です。
まず、がん細胞に特定の光に反応する光感作物質を点滴で投与します。投与してから20~28時間後、近赤外線レーザーを照射してがん細胞の細胞膜を破壊します。
照射後1週間は、皮膚・眼に強い光や直射日光が当たらないよう注意が必要です。できる限り外出を避けて室内で過ごしましょう。
治療効果が不十分な場合、4週間以上の間隔を空ければ最大4回まで受けることが可能です。
光免疫療法は、切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がんに対して保険診療で受けられ、また、早期がんのみならず、末期がん・難治性がんの治療にも対応できます。
免疫療法に副作用はある?
がん免疫療法は、がん細胞のみに作用する治療法であるため、比較的副作用が少ないといわれています。
しかし、免疫が働き過ぎることで「免疫関連有害事象(irAE)」と呼ばれる副作用が生じる可能性があります。
免疫関連有害事象(irAE)の主な症状は、下記のとおりです。
- 呼吸器症状(間質性肺炎・咳・息切れなど)
- 消化器症状(大腸炎・腹痛・下痢・血便など)
- 皮膚症状(皮膚のただれ・発疹・湿疹など)
- 神経症状(手足のしびれや痛み・筋力低下・感覚麻痺など)
- 心症状(胸痛・動悸・呼吸困難など)
- 脳症状(頭痛・発熱・嘔吐など)
また、糖尿病や甲状腺機能低下症などが引き起こされるケースもあります。
まとめ

本記事では、がん免疫療法の種類や費用を中心に解説しました。
がん免疫療法には、有効性・安全性が認められた保険適用の治療法と、科学的根拠が不十分な自由診療のものがあります。
保険適用の免疫療法は、高額医療費制度や医療費控除、がん保険などの保障が利用できるため、経済的な負担の軽減につながります。
一方、自由診療の場合、費用は完全自己負担です。非常に高額なケースが多く、また、効果が得られる保証もありません。
がん免疫療法を受ける際は、慎重に検討しましょう。
がんの診断を受けた方や、再発の可能性を指摘された方のセカンドオピニオンには、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は、血中に漏れ出したがん細胞を直接捉える高精度・高品質な血液検査です。
定期的にマイクロCTC検査を活用し、症状が現れない早期のうちからがんを発見して治療につなげましょう。
〈参考サイト〉
※1、※2、※3:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査
