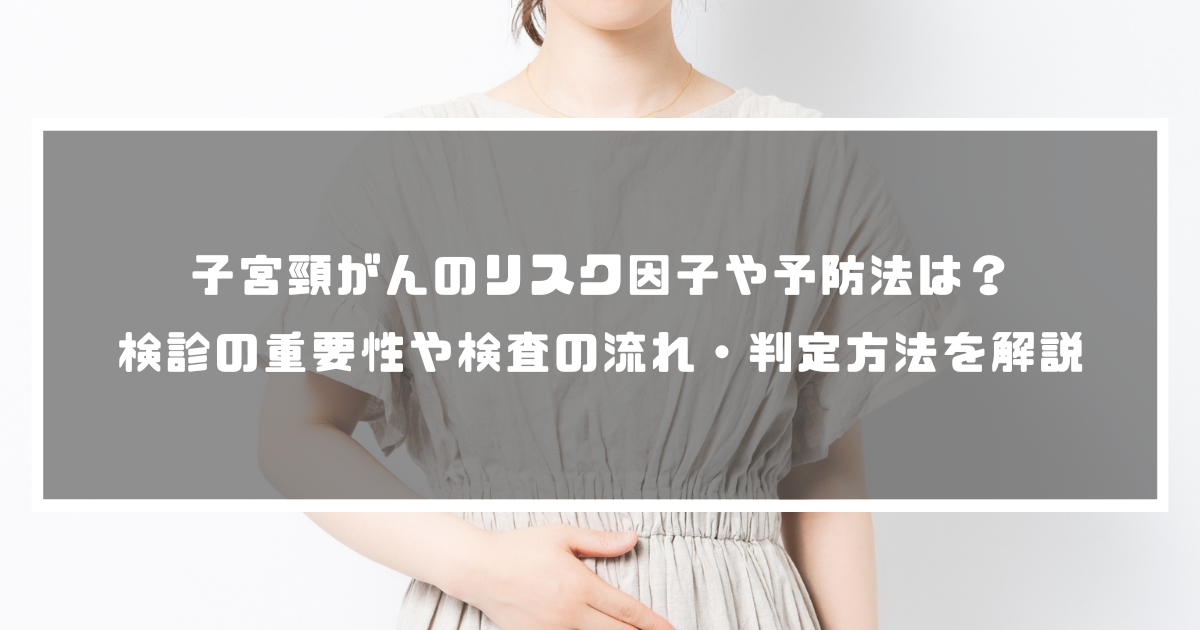「子宮頸がんにならないためにはどうしたらよいのか」
「子宮頸がん検診ではどのような検査をするのか」
上記のような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
子宮頸がんを予防するためには、子宮頸がんの知識を深め、検診に関する情報を知ることが大切です。
本記事では、子宮頸がんのリスク因子や予防法について解説します。
検診の重要性や検査の流れ、判定方法についてもあわせて解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

子宮頸がんとはどのような病気?
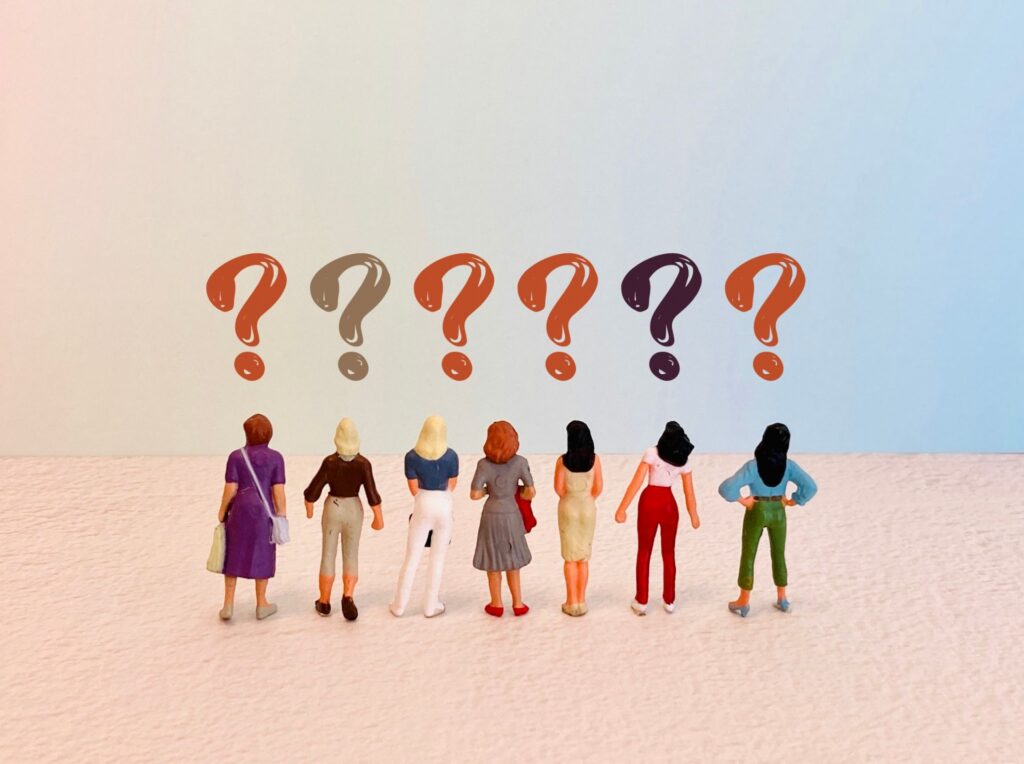
子宮頸がんとは、子宮の入り口である子宮頸部に発生するがんです。
日本では、毎年約1万人の方が子宮頸がんと診断されており、約3,000人が死亡しています。※1
また、比較的若い世代でも発症するリスクがあり、近年は患者数も死亡者数も増加傾向です。
はじめに、子宮頸がんの概要・症状・原因を詳しく紹介します。
子宮頸部にできる悪性腫瘍
子宮は、骨盤のなかにある、洋ナシを逆さまにした形状の臓器で、大きく分けて子宮体部と子宮頸部に分類されます。
子宮頸がんは子宮の入り口(子宮頸部)に、子宮体がんは子宮の奥の部分(子宮体部)にできる悪性腫瘍です。
子宮頸がんの罹患数は、20代後半から増えはじめ、30代後半にピークを迎えます。また、40代・50代で発症する方も少なくありません。※2
子宮頸がんは、早期に発見すれば治癒が可能です。
また、子宮を温存できるため、妊娠・出産の可能性も残せます。
しかし、子宮頸がんが進行すると、子宮そのものを摘出する必要があり、さらに他の臓器に浸潤・転移している場合は、生存率が著しく低下します。※4
主な症状
子宮頸がんは、初期段階では大半が無症状です。
がんが進行すると、下記の症状が現れることがあります。
- 不正出血
- おりものの異常
- 骨盤・下腹部・腰の痛み
- 血便・血尿
- 下肢のむくみ
不正出血は、月経以外の出血や性交時の出血を指します。子宮や卵巣などの腫瘍により引き起こされるケースが多く、子宮頸がんにもみられる症状です。
また、においを伴う茶色のおりものをはじめ、水っぽいおりもの、粘り気のあるおりものなど、いつもと異なるときは早めに婦人科を受診しましょう。
そのほか、がんがリンパ節や直腸、膀胱などに広がると、骨盤・下腹部・腰の痛み、血便・血尿、下肢のむくみが現れる場合があります。
原因はヒトパピローマウイルス(HPV)
子宮頸がんの主な原因は、性行為によるヒトパピローマウイルス(HPV)への感染です。
HPVはごくありふれたウイルスであり、性交経験のある女性の過半数において、一度は感染する機会があるといわれています。※5
HPVには、感染しても健康の被害を及ぼさないタイプと、子宮頸がんを引き起こすハイリスク型のタイプがあります。
しかし、ハイリスク型のHPVに感染しても、90%以上は体内から自然に排除されるため、すべての方が子宮頸がんを発症するわけではありません。※6
HPVに感染しても、多くの場合は身体の免疫機能により自然に排除されます。
一部の方は排除されずに感染が持続し、5~10年以上と長い時間をかけて子宮頸がんを発症するといわれています。※7
関連記事
子宮頸がんのリスクを下げる方法

ここで、子宮頸がんのリスクを下げる方法を紹介します。
- ワクチン接種
- 検診の受診
子宮頸がんワクチンは、子宮頸がんを引き起こすハイリスク型(16型・18型)HPVの予防に有効です。
また、定期的な検診で、がんになる前段階の病変が見つかると、早期に治療を開始でき、子宮頸がんの発症を未然に防ぐことにつながります。
次章で詳しく解説します。
ワクチン接種で予防する
子宮頸がんのリスクを下げる方法の一つは、HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)の接種による、ヒトパピローマウイルス(HPV)への感染予防です。
HPVワクチンは、性交渉を経験する前に摂取すれば子宮頸がんの予防効果が見込めます。
そのため、厚生労働省は小学校6年生から高校1年生の女子を対象に、公費での定期摂取を実施しています。
現在、日本国内で受けられるワクチンは次の3種類です。
- 2価ワクチン(サーバリックス)
- 4価ワクチン(ガーダシル)
- 9価ワクチン(シルガード9)
2価ワクチンと4価ワクチンでは子宮頸がんの原因を60~70%予防でき、9価ワクチンの接種では80~90%予防できるとされています。※8
検診を受ける
子宮頸がんは初期段階では無症状のことが多く、がんが進行するまで気づかないケースが少なくありません。
検診を受けることにより、がんが進行する前段階で発見できれば、早期治療や予防につながります。
子宮頸がんは、前がん病変といわれる子宮頸部異形成を経て発症します。
子宮頸部異形成には、軽度異形成(CIN1)、中等度異形成(CIN2)、高度異形成・上皮内がん(CIN3)の3種類があり、いずれも子宮頸がん検診で見つけることが可能です。
万が一、子宮頸がんを発症したとしても、早期のうちであれば身体的・経済的の負担が少ない治療法を選択できます。
子宮頸がんの早期発見・早期治療のためには、定期的に検診を受けることが重要です。
関連記事
子宮頸がん検診の流れ・判定方法

子宮頸がん検診の流れは、次のとおりです。
- 問診
- 視診・細胞診
- 内診
はじめに、診察をおこなうために重要な問診表を記入します。
問診表の項目は、最近の月経、妊娠・出産経験の有無、気になる症状、検診の受診状況、既存歴などです。
視診では、クスコ(腟鏡)と呼ばれる器具を腟に入れ、子宮頸部の状態を観察し、内診では、医師が腟側と腹部側を手で挟むような形で、子宮や卵巣の大きさを確認します。
そして、細胞診に必要な子宮頸部の細胞を専用のヘラやブラシなどでこすり取ります。所要時間は1分程度です。※9
細胞診の結果に応じてクラス1~5に分類され、クラス3a以上の場合は「要精密検査」の判定を受けます。※10
対象年齢・検診間隔
子宮頸がん検診の対象年齢は20歳以上で、2年に1回の定期的な受診が推奨されています。※11
子宮頸がんの進行スピードは基本的に非常にゆるやかであり、がんの前段階から進行がんになるまでにかかる期間は2~3年ほどです。※12
そのため、毎年受けても隔年で受けても発見率は変わらないとされています。
判定後の流れ
子宮頸がん検診で「精密検査不要」の結果が出た場合、がんの疑いはありません。
しかし、将来的なリスクを防ぐためにも定期的ながん検診の受診が大切です。
検査の結果、要精密検査の判定が出た場合は、子宮頸部の組織を採取して詳しく調べる組織診検査や、HPVの感染を確認する検査を受ける必要があります。
精密検査の結果、子宮頸がん(進行がん)であると診断された場合は、CT検査やMRI検査などの画像検査をおこない、がんの広がりや転移の有無などを確認します。
全身のがんリスクを調べるならマイクロCTC検査

マイクロCTC検査とは、浸潤や転移の恐れがある悪性度の高いがん細胞を感度高く発見できる検査です。
通常、全身のがん検診をする場合は、検査に半日~1日の時間を要しますが、マイクロCTC検査では1回5分の採血のみで、簡単に検査が可能です。
また、従来のがん検査で全身のがんを調べる場合は、20~30万円ほどの費用がかかるのに対し、マイクロCTC検査は198,000円(税込)と比較的安価に受けられます。※13※14
1回5分の血液検査のみでリスク判定
マイクロCTC検査は、1回5分程度の採血のみで終わる、非常に簡便な検査です。
そのため、仕事や子育てでなかなか時間がとれない方や、胃カメラやバリウムなどによる身体的な苦痛を避けたい方におすすめです。
また、検査前の食事制限や薬剤の服用は不要で、医療被ばくのリスクもありません。
悪性度の高いがん細胞を捕捉できる
CTC(Circulating Tumor Cells)とは「血液中を流れるがん細胞」のことをいいます。
通常のCTC検査とマイクロCTC検査の大きな違いは、がん細胞を捉える範囲です。
CTC検査は「上皮性がん細胞」を、マイクロCTC検査は「間葉系がん細胞」を捕捉します。
「上皮性がん細胞」は、がんが皮膚の表面である上皮内に留まっている状態で、治療の必要性がないものや、再発の可能性がないものが多くあり、悪性度は低いです。
一方、「間葉系がん細胞」は、浸潤・転移する能力を持っているため、悪性度が高いと評価されています。
マイクロCTC検査は、悪性度が高い「間葉系がん細胞」のみをキャッチし、早期治療につなげる画期的な検査です。
子宮頸がんのリスクに関するよくある質問
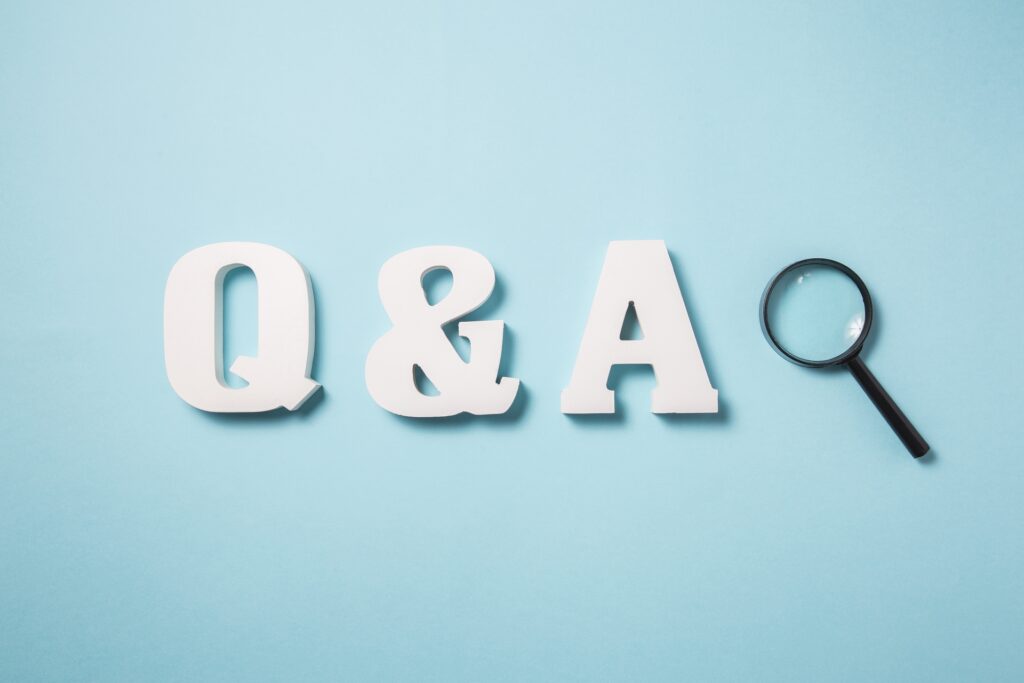
ここでは、子宮頸がんのリスクに関するよくある質問について回答します。
- 性行為が多いと子宮頸がんになりやすいのか
- 低用量ピルの使用で子宮頸がんリスクは高まるのか
- 子宮頸がんの治療法には何があるのか
子宮頸がんのリスクについて詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
性行為が多いとなりやすい?
子宮頸がんの主な発症要因であるヒトパピローマウイルス(HPV)は、性行為によって感染するため、性行為の経験が多いと、子宮頸がんの発症リスクが高まります。
しかし、性行為の経験が少ない方が子宮頸がんにかかりにくいわけでもありません。
性交渉の頻度よりも、子宮頸がんを引き起こしやすい種類のHPVに感染しているかが重要です。
一度でも性交渉の経験があれば、誰にでもHPV感染の可能性があることを理解しておきましょう。
低用量ピルの使用でリスクが高まる?
低用量ピルを服用している方では、子宮体がんや卵巣がんの発症リスクは低下するものの、子宮頸がんのリスクが高まるとされています。
そのため、低用量ピルを服用している方はとくに、子宮頸がん検診を定期的に受けるべきといえるでしょう。
子宮頸がんの治療法は?
子宮頸がんの治療方法には、主に手術療法や放射線療法、抗がん剤治療があり、がんの進行期(ステージ)や合併症の有無などを考慮して決められます。
がんの前段階の病変やがんの初期段階であれば、経過観察や異常な細胞を取り除く手術などが選択されます。
がんの広がりがみられる場合は手術が難しいケースもあるため、主に放射線療法や抗がん剤治療が選択されるでしょう。
まとめ

子宮頸がんは、初期の自覚症状がほぼないため、発見されたときにはすでに進行がんになっているケースも少なくありません。
子宮頸がんの発症リスクを下げるためには、ワクチン接種や定期的な子宮頸がん検診の受診が大切です。
子宮頸がんをはじめとする全身のがんリスクを簡単に調べたい方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
1回5分の採血のみで検査が受けられるため、検診を受ける時間がないときは、マイクロCTC検査を活用しましょう。
関連記事
〈参考サイト〉
※1、※2:国立がん研究センター がん統計|子宮頸部
※3、※5:公益社団法人 日本産科婦人科学会|子宮頸がん
※4:全がん協加盟施設の生存率協同調査|全がん協生存率
※6:子宮頸がん情報サイト|HPVとは
※8:厚生労働省|ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~
※9:【中外製薬】おしえて 子宮頸がんのコト|当日の流れは?
※10:子宮頸がん講座|検診の内容 | 検診に行こう!
※11:国立がん研究センター がん情報サービス|子宮頸がん検診について
※12:知っておきたいがん検診|子宮頸がん検診Q&A
※13:国立がん研究センター 中央病院|検診費用
※14:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査