子宮頸がんは、結婚・妊娠・出産などのライフイベントが豊富な20~40歳代の女性に多く発症します。※1
そのため、国は20歳以上の女性に対し、2年に1回の子宮頸がん検診の受診を推奨しています。
しかし、妊娠中や妊娠の可能性がある場合、子宮頸がん検診を受けるべきか迷う方もいるでしょう。
本記事では、子宮頸がんの概要をはじめ、妊娠中に子宮頸がん検診をおこなう理由、検査の種類・治療法などを詳しく解説します。
自身とお腹の赤ちゃんの健康を守るためにも、子宮頸がんに関する知識を深めましょう。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

子宮頸がんとは?

子宮頸がんとは、子宮の入り口に位置し、腟につながる部分である子宮頸部のがんです。
主な原因は、ヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染であり、大半は前がん病変と呼ばれるCIN(子宮頸部上皮内腫瘍)やAIS(上皮内腺がん)を経て発症します。
30歳後半~40歳代の女性に多く、20歳代の若年層でも罹患するリスクがあります。※2
初期の子宮頸がんは、自覚症状がほぼありません。進行すると、下記のような症状が現れます。
- 不正出血
- おりものの異変
- 血尿・血便
最も多い症状は、月経中の期間外や性交時の出血です。また、おりものが茶色い、水っぽい、膿のようなものが増えたなどの変化も現れやすいといわれています。
がんが膀胱・直腸に浸潤すると、下腹部の痛み・血尿・血便などが生じます。
妊娠中に子宮頸がん検診をおこなう理由

ここで、妊娠中に子宮頸がん検診をおこなう理由を紹介します。
- 子宮頸がんの発症年齢と出産年齢が重なる
- 母子保健法に定められている
日本人の出産平均年齢である30.9歳は、子宮頸がんの罹患数が急増する年齢と重なります。また、近年では発症ピークに該当する45歳以上で出産する方も増加しています。※3※4
発症リスクが高い年代であるからこそ、妊娠中の子宮頸がん検診が大切です。
自治体は、母子保健法により妊婦健康検査の実施が義務付けられています。妊婦と胎児の健康状態を定期的に確認するための検査項目として、子宮頸がん検診が含まれています。
妊娠中期以降は出血の恐れや、精密検査が受けられないケースも多いことから、子宮頸がん検診は妊娠初期が望ましいです。
実際に、子宮頸がんの約3%は妊娠中に見つかっており、約1.4%の頻度で細胞診異常が確認されています。※5
妊娠中におこなう子宮頸がん検診の種類

妊娠中の子宮頸がん検診の種類は、下記のとおりです。
- 細胞診
- コルポスコープ組織診
- ハイリスクHPV検査
次章では、それぞれの検査を詳しく紹介します。
細胞診
細胞診とは、子宮頸部の細胞をヘラやブラシなどでこすり取り、顕微鏡で異変の有無を調べる検査です。
がんはもちろん、前がん病変の発見にも有用であるため、子宮頸がんの一次検診としておこなわれています。
細胞診の検査結果は、ベセスダシステムに基づいて下記に分類されます。
| 分類 | 判定 | 精密検査 |
|---|---|---|
| NILM | 正常 | 不要 |
| ASC-US | 細胞の変化がみられ、軽度異形成の可能性がある | 必要 |
| ASC-H | 高度な細胞異型の可能性がある | 必要 |
| LSIL | HPV感染や軽度異形成がみられる | 必要 |
| HSIL | 中等度異形成・高度異形成・上皮内がんと考えられる | 必要 |
| SCC | 扁平上皮がんが疑われる | 必要 |
| AGC | 異型腺細胞が疑われる | 必要 |
| AIS | 上皮内腺がんの疑い | 必要 |
| Adenocarcinoma | 腺がんの疑い | 必要 |
| Other | 子宮頸がん以外のがんの疑い | 必要 |
細胞診にて異常なし、すなわち「精密検査不要」と通知されるものはNILMのみです。「要精密検査」の結果が届いた方は、できる限り早く精密検査を受診しましょう。
コルポスコープ組織診
コルポスコープ組織診は、細胞診で「要精密検査」と判定された場合におこなわれる、子宮頸がんの精密検査です。
コルポスコープと呼ばれる拡大鏡を用いて子宮頸部を詳しく観察し、疑わしい病変の組織を採取して病理検査(生検)をおこないます。
検査結果は、主に下記の6つに分かれます。
- 異常なし
- 軽度異形成
- 中等度異形成
- 高度異形成
- 上皮内がん
- 浸潤がん
細胞診で「異常あり」でも、コルポスコープ組織診では「異常なし」と判定されるケースが少なくありません。以降は、1~2年に1回は定期健診を受けるとよいでしょう。
軽度異形成・中等度異形成は、自然治癒する可能性が高いため4~6か月ごとの経過観察が基本となります。
高度異形成・上皮内がんの場合、状況に応じて厳重な経過観察や手術を検討します。
浸潤がんは、手術・放射線治療・化学療法などの治療が必要です。しかし、妊婦に対しては胎児への影響を考慮したうえで、大半は出産後におこなわれます。
ハイリスクHPV検査
ハイリスクHPV検査は、ヒトパピローマウイルス(HPV)の主な原因であるハイリスク型を検出する検査です。
子宮頸部の細胞を採取して遺伝子レベルで感染状況を調べ、子宮頸部のがんや異形成の有無、発症リスクを評価します。
検査結果は陽性・陰性のみで判定され、陽性の場合はコルポスコープ組織診にて精密検査をおこないます。
現在、ハイリスクHPV検査は、一部の子宮頸がん検診のみに含まれており、細胞診で異常を指摘された方や、子宮頸がんの治療後の経過観察として受診する際は、保険適用です。
また、妊娠中の方に対して無料で実施している自治体もあります。
妊娠中に子宮頸がんが見つかった場合は?

万が一、妊娠中に子宮頸がんが見つかった場合は、状況に応じて下記を検討します。
- 経過観察
- 手術
次章で詳しく解説します。妊娠中の方はもちろん、将来、妊娠・出産を望んでいる方もぜひ参考にしてください。
経過観察
一般的に、妊娠中に子宮頸がんが見つかった場合、妊娠を継続しながら慎重に経過観察をおこない、出産後に治療を開始します。
子宮頸がんの進行速度は比較的遅いうえに、高度異形成は分娩後に自然に縮小するケースも少なくありません。
そのため、浸潤がんに進行しない限りは直ちに治療せず、3~4か月ごとの細胞診やコルポスコープ組織診などで経過を見守ります。
手術
妊娠中の上皮内がんに対しては、電気メスやレーザーメス、超音波メスなどで子宮頸部を円錐状に切除する「円錐切除術」をおこないます。
子宮頸部円錐切除術は、安全性・有効性を考慮して妊娠初期(4か月)までにおこなうことが望ましいです。
妊娠中期以降は、進行期に応じて出産後に下記の手術をおこないます。
- 円錐切除術
- 子宮全摘出術
- 広汎子宮全摘出術
子宮頸部の一部を切除する円錐切除術に対し、子宮全摘出術は子宮を切除する手法です。
広汎子宮全摘出術では、がんの取り残しを避けるために、子宮と周りの組織や腟の大部分、必要に応じて骨盤内のリンパ節も切除します。
マイクロCTC検査は採血のみで全身のがんリスクを判定

マイクロCTC検査は、採血のみで全身のがんのリスクがわかる画期的な検査です。
血中のがん細胞を特異度94.45%で検出して1個単位で明示するため、がんの早期発見はもちろん、再発の有無や治療効果の確認にも役立ちます。
ここからは、マイクロCTC検査の魅力と概要を紹介します。
検査は1回5分の採血のみ
マイクロCTC検査は1回5分の採血のみで、子宮頸がんはもちろん、全身のがんリスクが判明します。
従来の検査で全身のがんを調べる場合は複数の検査を受ける必要があり、半日~1日程度の時間を要するため検査時間を確保できず、受診を後回しにする方も少なくありません。
がんは、発見が遅れるほどさまざまな部位に浸潤・転移し、治療における身体的・精神的・経済的な負担が増えて、転移・再発のリスクも増加します。
仕事・家庭・プライベートの時間を確保したい方は、短時間かつ手軽に受けられるマイクロCTC検査を活用し、がんの早期発見を目指しましょう。
また、検査予約から結果確認までWebで完結できることも、マイクロCTC検査の魅力の一つです。
自宅・外出先など、自身の都合のよい場所からアクセスできるため、わざわざ医療機関へ出向く手間がかかりません。
そのほか、完全予約制のマイクロCTC検査は、待ち時間の短縮にもつながります。
妊娠中でも検査可能
マイクロCTC検査は、妊娠中でも安心して受けられる血液検査です。
妊娠中は、胎児への影響を考慮して下記の検査が受けられない場合があります。
- X線・CT検査
- PET検査
- 内視鏡検査
乳がんの発見に有用なマンモグラフィや、肺がんの検出感度が高いCT検査は、放射線の一種であるX線を使用するため、胎児が被ばくする恐れがあります。
放射線薬剤を投与するPET検査も、同様の理由から妊娠中は控えるべきです。
胃がん・大腸がんの検査に用いられる内視鏡検査は、母体や胎児に刺激を与えます。早産・流産のリスクがあり、妊娠中は基本的に実施されません。
マイクロCTC検査は、採血した5~10mlの血液からがん細胞を検出する血液検査です。X線の照射や検査薬の投与が不要であり、被ばくの心配はありません。
体の負担・刺激がないことから、妊娠中でも問題なく全身のがんリスクを調べられます。
料金・クリニック概要
マイクロCTC検査は、1回198,000円(税込)です。※6
全身のがんを調べる総合検診+PET/CT検査コース(234,800~267,800円)と比べて、低コストといえます。※7
マイクロCTC検査は、全国176件のクリニックで導入されており、居住地域や勤務先などの希望エリアで受診が可能です。
検査の流れは、次のとおりです。
- クリニック検索
- 予約
- 個人情報・問診票の入力
- 検査
- 結果確認
まず、マイクロCTC検査の公式サイトにアクセスし、受診するクリニックと日時を選びます。はじめて利用する方は会員登録が必要です。
次いで、既往歴を含む個人情報と受診に必要な問診票を入力し、支払い方法を選択のうえ予約を確定させます。
検査当日は、身分証明書を持参して10分前に来院しましょう。医療機関の指示に従って採血を受ければ検査は終了です。
予約時にクレジットカードで決済した方は、そのまま帰宅できます。
検査結果は1週間前後で確定します。登録先のメールアドレスに通知が届いたらマイページで確認しましょう。
万が一、がん細胞が検出された場合でも、医師による無料相談が受けられます。
妊娠中の子宮頸がん検診に関するよくある質問
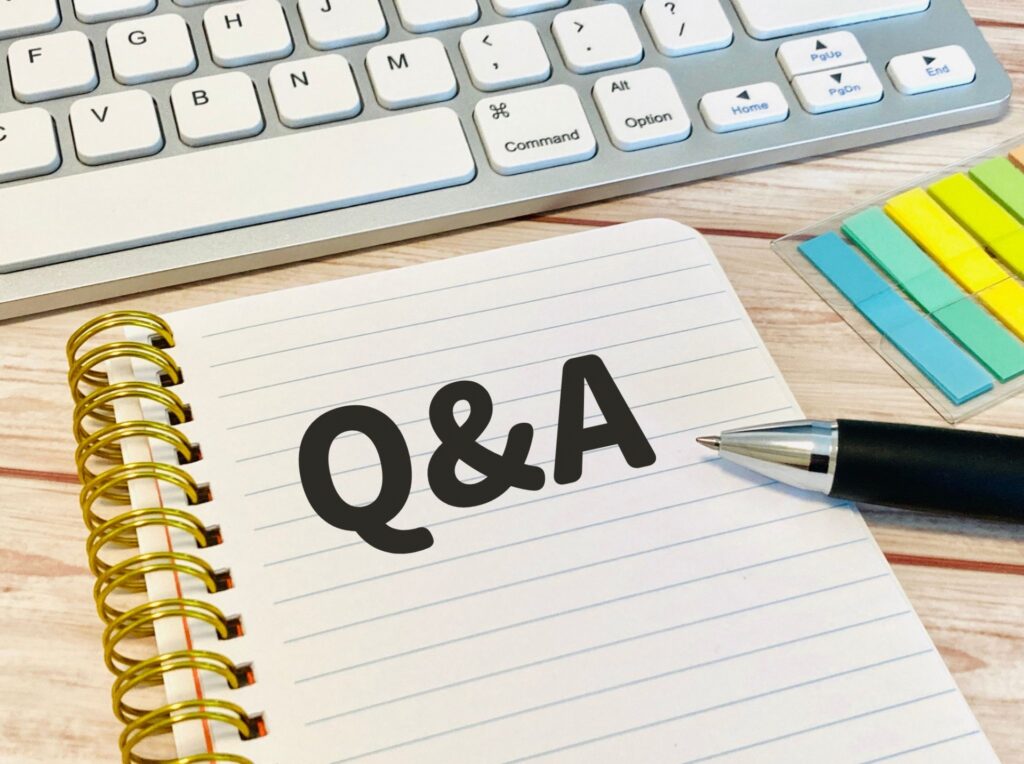
最後に、妊娠中の子宮頸がん検診に関するよくある質問を紹介します。
同じような悩みを抱いている方は、解決のヒントに活用ください。
子宮頸がんはお腹の赤ちゃんに影響する?
子宮頸がんは、お腹の赤ちゃんに影響を及ぼす可能性があります。
母親のがん細胞は、胎盤の血液を通して赤ちゃんのさまざまな臓器に広がるといわれており、子宮頸がんにおいては、赤ちゃんの肺への転移が確認されました。
赤ちゃんは、出産直後に泣くことで呼吸を開始します。その際、子宮頸がんのがん細胞が混じった羊水を赤ちゃんが吸い込み、肺にがんを発症します。
お腹の赤ちゃんを守るためにも、子宮頸がんの早期発見は重要です。
産後は子宮頸がんになりやすくなる?
産後に子宮頸がんのリスクが上がることはありません。
しかし、ヒトパピローマウイルス(HPV)の主な感染ルートは性交渉であるため、妊娠・出産の経験が多い方は、子宮頸がんになりやすいといえます。
出産直後は正しい結果が得られない可能性があるので、子宮頸がん検診は産後1年ほど経過してから受けましょう。
妊娠中に子宮頸がんワクチンを接種できる?
妊娠中の子宮頸がんワクチンは、安全性・有効性が確立されていないため、接種は避けた方がよいでしょう。
万が一、妊娠に気づかず接種した場合でも、妊娠初期であれば赤ちゃんへの影響は少ないといわれています。
子宮頸がんワクチンは、1年以内に3回の接種を終えることが望ましいとされていますが、完了する前に妊娠が発覚した際は、一旦中断します。
また、授乳中の接種も推奨されていません。授乳の中断が必要になります。
出産・授乳を終えてから接種を再開しても、一定の予防効果は期待できます。
まとめ

本記事では、妊娠中の子宮頸がん検診を中心に解説しました。
初期の子宮頸がんは、自覚症状がほぼありません。とくに発症リスクが高い20~40歳代の方は、定期的な子宮頸がん検診の受診が大切です。
また、妊婦健康検査においては、妊娠初期の検査項目に子宮頸がん検診が含まれています。
万が一、子宮頸がんが見つかり手術が必要になった場合でも、早期であれば妊娠を継続しながら治療が可能なため、該当する方は必ず検査を受けましょう。
妊娠中で従来のがん検査が受けられない方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は1回5分の採血のみで、子宮頸がんはもちろん、全身のがんリスクがわかります。
体の負担やお腹の赤ちゃんへの影響がないマイクロCTC検査を活用し、がんの早期発見につなげましょう。
〈参考サイト〉
※1:国立がん研究センター がん統計|子宮頸部
※2、※4:国立がん研究センター|集計表 全国がん罹患データ
※3:厚生労働省|令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況
※5:日本産婦人科医会|周産期の立場から(松本 直)
※6:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査
※7:国立がん研究センター 中央病院|検診費用
