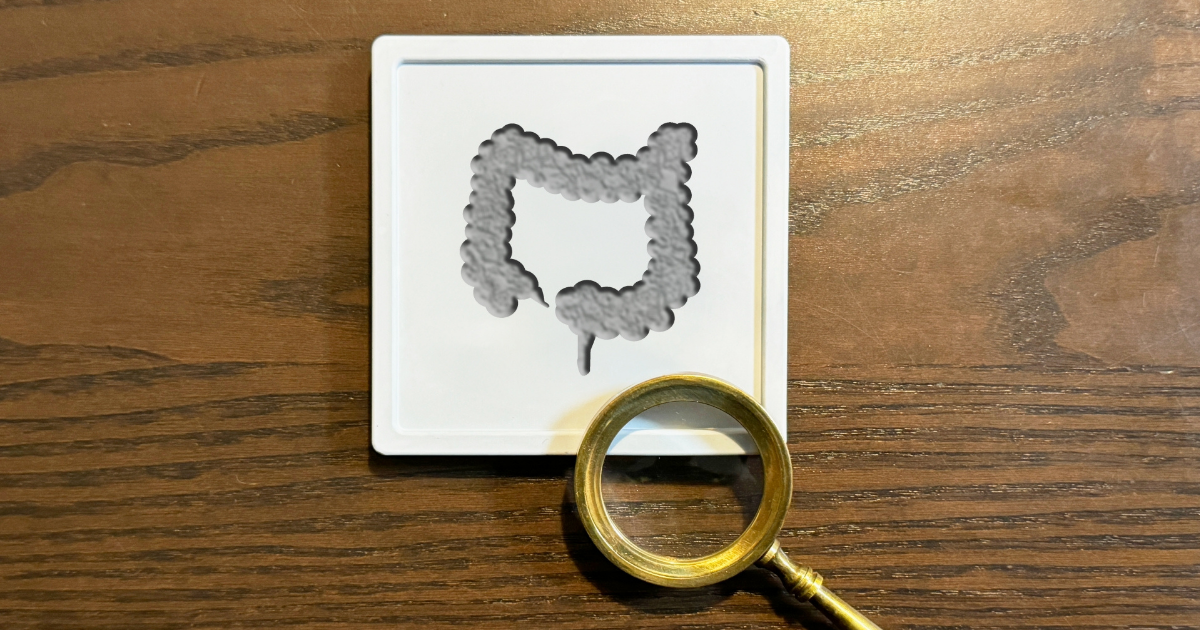大腸カメラ(大腸内視鏡検査)に対して、「痛い」「苦しい」とイメージを持っている方もいるでしょう。
しかし、大腸カメラの受診をためらっていると、病気が進行・悪化して命を危険にさらすことになります。
本記事では、大腸カメラの概要をはじめ、痛みの原因や痛みを感じやすい方の特徴、痛くない検査を受ける方法などを詳しく解説します。
大腸カメラは、大腸がんをはじめ、さまざまな病気の早期発見・早期治療に有用な検査です。
症状があるときはもちろん、無症状の場合でも医師に提案された際は、受診しましょう。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

大腸カメラ(大腸内視鏡検査)とは?

大腸カメラ(大腸内視鏡検査)とは、肛門から超小型カメラが搭載されたスコープを挿入し、大腸(結腸・直腸)と小腸の一部を観察する検査です。
多くの場合、血便をはじめ、下痢・便秘、腹痛などの症状がある際に、医師から検査を提案されますが、定期検診や経過観察を目的に大腸カメラを行うことも可能です。
大腸カメラは、粘膜の状態を直接観察できるため、次の病気の発見に役立ちます。
- 大腸がん
- 大腸ポリープ
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病
- 潰瘍性大腸炎
- 直腸潰瘍
また、モニターを通じてカメラから送られた映像をリアルタイムで確認できるため、検査と同時にがんやポリープの切除治療も可能です。
必要に応じて病変の組織の一部を採取して生検を実施し、確定診断につなげます。
大腸カメラが痛い原因

大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は、痛みや不快感を伴う場合があります。
おもな原因は、次のとおりです。
- 挿入による痛み
- お腹の張りによる苦痛
- 炎症・癒着の影響
次章では、それぞれの理由について詳しく解説します。
挿入による痛み
大腸カメラ(大腸内視鏡検査)では、先端にカメラが取り付けられたスコープを肛門から挿入し、直腸、S状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸、盲腸の順に観察します。
大腸カメラで使用するスコープは、直径10~13mm程度と非常に細径です。
しかし、挿入時にスコープが腸内を圧迫したり、引き延ばしたりと、周囲の筋肉・神経へ刺激を与えることで痛みが生じる場合があります。
とくに、臓器に固定されていないS状結腸と横行結腸は、強い痛みが伴うケースが多いです。
また、腸管のカーブが急な下行結腸と横行結腸の間(脾弯曲)や、横行結腸と上行結腸の間(肝弯曲)も、スコープによる刺激を受けやすい部位です。
近年では、腸を手前に畳み込むように短縮させ、形を整えながらスコープを進める「軸保持短縮法」を導入し、痛みの軽減に努めている医療機関が増えています。
お腹の張り
大腸は、自然な状態ではしぼんでいるため、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)をおこなう際は、空気を入れて腸内を膨らませて、視野を確保する必要があります。
空気は体内に吸収されにくく、腸の奥まで入れた空気はなかなか排出されません。そのため、お腹の張りによる苦痛を訴える方も少なくありません。
多くの医療機関では、空気より吸収力が優れている炭酸ガスを使用して、お腹の張りを速やかに解消するように努めています。
また、空気の代わりに少量の水を用いる水浸法を導入している医療機関もあります。
水浸法は、腸を膨らませる必要がなく、浮力によりスコープの摩擦が軽減するため、ほぼ痛みが生じないことが特徴です。
炎症・癒着の影響
大腸カメラ(大腸内視鏡検査)では、潰瘍性大腸炎やクローン病の場合、スコープが炎症部位に触れると痛みが発生します。
癒着とは、大腸がほかの臓器・組織と張り付いた状態を指し、過去の手術や憩室炎、虫垂炎などで引き起こされます。
癒着により腸のねじれ・狭窄が生じていると、スコープが曲がり、スムーズに腸内を通過できません。
そのため、腸管に不自然な圧がかかり腸が過度に伸展するため、痛みが引き起こされます。
大腸カメラで痛みを感じやすい方

大腸カメラ(大腸内視鏡検査)の痛みには個人差がありますが、次に該当する方は痛みを感じやすい傾向にあります。
- 体が小さい方
- 腸の神経が敏感な方
- 開腹手術の経験がある方
次章では、痛みを感じやすい理由を紹介します。
体が小さい
大腸の長さは、体が大きい方と小さい方で大きな差はありません。
体が小さい方や痩せている方は、狭い骨盤のなかに大腸が細かく折りたたまれています。そのため、腸のカーブが強く、スコープが挿入すると圧力がかかり、痛みを感じやすいです。
また、内臓脂肪が少ない方や高齢な方は、腸の固定が弱くスコープが安定しないため、スムーズに腸内を通過できず、痛みが引き起こされることがあります。
腸の神経が過敏
腸の神経が過敏になっている場合、スコープが通過する際に刺激を受けやすいため、過敏性腸症候群や感染性腸炎の方は、強い痛みを感じる場合があります。
また、過度に緊張・不安を抱くと、体が硬直して痛みが増すといわれています。
できる限りリラックスした状態で検査を受けることが大切です。
お腹を開ける手術の経験がある
お腹を開ける手術(開腹手術)を受けると、傷を治すために破損した臓器や組織がくっつく癒着が起こります。
癒着した部分は、ねじれたり、曲がったり、スコープの動きが制限されるため不自然な力が加わり、痛みを引き起こす場合があります。
虫垂炎、腸閉塞、胃・大腸・肝臓・胆嚢・子宮・卵巣などの手術歴がある方は、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)を受ける前に医師に伝えましょう。
痛くない大腸カメラ検査を受ける方法

ここで、痛くない大腸カメラ検査を受ける方法を紹介します。
過去に強い痛みを経験した方や、痛みが不安で検査をためらっている方は、ぜひ参考にしてください。
内視鏡の専門医がいる
痛みが少ない大腸カメラ(大腸内視鏡検査)を受けたい方は、内視鏡の専門医が在籍する医療機関がおすすめです。
内視鏡の専門医とは、内視鏡に関する豊富な知識・経験を持っており、「一般社団法人 日本消化器内視鏡学会」の認定を受けた医師です。
認定後も定期的に学会・研究会などに出席し、最新の内視鏡の技術やシステムを習得しています。
そのため、丁寧かつ患者の体への負担を抑えた大腸カメラの提供が可能です。
「一般社団法人 日本消化器内視鏡学会」の公式サイトでは、内視鏡の専門医名簿を公開しており、所属先の医療機関も掲載されています。
検査数・治療数が豊富
大腸カメラ(大腸内視鏡検査)の検査数・治療数が豊富な医療機関は、内視鏡専門医が複数人在籍しているケースが多いです。
また、十分に施設を整えたり、最新の内視鏡システムを採用したりと、内視鏡検査に力を入れていると考えてよいでしょう。
公式サイトに検査数・治療数の記載がない場合、内視鏡検査に携わっている期間が目安になります。
期間が長ければ長いほど、痛みに配慮した大腸カメラが期待できます。
鎮静剤を使用できる
鎮静剤は、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)による痛みの軽減に有効です。しかし、鎮静剤にはデメリットもあるため、使用せず検査をおこなう医療機関があります。
大腸カメラに対する不安が強い方や、検査中の痛みを和らげたい方には、鎮静剤が使用できる医療機関がおすすめです。
鎮静剤を使用した場合、眠っている間に検査が終了しますが、効果が薄れるまで院内で休む必要があります。
自身に合う下剤を選択できる
大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は、腸内を空にしてから実施するため、下剤の服用が必要です。
下剤は、種類により味や服用量などが異なるため、自身にあう下剤を選択できる医療機関を選びましょう。
また、下剤は自宅・院内のどちらかで服用します。来院までの便意を心配したくない方や、腹痛・嘔吐など急な体調変化が心配な方は、院内での服用がおすすめです。
院内で下剤を服用する場合、前処置室と呼ばれる部屋が必要です。
前処置室は、すべての医療機関に設けられているわけではないため、事前に確認しましょう。
マイクロCTC検査は痛みなく大腸がんリスクを判定

痛みなく、大腸をはじめとする全身のがんリスクを明確にしたい方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は、従来の検査に比べて非常に早い段階のがん細胞をキャッチし、個数を明示します。
ここからは、マイクロCTC検査の仕組み・所要時間・検査施設などを紹介します。
マイクロCTC検査の仕組み
マイクロCTC検査は、全身のがんリスクが非常に早い段階で明確になる血液検査です。
CSV(細胞表面ビメンチン)抗体と特殊な機械を用いて、血中に漏れ出したがん細胞を捉えて、個数を明示します。
遺伝子の異常により発症したがん細胞は、長い年月をかけて「がん」になります。
がん細胞が1cmになるまでには10~20年ほどかかりますが、1cmから2cmに成長するために必要な時間は、たった1年半程度です。※1
がん細胞の成長と進行速度は比例しており、早期がんで年単位、進行がんで半年単位、末期がんは1か月単位といわれています。
しかし、CT・MRI・PETなどの画像検査は、がん細胞が1cm以上にならない限り発見できません。
マイクロCTC検査の場合、発がんする前の1cm未満のがん細胞の捕捉が可能です。
検査は1回5分の採血のみ
マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで終了するため、忙しい方でも気軽に受診できます。
下記は、全身のがんを調べる検査の比較表です。
| 所要時間 | 事前準備 | 侵襲性 | 受診制限 | |
|---|---|---|---|---|
| マイクロCTC検査 | 1回5分 | なし | なし | なし |
| DWIBS検査 | 1~2時間 | なし | なし | あり |
| PET-CT検査 | 3~4時間 | 当日は絶食 | あり | あり |
マイクロCTC検査は、事前準備や着替えなどが一切不要で、どなたでも受診が可能です。また、予約から検査結果までWebで完結する手軽さも魅力の一つです。
DWIBS検査の場合、MRI装置を用いるため、ペースメーカーや人工内耳などが体内に入っている方や、金属製の塗料を使用したタトゥーをしている方は検査が受けられません。
PET-CT検査では、検査前に絶食をし、血液検査をおこなう必要があります。受付から会計までを含めると、半日程度かかるでしょう。
また、放射性の検査薬による医療被ばくがあります。
全国の提携医院で検査可能
マイクロCTC検査は、全国の提携医院で導入されています。
自宅や勤務先の近郊で受診したい方や、出張先・引っ越し先でも同様の検査を受けたい方におすすめです。
万が一、がん細胞が検出された場合、電話による無料相談が可能です。また、遠方の方に対してはオンライン面談を実施しています。
マイクロCTC検査センター長、および代々木ウィルクリニックの院長である太田医師が、検査結果の説明や精密検査の提案、専門医・医療機関の紹介をおこないます。
関連記事
大腸カメラの痛みに関するよくある質問

最後に、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)に関するよくある質問を紹介します。
大腸カメラの受診を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
大腸カメラと胃カメラはどちらが痛い?
大腸カメラと胃カメラは、痛みの種類が異なるため、程度は比べられません。
大腸カメラでは、腸の圧迫やお腹の張りによる痛みが生じますが、胃カメラの場合、嘔吐反射による苦痛が伴います。
ともに、眠ったような状態で検査が受けられる鎮静剤や、痛みを抑える鎮痛剤を用いることが可能です。
麻酔なしは痛い?
大腸カメラで使用する麻酔とは、一般的に鎮静剤(静脈麻酔)を指します。
大腸カメラの痛みは、鎮静剤を使わなくてもとくに痛みを感じない方もいれば、耐えがたいほどの苦痛が生じた方もいるなど、個人差が大きいです。
痛みが苦手な方、恐怖を感じる方は、鎮静剤を使用した方がよいでしょう。
しかし、心疾患や糖尿病、てんかんなどを患っている場合や、妊娠中・授乳中は鎮静剤を使用できません。
痛みが心配な際は、医師に相談しましょう。
激痛で中止する場合もある?
激痛により、検査を続けることが困難な場合は、中止する可能性があります。
鎮静剤の量を増やしての再検査や、スコープを挿入しない大腸CT検査を実施するケースもあるため、痛みが強いときは我慢せずに医師に伝えましょう。
まとめ
本記事では、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)の概要から、痛みの原因・痛みを感じやすい方の特徴、痛くない大腸カメラの受診方法まで解説しました。
大腸カメラは、大腸がんをはじめ、ポリープや腫瘍、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)などの発見が可能です。
しかし、挿入時の痛みやお腹の張りによる苦痛が生じるケースがあり、腸内に炎症・癒着がある場合は、強い痛みが伴います。
とくに、体が小さい方、腸の神経が敏感な方、過去に開腹手術を受けた方は、痛みが増す傾向にあるため、鎮静剤を用いた大腸カメラに対応している医療機関を選択しましょう。
大腸がんはもちろん、全員のがんリスクを短時間で把握したいときは、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は、従来の検査で発見が難しい小さながん細胞も捉えるため、非常に早い段階でがんリスクが明確になります。
定期的にマイクロCTC検査を受診すれば、発がんする前段階で発見でき、治療につなげることが可能です。
〈参考サイト〉
※1:がん対策推進企業アクション|早期がんを発見できる時間