卵巣がんは初期症状がほぼなく、自覚症状もお腹の張りや下腹部痛など女性がよく経験する症状のため、放置するケースも少なくありません。
がんが進行すると、卵巣の肥大化による激痛や、遠隔転移、さらには生命のリスクも高まるため、早期発見が望ましいです。
出産経験が少ない方、卵巣がんを患った血縁者がいる方は、卵巣がんにかかりやすいため無症状でも定期的にがん検診を受けることをおすすめします。
本記事では、卵巣がんが発覚するきっかけについて詳しく解説します。
卵巣がん発症の原因や初期症状の具体例、早期発見する方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

卵巣がんとは?

卵巣がんとは、卵巣にできる悪性腫瘍のことです。
がんが進行すると、下腹部の張りや食欲低下などが見られますが、初期症状はほぼないことで有名です。
そのため、たまたま受けた検診が卵巣がん発覚のきっかけになることも珍しくありません。
まずは、卵巣がんの特徴や症状について詳しく解説します。
卵巣がんの特徴
卵巣がんは、ほかのがんに比べて発症年齢が低いことが特徴です。
卵巣にできる腫瘍は、組織により上皮性腫瘍、胚細胞腫瘍、性索間質性腫瘍の3つに分類されることが一般的で、かかりやすい年代はそれぞれ異なります。
卵巣がんの約9割を占める上皮性卵巣がんは、40~60代がかかりやすいがんです。
卵巣胚細胞腫瘍は、10~30代の若い世代がかかりやすいがんで、どちらも共通して初期は無症状であるケースが多いです。
卵巣がんが進行するとガスがたまりやすい、便秘になりやすいなどの違和感を覚えることがあり、腫瘍がさらに大きくなると腹部に激痛が出る場合もあります。
若いから大丈夫、よくある不調だからそのうち治ると過信せず、早い段階から定期的に婦人科検診を受けることをおすすめします。
初期症状はほぼない
卵巣がんには、自覚できる初期症状がほぼありません。
卵巣に腫瘍ができた時点では、大多数の女性が無症状で過ごしていますが、腫瘍が大きくなるにつれて、子宮や膀胱、直腸が圧迫され不調を感じることが一般的です。
しかし、お腹の張りや下腹部痛は、不規則な生活やストレスにより見られる日常的な不調でもあるため、様子を見る女性が多い傾向にあります。
卵巣がん患者の半数以上が、進行した状態での発見となり完治が難しく、悪性度が高いがんに分類されます。
初期症状がほぼない卵巣がんを可能な限り早く見つけるためには、定期的にがん検診を受けることが大切です。
血縁者に卵巣がんを患った方がいる場合、下腹部の違和感や食欲低下などでも油断せず、早めに専門医に相談しましょう。
卵巣がんが発覚するきっかけ

初期症状がほぼない卵巣がんが発覚するきっかけは、主に婦人科での検診です。
検診以外ではがんの進行にともない現れる自覚症状が卵巣がん発覚のきっかけになることもあります。
卵巣がんが発覚するきっかけについて、詳しく解説します。
婦人科での検診
卵巣がんは、初期に症状が出にくいため、婦人科で専門医の検診で発覚します。
がん検診の受診率60%以上を目標に掲げる厚生労働省は、推奨するがん検診に子宮頸がんと乳がんを挙げていますが、卵巣がんは含まれていません。
しかし、早期発見が難しい卵巣がんは、見つかったときには進行している可能性が高いからこそ、定期的に検診を受けるべきです。
検診では主に、次のような検査がおこなわれます。
- 触診
- 内診
- エコー検査
- 腫瘍マーカー検査
- CT検査
- MRI検査
CT検査やMRI検査、腫瘍マーカーは悪性腫瘍の可能性が疑われ、精密検査が必要になった際におこないます。
子宮頸がん検診は、20歳以降、2年に一度の頻度で受けることが推奨されているため、早期発見のために、卵巣がん検診も追加して受けるとよいでしょう。
進行した場合の自覚症状
卵巣がんが進行した場合、自覚症状が発覚するきっかけとなります。卵巣がんが進行すると次のような症状があらわれることがあります。
- お腹が張る
- 腹部にしこりができる
- 食欲低下
- むくみ
- 頻尿や便秘
卵巣がんが進行し、腫瘍が大きくなると腹部が張り、服のウエストが急にきつくなることが多いです。
卵巣周辺の臓器が圧迫されることにより炎症が起こり、腹水が溜まるとお腹に張りが出て、食欲が低下する可能性もあります。
さらに、リンパ管が圧迫されるとむくみが、膀胱や腸が圧迫されると頻尿や便秘などの症状が出ます。
これらの症状が進行した卵巣がん発覚のきっかけになることもあるのです。
卵巣がんになりやすい方は?原因やリスク要因

卵巣がんは、35歳以上の女性や排卵の回数が多い方になりやすい傾向にあります。
主な原因には、婦人科系の疾患や遺伝です。ほかにも肥満や喫煙がリスク要因になる可能性もあります。
卵巣がんになりやすい方の特徴やリスク要因について、詳しく解説します。
35歳以上
卵巣がんは、35歳頃から罹患率と死亡率が上昇する傾向があります。
人口10万人に対する、卵巣がんの罹患率と死亡率を年齢別でまとめた表は、次のとおりです。(2020年)
| 年齢 | 罹患率 | 死亡率 |
|---|---|---|
| 20~24歳 | 5.6% | 0.1% |
| 25~29歳 | 6.5% | 0.3% |
| 30~34歳 | 9.3% | 0.4% |
| 35~39歳 | 12.2% | 1.3% |
| 40~44歳 | 19.4% | 3.1% |
| 45~49歳 | 28.0% | 5.4% |
| 50~54歳 | 35.1% | 9.6% |
| 55~59歳 | 34.3% | 10.5% |
| 60~64歳 | 33.1% | 12.6% |
| 65~69歳 | 29.9% | 13.0% |
| 70~74歳 | 27.7% | 14.0% |
卵巣では、排卵のたびに傷ついた被膜を修復しています。
卵巣がんは、傷ついた卵巣を修復する過程で発症リスクが高まるため、排卵の累計回数が多くなるにつれて、罹患率は上昇します。
排卵の回数が多い
排卵の回数が多いほど卵巣の修復活動も多くなるため、卵巣がんにかかりやすいです。
具体的には、次のような女性は排卵の回数が多く、発症リスクが高い可能性があります。
- 妊娠、出産経験が少ない
- 初経が早い
- 閉経が遅い
出産経験が少ない女性のほうが卵巣がんにかかりやすいと考えられる理由は、複数回出産している方よりも、排卵累計数が多いためです。
妊娠出産すると排卵は約2年間止まるため、出産回数が多いほど、卵巣がん発症の要因リスクは減少します。
一方で、妊娠出産経験が少ない女性は、排卵の停止期間が短く、卵巣がんにかかりやすいと考えられます。
また、初経が早い方、閉経が遅い方も排卵の累計回数が多いことが理由で、卵巣がんにかかりやすいといえるでしょう。
婦人科系の疾患
子宮内膜症の一種であるチョコレート嚢胞は、がん化する可能性が高いため注意が必要です。
すべてのチョコレート嚢胞ががん化するわけではありませんが、嚢胞の大きさが10cm以上になると卵巣がん合併率は高くなります。
また、卵巣がん合併率を年齢別でみると40代は4.11%。50代は21.93%、60代は49.09%と大きく上昇します。
40代以上の方で強い月経痛や下腹痛、不正出血などの症状が続く場合は、早めに婦人科を受診しましょう。
肥満・喫煙
生活習慣の乱れや不摂生は多くのがんのリスク要因となりますが、卵巣がんの場合、肥満と喫煙にとくに注意が必要です。
BMI30以上の女性は、標準体重の女性よりも卵巣がんの発症リスクが高くなります。
喫煙は、卵巣がんに限らず多くのがんの原因となるため、喫煙習慣のある方は禁煙を目標に、改善に取り組むことをおすすめします。
適度な運動と規則正しい食事で標準体重を維持し、喫煙習慣をなくすと卵巣がんのリスク軽減に効果が期待できるでしょう。
遺伝
卵巣がんは、約10%が遺伝的な要因で発症すると考えられています。
原因となる遺伝子はBRCA1、BRCA2と呼ばれる2種類で、いずれかの遺伝子に変化がある女性は卵巣がんの発症リスクが高いです。
2020年度より、BRCA1とBRCA2の遺伝子検査が保険適用となったため、血縁者に卵巣がんを患った方がいる場合、遺伝子検査を検討するとよいでしょう。
ただし、保険適用には一定の基準が設けられており、希望する方は事前に確認する必要があります。
卵巣がんの検査方法や治療法

卵巣がん検診では主に、触診やエコー検査をおこない、悪性腫瘍の可能性が疑われる場合MRI検査やCT検査でより詳しく調べます。
がんの治療方法は進行度により大きく異なるため卵巣がんが発見された場合には、ステージに適した治療を受けることが大切です。
卵巣がんの検査方法と治療方法について、詳しく解説します。
検査方法
卵巣がん検診ではまず、お腹を軽く押して調べる触診、腟から卵巣に触れて調べる内診、超音波を当てて画像化するエコー検査などをおこなうことが一般的です。
腫瘍の大きさや、ほかの臓器との位置関係の把握につながりますが、初期の小さな腫瘍は発見に至らない場合もあります。
腫瘍が確認されたら、CT検査やMRI検査で転移していないか調べ、良性か悪性か判断するために病理検査をおこないます。
卵巣がんの場合、病理検査に必要な病変の採取には手術が必要です。卵巣の一部や腹水を詳しく調べ、がんの種類やステージを確定させます。
がんの進行具合や治療経過の確認を目的に、がんにより増加するたんぱく質の量を測定する腫瘍マーカー検査がおこなわれるケースもあります。
治療方法
卵巣は骨盤の奥深くにあり、検査のみでは正確な進行度が把握できません。そのため、まず手術で可能な限り腫瘍を取り除きます。
卵巣がんの治療には薬物療法が選択されることが多く、切除した卵巣からがんの種類や進行度を調べ、適切な治療薬が提案されます。
ただし、発見が遅れ広範囲ががん化している場合には、手術前に抗がん剤治療をおこない、がんの範囲を小さくしてから切除に臨む方針が効果的です。
再発した場合の治療も、主に薬物療法となりますが、激しい痛みがともなう場合には局所的に放射線治療がおこなわれるケースもあります。
卵巣がんは早期発見が重要

卵巣がんは、初期症状が出にくく発見が遅れやすいがんですが、生存率を高めるためには早期発見と早期治療が何よりも大切です。
卵巣がんの状態ごとの5年生存率は、次の表のとおりです。
| 状態 | 5年生存率 |
|---|---|
| がんが卵巣内にのみある状態 | 92.5% |
| 骨盤やリンパ節にも転移している状態 | 59.3% |
| 遠隔の臓器やリンパ節にまで転移している状態 | 23.9% |
卵巣がんの場合、自覚症状が出たときには、すでにがんが進行している可能性が高いです。
そのため、自覚症状がなくても定期的に検診を受け、早期発見に努めることが重要になります。
卵巣がんの早期発見にマイクロCTC検査がおすすめ

卵巣がんの早期発見が難しく、定期検診が大切ではあるものの、家事や仕事、育児が忙しく、がん検診に行く時間が取れない女性もいるでしょう。
自身のことは二の次にしがちな女性には、がんリスクを手軽に判定できる「マイクロCTC検査」がおすすめです。
さまざまな理由でがん検診を受診できていない女性にマイクロCTC検査をおすすめする3つの理由を詳しく解説します。
検査は1回の採血のみ
マイクロCTC検査は、血液がんを除く全身のがんリスクを1回の採血のみで確認できます。
全身のがん検査を受けようとするとPET/CTやMRIに加えて、胃カメラなど複数の検査を受ける必要があり、半日以上かかります。
中には、1日ではすべての検査を受けられないこともあり、その場合には別日に再受診しなければなりません。
マイクロCTC検査であれば、予約時に問診票の記入や支払い方法の選択が済んでいるため、検査当日は採血のみですぐに終了となります。
所要時間は短く、体への負担も少ないため、仕事の休憩時間や外出時の隙間時間の有効活用にも適しています。
卵巣がんの場合、腟から卵巣の状態を確認する内診に抵抗を感じる女性も少なくありませんが、採血のみのマイクロCTC検査ならば安心です。
がん検診に割く時間がない方、検査に強い抵抗があり気が進まない方は、マイクロCTC検査を検討するとよいでしょう。
全身のがんリスクを判定可能
マイクロCTC検査は、少量の血液で全身のがんリスクを判定できます。
CTC検査とは、血中に漏れ出たがん細胞を捕捉する検査で、悪性化したがん細胞が存在する部位の発見に役立ちます。
卵巣がんの場合、腫瘍が小さい初期の時点では、触診やエコー検査でがんを発見できないケースも多いです。
初期症状がないため自身でも異変に気付けず、発覚したときにはすでに卵巣がんが進行している女性も少なくありません。
対して、血中に含まれるがん細胞を捕捉できるマイクロCTC検査ならば、早期発見に高い効果が期待できます。
また、卵巣がん以外のがんリスクも同時に判定できるため、体への負担を大きく軽減でき、検査のハードルが低くなります。
造影剤が苦手な方、被ばく量が不安でCT検査に抵抗がある方も安心して受けられるでしょう。
マイクロCTC検査は、がん検診にかかる時間、肉体的または精神的な負担を可能な限り減らして、全身のがんリスクを判定できる検査です。
料金・クリニック概要
マイクロCTC検査の料金は、1回198,000円(税込)です。提携クリニックは、全国に176件もあり、来院しやすいクリニックを選択できます。
予約は最大12か月先まで対応しているため、都合のよい日時の予約を取りやすいでしょう。
検査結果はWebで確認可能で、がん細胞が検出された方は代々木ウィルクリニックで指定医師の無料相談が受けられます。
オンライン相談にも対応しているため、遠方でクリニックに来院できない方でも安心です。
卵巣がんに関するよくある質問
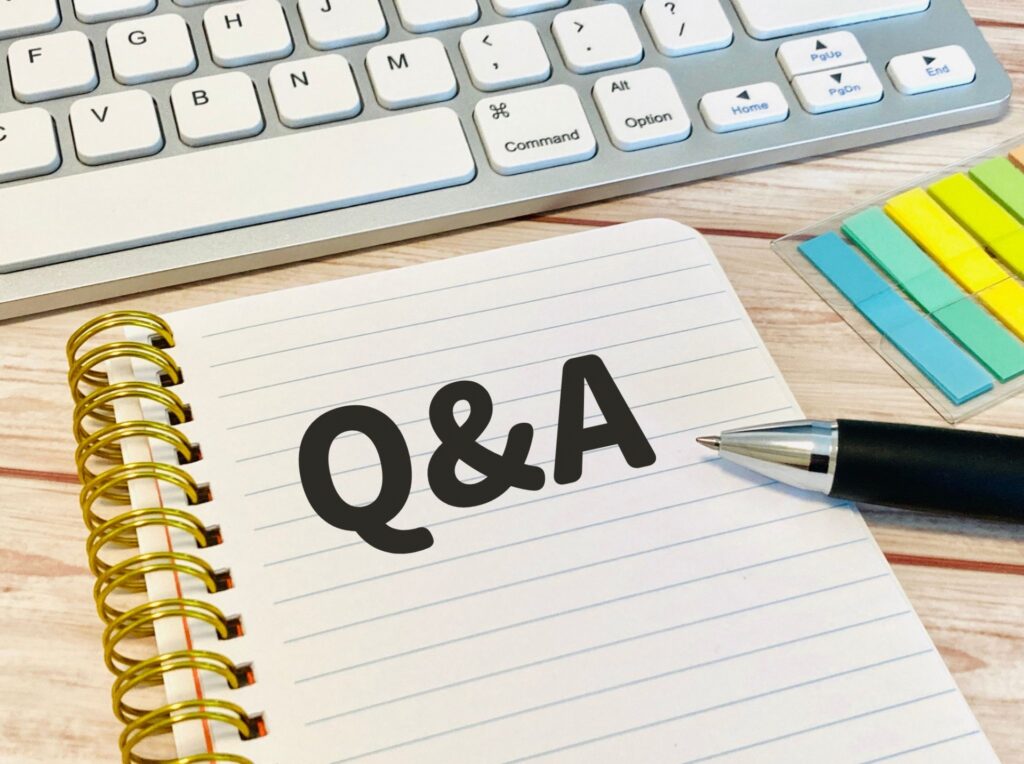
最後に、卵巣がんに関するよくある質問に回答します。
下腹部にしこりがあり不安な方、進行速度や予防法を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
下腹部にしこりを感じる?
卵巣がんにかかった約2割の方が、下腹部のしこりを自覚しています。
腫瘍が大きくなり卵巣が肥大化すると、下腹部の左右どちらかにしこりが生じます。
腰骨の少し下に硬いしこりがある場合は、早急に婦人科を受診しましょう。
進行速度は?
卵巣がんは、種類により進行速度が異なります。
卵巣がんの約9割を占める上皮性腫瘍の進行速度は、比較的遅い傾向にあります。
しかし、自覚症状が出にくいため発覚したときには、転移の可能性が考えられるほど進行しているケースも珍しくありません。
胚細胞腫瘍も上皮性腫瘍と同じく、進行速度は遅めです。性索間質性腫瘍は、上記の2種類よりは早く進行する傾向にあります。
ただし、がんの進行速度は年齢や体力などによる個人差も大きいため、あくまで目安として捉えましょう。
予防する方法は?
次の取り組みは、がん全般の予防に効果が期待できます。
- 禁煙
- アルコール摂取量の見直し
- 栄養バランスの整った食事
- 適度な運動
- 適正体重の維持
- 感染対策
卵巣がんのみを対象にした予防法は現時点では発表されていませんが、国立がん研究センターは上記の6つをがんの予防法として推奨しています。
生活習慣全般を見直し、健康的な暮らしを続けたうえで、定期的に検診を受けることががん予防に効果的な方法といえるでしょう。
まとめ

卵巣がんは初期症状がほぼなく、早期発見が難しいがんです。
排卵の回数が多いと卵巣がんの発症リスクが高いと考えられているため、出産経験が少ない方、初経が早い方、閉経が遅い方はとくに定期検診の受診をおすすめします。
しかし、自覚症状がないと検診を受ける気になれない、内診に抵抗があり病院に行きたくないと感じる方も多いでしょう。
また、仕事や育児、家事が忙しくて受診する時間が取れない女性も少なくありません。
さまざまな理由でがん検診を受診できていない方には1回5分の採血で、血液がんを除く全身のがんリスクを判定できる「マイクロCTC検査」がおすすめです。
がん細胞を捕捉できる検査で、早期発見が難しい卵巣がんの検査に適しています。
