前立腺がんは、男性が最もかかりやすいがんです。生涯のうち、男性の10人に1人が前立腺がんになるといわれています。※1
近年では、日本人の高齢化や食生活の欧米化により前立腺がんの罹患数は増えており、今後も増加の一途を辿る可能性が高いです。
本記事では、前立腺がんの概要・原因・症状から、前立腺がんになりやすい人の特徴や、検査・治療・予防の方法まで詳しく解説します。
多くの前立腺がんは初期の自覚症状がないため、早期発見のためには前立腺がんに関する知識を深めておくことが重要です。ぜひ参考にしてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

前立腺がんとは?

前立腺がんとは、男性のみにある前立腺の細胞ががん化する病気です。
2020年では87,753人が前立腺がんと診断されており、今後も増加が予想されます。※2
前立腺がんは、発がんまで40年近くかかるといわれており、進行速度が遅いことからほかのがんと比べて死亡率が低い傾向にあります。※3
しかし、初期の自覚症状がないケースが多く、早期発見のためには定期的な検査が重要です。
次章では、前立腺がんの概要・症状を紹介します。
中高年の男性に多いがん
前立腺がんは、加齢とともに発症率が高まり、60歳代から急激に増え始めて70歳代にピークを迎えます。
年代別の罹患数は、次のとおりです。
| 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
|---|---|---|---|---|
| 罹患数 | 3,488人 | 18,555人 | 40,835人 | 21,462人 |
前立腺がんは、70歳代男性の全がん罹患数の約20%を占めており、80歳代の半数以上の男性が罹患しているといわれています。※4
発症には、食生活・生活習慣をはじめ、さまざまな要因が考えられていますが、加齢に伴う男性ホルモンの乱れや慢性的な前立腺の炎症も深く関与しているといえます。
30・40歳代で発症するケースは非常に稀ですが、遺伝子的要素も発症に影響を及ぼすため、とくに前立腺がんの家族歴がある方は注意が必要です。
主な症状
前立腺がんは、初期の自覚症状に乏しく、進行に伴い下記の症状が現れる場合があります。
- 尿が出にくい
- 排尿の回数が増える
- 排尿時に痛みがある
- 尿・精液に血が混じる
前立腺は、膀胱のしたにあり、尿道を取り囲んでいるため排尿に関する異変が起こりやすいです。
排尿困難・頻尿・排尿痛のほか、尿意が我慢できなくなる尿意切迫や、尿がまったく出ない状態の尿閉が引き起こされるケースも少なくありません。
また、尿道が圧迫されて血尿が出たり、精のうが影響を受けて精液に血が混じったりなどの症状が、前立腺がんの進行とともに現れる場合もあります。
そのほか、がんが骨に転移すると腰・背中・股関節・太ももなどに痛み、手・足のしびれなどが起こりやすくなります。
前立腺がんになりやすい人は?
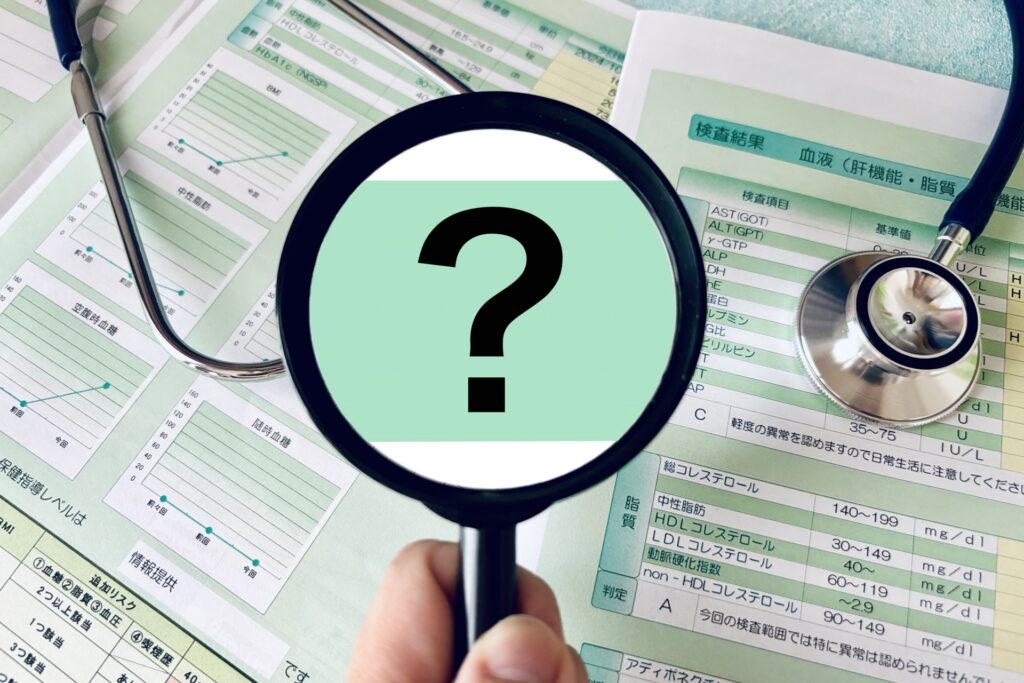
ここで、前立腺がんになりやすい人の特徴を紹介します。
前立腺がんの発症には、さまざまな原因が考えられており、主に下記の要因が深く関与しているといわれています。
- 遺伝(家族歴)
- 男性ホルモン
- 肥満
- 喫煙
- 食生活
次章では、前立腺がんとそれぞれの要因の関係を詳しく解説します。
遺伝(家族歴)
前立腺がんは、遺伝要因が強いことがわかっており、父親の家族歴では7.52倍、兄弟の場合は5.6倍です。※5
2人以上の家族歴を有する方のリスクはさらに高まり、とくに、生殖細胞系の「HOXB13」の変異(G84E)保因者は最大で20.1倍まで上昇します。※6
また、前立腺がんはBRCA1やBRCA2の変異の影響を受けるため、前立腺がんのみならず、乳がんや卵巣がん、腎臓がんの家族歴がある方も注意が必要です。
一般的に、前立腺がん検診の対象年齢は50歳以上ですが、家族歴がある際は40歳から定期的に検査を受けることが大切です。
男性ホルモン
男性ホルモンの変化は、前立腺がんの発症に深く関与しています。
精巣や副腎から分泌される男性ホルモンは、加齢とともに減少してホルモンバランスを崩し、前立腺の細胞は正常な状態を保てなくなることでがん化すると考えられています。
また、前立腺がんは男性ホルモンの刺激により増殖するため、治療や進行予防にホルモン療法が有効です。
肥満
肥満は、前立腺がんの要因として推測されています。
発症のみならず、がんの進行にも影響を与え死亡率を上昇させる可能性も示唆されており、肥満に分類されるBMI30値以上の死亡リスクは、標準体重の1.28倍です。※7
また、肥満によるインスリンの過剰分泌により、食道・膵臓・肝臓・大腸・腎臓などにもがんが発症しやすくなるといわれています。
そのほか、肥満は狭心症や心筋梗塞などの心疾患、脳梗塞をはじめとする脳疾患のリスクなども高めるため、該当する方は改善を目指しましょう。
喫煙
喫煙は、前立腺がんの発症率を高めることがわかっています。
非喫煙者に比べて喫煙者のリスクは1.4~2倍で、国立がん研究センターの報告によると、前立腺がん患者全体の38.8~45.3%は喫煙者でした。※8※9
また、ヘビースモーカーの場合、死亡リスクが24~30%ほど高まるといわれています。※10
そのほか、喫煙はがん全体の発生率を1.6倍ほど高め、死亡率も上昇させることが認められています。※11
食生活
食生活は、前立腺がんの要因の一つです。欧米型の食事パターンは、発症リスクが22%増えることがわかっています。※12
欧米型の食事パターンとは、肉類・加工肉などの高脂肪食を多く摂り、野菜・果物・大豆食品の摂取量が少ない食生活です。
近年では、ファーストフードや加工品の普及で、新たな食材や調理法を使用した世界の食文化が広がり、無意識に偏った欧米型の食生活を送っている方も少なくありません。
健康型の食事パターンに改善すれば、前立腺がんのリスクを約30%下げることが可能です。前立腺がんはもちろん、がん全体の予防にもつながるため食生活を見直しましょう。※13
そのほか、過度な飲酒も前立腺がんのリスク上昇につながります。禁酒・節酒を心がけることが大切です。
前立腺がんの検査・診断方法

前立腺がんの検査・診断方法は、下記のとおりです。
- PSA検査
- 直腸診・超音波検査
- 画像診断
- 生検
次章では、それぞれの概要を詳しく紹介します。
PSA検査
PSA検査とは、前立腺がんのスクリーニング検査として最初におこなう腫瘍マーカーです。
PSAとは、前立腺でつくられるタンパク質分解酵素(前立腺特異抗原)のことで、前立腺に何らかの異常があると血液中に漏れ出すことがわかっています。
血中のPSA濃度が高く、数値が高い場合は前立腺がんが疑われます。
年齢別のPSA基準値は、下記のとおりです。
| 年齢 | PSA基準値 |
|---|---|
| 50~64歳 | 3.0ng/ml以下 |
| 65~69歳 | 3.5ng/ml以下 |
| 70歳以上 | 4.0ng/ml以下 |
PSA値は加齢に伴い上昇するため年齢別の基準値が設けられていますが、がんのみならず、前立腺肥大症や前立腺炎などの疾患にも反応します。
そのため、標準以下でも前立腺がんが発見されるケースがある一方で、100ng/mlを超えていても前立腺がんを発症していない場合もあります。
直腸診・超音波検査
PSA値が基準値を超えている場合、直腸の壁越しに前立腺を触診する直腸診をおこないます。
直腸診とは、医師が肛門から指を入れて、前立腺の大きさ・硬さ・左右非対称性、表面の凹凸や痛みの有無などを詳しく調べる検査です。
正常な前立腺は弾力性のあるクルミ程度のサイズですが、がんが発生すると石のように硬くなったり、左右の大きさが異なったりと、何らかの異常が認められます。
直腸診にて異常が確認された際は、経直腸エコーと呼ばれる超音波検査が有効です。
超音波検査では、超音波を発するプローブを挿入し、前立腺の内部を画像化して詳しく観察して異常の原因を調べます。
万が一、がんがある場合は黒い影として映し出されます。
画像診断
前立腺がんには、下記の画像診断が用いられます。
- CT検査
- MRI検査
- 骨シンチグラフィ
CT検査は、X線を照射して体の断面画像を撮影する検査で、前立腺がんの有無からリンパ節や肺への転移まで調べることが可能です。
短時間で実施できることがメリットですが、被ばくのリスクが伴います。
MRI検査では、磁気を使用してさまざまな方向から撮影し、3次元の断面画を描写します。組織分解能に優れているため、前立腺がんの有無・広がりなどの総合的な評価に有効です。
被ばくのリスクはなく、骨の影響を受けずに血管まで撮影できる点が強みです。
骨への転移が疑われる場合、骨の代謝が盛んな部位に集まる性質を持つ薬剤を注射して全身の骨の状態を確認する、骨シンチグラフィがおこなわれます。
より正確な診断のために、複数の画像検査を組み合わせる医療機関もあります。
生検
前立腺がんの確定診断には、生検が必要です。
生検では、直腸にプローブを挿入して超音波で画像を映しながら、がんが疑われる場所の組織を採取します。
稀に出血や発熱が起こりますが、基本的に痛みは少ないことから全身麻酔の必要がなく、外来でも実施が可能です。
採取した組織は、顕微鏡で観察してがん細胞の有無を確認し、グリーソンスコアを用いて悪性度を評価します。
一部の医療機関では、肛門と陰嚢の間の会陰部から針を刺す「経会陰生検」を採用しています。経会陰生検の場合、麻酔が必要となるため2~3日の入院が必要です。
前立腺がんの治療・予防方法

前立腺がんには、手術療法・放射線療法・薬物療法などのさまざまな治療法があり、必要に応じて複数の治療法を組み合わせます。
また、前立腺がんには生命を脅かさないものが存在しており、治療の緊急性が低い場合は監視療法と呼ばれる経過観察を検討します。
治療法は、患者の全身状態・年齢・要望はもちろん、PSA値とグリーソンスコア、TNM分類などの因子を考慮して決めることが重要です。
次章では、それぞれの治療法と予防方法を詳しく紹介します。
治療方法
前立腺がんの主な治療法は、下記のとおりです。
- フォーカルセラピー
- 手術療法
- 放射線療法
- 薬物療法
フォーカルセラピーとは、前立腺の正常組織を残してがんが発生した部位のみを治療する治療法で、身体機能を温存しながら治療ができることが最大のメリットです。
前立腺がんの標準的な手術療法は、前立腺全摘除術です。前立腺・精のうを摘出したあと、膀胱と尿道をつなぎ合わせる手法で、必要に応じて周囲のリンパ節も取り除きます。
放射線療法には、外部照射療法と組織内照射療法があり、がんの進行度や全身状態を考慮したうえで選択されます。
前立腺がんには、薬物療法の一つであるホルモン療法が非常に有効です。男性ホルモンの作用を妨げることでがんの増殖を抑えて治療します。
そのほか、がんの転移・再発を防いだり、がんによる症状を緩和したり、抗がん剤を用いた薬物療法を併用するケースが多いです。
予防方法
前立腺がんに限らず、すべてのがんの予防には下記の方法が効果的です。
- 禁煙する
- 節酒を心がける
- 食生活を見直す
- 体を動かす
- 適正体重を維持する
喫煙は何らかのがんになるリスクが約1.5倍高まります。禁煙が難しい方は、医療機関や専門家のサポートを受けながら取り組みましょう。※14
過度な飲酒はがんの危険因子の一つです。1日あたりのアルコール摂取量が23g程度を超えないように気をつけましょう。
また、塩分濃度が高い食べ物を避ける、野菜・果物を多く摂るなど、食生活の見直しもがん予防の効果が期待できます。
そのほか、適度な運動や適正体重の維持も、がんの予防につながります。
マイクロCTC検査は採血のみでがんを捕捉

マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで前立腺がんを含む全身のがんリスクが明確になる血液検査です。
血中に漏れ出したがん細胞を特異度94.45%で検出するため、従来の検査よりがんの早期発見・早期治療につながります。※15
ここからは、マイクロCTC検査の概要・魅力を紹介します。
先進的検査で全身のがんリスクを判定
マイクロCTC検査は、従来の検査と比べて下記の点が優れています。
- 超早期のがん発見につながる
- 悪性度の高いがん細胞のみを捕捉できる
- 短時間で全身のがんリスクが判明する
CT・MRI・PETなどの画像検査では、1cm未満の小さながんは見つけにくいといわれており、早期がんのうちに発見できる期間は長くありません。
マイクロCTC検査の場合、血中のがん細胞そのものをキャッチするため、発がんの前段階でもリスクが把握でき、がんの早期発見につながります。
そのほか、検査時間がスピーディなこともマイクロCTC検査の魅力です。
人間ドックで全身のがんを調べる場合、半日~1日程度の時間がかかるため、仕事や家庭などで忙しい方は受診のハードルが高いと感じるでしょう。
マイクロCTC検査は1回5分の採血のみで、受付を含めても30分程度で終了します。時間をかけず、手軽に自身のがんリスクを知りたい方はマイクロCTC検査を活用しましょう。
高精度・迅速な検査体制を実現
これまでのCTC検査では、「上皮性がん細胞」しか検出できませんでした。
マイクロCTC検査は、世界有数のがん治療・研究施設「米国MDアンダーソンがんセンター」が開発した抗体を用いた独自の検出方法を導入しています。
そのため、特異度94.45%を誇る非常に高い精度で、浸潤・転移の危険がある悪性度の高い「間葉系がん細胞」のみを捉えることが可能です。※16
また、血液検体をスムーズかつ正確に分析するために、国内に民間初となる検査センターを設けて迅速な検査体制と高い検査品質を実現しています。
AIによる分析と専門の検査技師による解析のダブルチェックをおこなうことで、高品質のがんリスク検査を可能にしています。
充実したアフターフォローで安心
マイクロCTC検査でがん細胞が検出された方は、医師による無料相談が受けられます。
無料相談は、マイクロCTC検査センター長および代々木ウィルクリニックの太田医師が担当し、下記の相談に対応しています。
- 検査結果の詳しい説明
- 受けるべき精密検査の内容
- 専門医・医療機関の紹介
基本的に無料相談はクリニックで直接対面での面談で実施していますが、遠方の方はオンライン面談が可能です。
相談後、画像診断や内視鏡検査などを受診してもがんが発見されなかった場合は、再度相談が受けられます。
万が一のとき、医師に相談できるため、1人で悩まず安心して検査が受けられることも、マイクロCTC検査の魅力の一つです。
関連記事
まとめ

本記事では、前立腺がんになりやすい人の特徴やリスクを高める原因などを中心に解説しました。
前立腺がんは、男性のがん罹患数の1位であり、とくに50歳以上の中高年の男性に多く、70歳代で好発します。※17
前立腺がんの原因には、遺伝(家族歴)、男性ホルモン、肥満、喫煙、食生活などが考えられているため、該当する方は定期的に検査を受けることが大切です。
大半の前立腺がんには初期の自覚症状がないため、前立腺がんの早期発見を目指す方にはマイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで前立腺がんを含む全身のがんリスクが判明します。
高精度・高品質ながん検査を手軽に受けたいときは、マイクロCTC検査を検討しましょう。
〈参考サイト〉
※1、※2、※17:国立がん研究センター がん統計|最新がん統計
※3:武田薬品工業株式会社|前立腺がんの特徴
※4:国立がん研究センター 集計表|全国がん罹患データ
※5:日本泌尿科学会|前立腺がん 検診ガイドライン(2018年版)
※6:日本癌治療学会|前立腺がん 診療ガイドライン
※7:医師向け医療ニュース ケアネット|前立腺がん、診断後の肥満は死亡リスクと関連
※8:国立がん研究センター がん対策研究所|飲酒・喫煙と前立腺がんとの関連について
※9:日経メディカル|喫煙は「たちの悪い」前立腺癌を増やす−−米研究
※10:PubMed|前立腺がんの危険因子としての喫煙
※11:国立がん研究センター がん対策研究所|喫煙と全がんリスク
※12、※13:国立がん研究センター がん対策研究所|食事パターンと前立腺がん罹患との関連
※14:国立がん研究センター|科学的根拠に基づくがん予防
※15、※16:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査
