ほくろ(ホクロ)は、多くの場合、ほくろは体に影響を与えない良性の腫瘍ですが、皮膚がんの可能性も否定できません。
皮膚がんには、ほくろと似たものが多く存在するため、見極めが重要です。
とくに、急に大きくなったり、数が増えたりして、色・形に変化が現れた場合は皮膚がんが疑われます。
本記事では、皮膚がんの概要をはじめ、ほくろと似ている皮膚がんの種類や見分け方、皮膚がんの検査方法・治療法などを詳しく解説します。
最近、ほくろが増えたように感じる方や、ほくろの形状が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

皮膚がんとは?
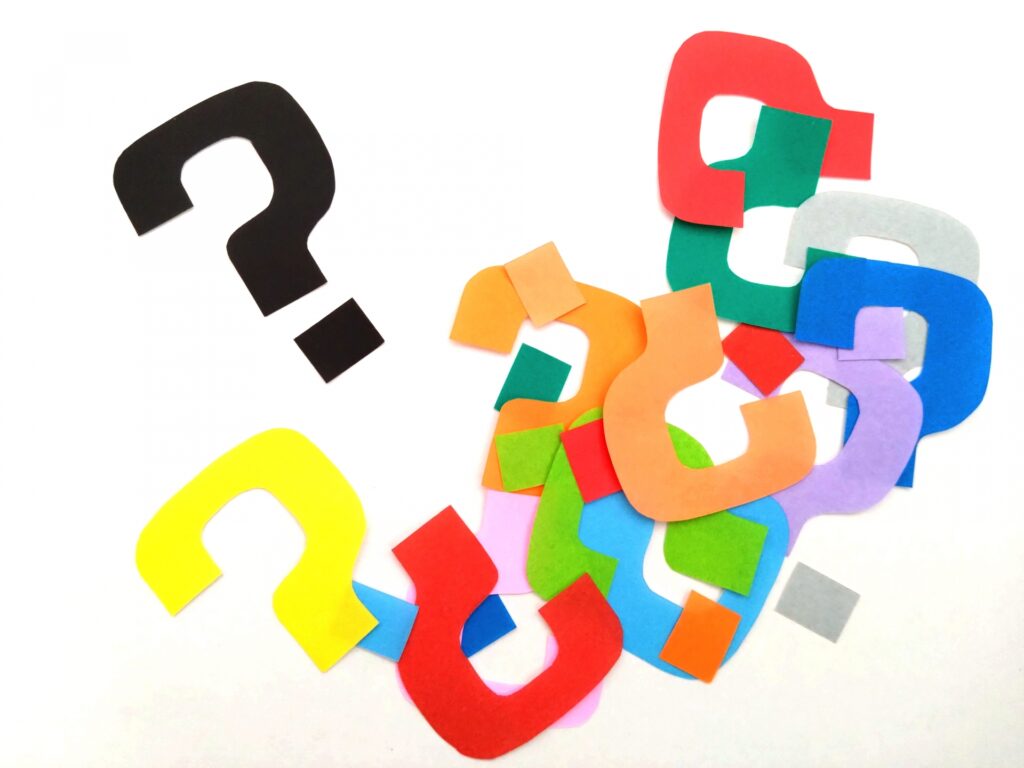
皮膚がんとは、皮膚に発症するがんの総称です。内臓にできるがんと異なり、症状が目視できることから早期発見しやすいといわれています。
しかし、ほくろ(ホクロ)をはじめ、できもの・湿疹などの形状と似ているため、見過ごしてしまいがちです。
皮膚がんの主な原因は、下記のとおりです。
- 紫外線
- 放射線
- ウイルス
- 化学物質
皮膚がんの約80%は、紫外線が原因です。※1
長年にわたり、繰り返し紫外線によるダメージを受けた皮膚のDNAは、制御不能に増殖して皮膚がんを引き起こします。また、放射線も同様にDNAを損傷させてがん化を促します。
そのほか、ヒトパピローマウイルス(HPV)、ヒ素を代表とする化学物質、皮膚の外傷や慢性的な刺激も皮膚がんのリスク因子です。
ほくろ(ホクロ)と似ている皮膚がんの種類

皮膚がんにはさまざまな種類があり、ほくろ(ホクロ)と酷似しているものもあります。
ほくろと間違われやすい皮膚がんは、悪性黒色腫(メラノーマ)、基底細胞がんです。
次章では、それぞれの特徴・症状などを詳しく解説します。
悪性黒色腫(メラノーマ)
悪性黒色腫(メラノーマ)とは、皮膚の色合いをもたらすメラニン色素を産生する、メラノサイトの細胞ががん化したものです。
日本人の発症頻度は10万人に1~2人で、年間の罹患数は5,000人程度と非常に少なく、希少がんに分類されます。※2
褐色から黒色のシミ(色素斑)・できもの(腫瘤)として、足の裏や手のひら、顔・胸・腹・背中などの皮膚のほか、粘膜・眼・中枢神経系などにも現れます。
悪性黒色腫の特徴的な症状は、下記のとおりです。
- 形が左右非対称である
- 輪郭がギザギザしている
- 色調が均一でない
- 大きさが6mm以上ある
また、大きさ、色・形・硬さなどが変化し、明らかにほくろ(ホクロ)と異なる症状が出ます。
悪性黒色腫は、進行が早いうえに転移・再発するケースが少なくありません。該当する症状がある場合は、直ちに皮膚科を受診しましょう。
基底細胞がん
基底細胞がんは、表皮の最下層にある基底細胞や毛包(毛根を包む組織)の細胞にできるがんです。
皮膚がんのなかで最も発症頻度が多く、7割以上は顔面(外鼻部・下眼瞼部・頬部・上口唇部)に現れます。※3
基底細胞がん全体の約80%は、ほくろ(ホクロ)と勘違いされやすい結節・潰瘍型です。小さな黒いほくろと似たものが徐々に大きくなり、中心部が潰瘍化します。※4
また、表面に光沢があり、周囲は堤防状に盛り上がるほか、毛細血管が膨張して出血するケースも少なくありません。
一般的に、基底細胞がんは転移しません。しかし、放置をすると筋肉や骨などに浸潤して組織を破壊するため、早期の切除が必要です。
皮膚がんとほくろ(ホクロ)の見分け方

皮膚がんとほくろ(ホクロ)を見分けるポイントは、形や境界線、色・大きさ・変化の有無などです。
次章では、それぞれのポイントを詳しく解説します。最近、新しいほくろができた方や、気になるほくろがある方はぜひ参考にしてください。
形が左右対称でない
通常、ほくろ(ホクロ)は円形または楕円形で左右対称です。
一方、皮膚がんは細胞が異常に増殖しているため、左右非対称のいびつな形として現れます。
左右非対称の場合、悪性黒色腫(メラノーマ)の可能性があります。放置せずに皮膚科を受診しましょう。
境目が鮮明でない
ほくろ(ホクロ)は輪郭がはっきりしており、周囲の皮膚との境目が明確です。
縁がギザギザして境目が不鮮明な場合は、悪性黒色腫(メラノーマ)や基底細胞がん(斑状強皮症型)が疑われます。
初期の段階では目視のみで判断しにくく、ある程度進行してから気付くケースも少なくありません。軽度でも異変がある際は、医療機関に相談しましょう。
色が均一でない
色が均一でなく、濃淡が混じっているほくろ(ホクロ)は、悪性黒色腫(メラノーマ)によくみられる症状です。
一つのほくろのなかに薄い茶色や濃い黒色など、複数の色調が存在しないか定期的にチェックし、早期発見・早期治療につなげましょう。
大きくなる・数が増える
ほくろ(ホクロ)が急に大きくなったり、数が増えたり、変化がみられた場合は注意が必要です。
悪性黒色腫(メラノーマ)の進行スピードは非常に速く、1~2か月で周辺に転移するため、ほくろの拡大・増加が現れます。
明らかな変化が確認できた際は、皮膚科を受診してください。
隆起している
ほくろ(ホクロ)の隆起は、皮膚がんの特徴的な症状の一つです。
表面の隆起のほか、しこりが出現して中央部が膨らんできた、皮膚が硬くなったなどの変化にも注意しましょう。
隆起が赤みを帯び、長期間のただれや角化性が治らない場合は、有棘(ゆうきょく)細胞がんが疑われます。
悪化すると出血や悪臭が伴うケースがあるため、できる限り速やかに検査をおこない、適切な治療を受けましょう。
皮膚がんの検査方法・治療法

皮膚がんの初期は、ほくろ(ホクロ)をはじめ、シミ・湿疹などの日常的な肌トラブルと見分けがつきにくいです。
自己判断が難しい場合は皮膚科を受診し、必要に応じて専門医の診断・治療を受けることが大切です。
次章では、皮膚がんの検査方法・治療法を詳しく紹介します。気になる症状がある方は、ぜひ参考にしてください。
検査・診断方法
皮膚がんの検査・診断方法は、下記のとおりです。
- 視診
- ダーモスコピー
- 病理生検
- 画像検査
皮膚がんの検査では、まず医師が病変の色・形・硬さなどを目視で確認する視診がおこなわれます。
目視での判断が難しい場合、ダーモスコピーと呼ばれる拡大鏡を使用し、強い光を照射しながら皮膚の色素や血管などの状態を調べます。
皮膚がんの診断には、病理生検が必要です。局部麻酔下で疑わしい病変の一部、または全部をメス切除して顕微鏡で細かく観察します。
がんの広がり・転移の有無を確認するためには、超音波(エコー)・CT・MRIなどの画像検査が有用です。
そのほかの検査方法として、遺伝子異変の有無がわかる遺伝子パネル検査や、がんが産生する物質量を測定する血液検査(腫瘍マーカー)などがあります。
治療法
皮膚がんの治療法は、がんの進行度や皮膚のタイプ、体の状態を評価したうえで、決定します。主な治療法は、下記のとおりです。
- 手術
- 放射線治療
- 化学療法
がんが皮膚の表面に留まっている、あるいは真皮まで進行してもリンパ節への転移がない皮膚がんは、手術による根治が可能です。
がんそのものと一定の範囲をメスで切除し、必要に応じて傷口にほかの部位の皮膚を貼り付ける植皮術や、周囲の皮膚と皮膚組織を移植する皮弁作成術をおこないます。
手術が困難な皮膚がんやリンパ節に転移がみられた際は、放射線治療を選択します。また、再発・転移を防ぐために、術後放射線治療をおこなうケースも多いです。
遠隔転移がある場合は、化学療法を実施します。
化学療法には抗がん剤のほか、がんに対する免疫細胞の攻撃力を上げる免疫チェックポイント阻害薬や、がん細胞の増殖・転移に関わる分子のみに作用する分子標的薬があります。
マイクロCTC検査でがんの早期発見が可能

マイクロCTC検査は、皮膚がんを含む全身のがんの早期発見につながる血液検査です。
増殖の過程で血中に漏れ出したがん細胞を特異度94.45%で検出するため、画像検査では見つけにくい微小ながんの発見にも役立ちます。※5
また、従来のCTC検査(セルサーチ社)と異なり、浸潤・転移する能力を持つ悪性度の高いがん細胞のみを捉えることも、マイクロCTC検査の特徴の一つです。
そして、マイクロCTC検査は時間・場所を問わず、検査の予約から検査結果の確認までWebで完結します。がん検診や人間ドックを受ける時間がない方でも気軽に受診できるでしょう。
ここからは、がんの早期発見が重要な理由とマイクロCTC検査の概要を紹介します。
がんの早期発見が重要な理由
多くのがんは、初期の段階では自覚症状が現れにくく、また、がん特有の症状はないことから、発見が遅れるケースが少なくありません。
がんの進行速度はステージにより大きく変わり、進行するほど生存率が低くなります。ステージ別の5年生存率は、下記のとおりです。
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | |
| 全がん | 96.2% | 83.2% | 52.7% | 20.0% |
ステージ1・2の早期がんは年単位で進行するため、8割以上で根治が可能です。
しかし、進行がんに該当するステージ3は半年、末期がんのステージ4は1か月の単位で進行し、生存率は著しく低下します。
がんの早期発見のメリットは、生存率の向上はもちろん、身体的・精神的・経済的な負担を抑えた治療の選択ができることです。
また、治療後の生活の質(QOL)の維持にもつながります。
採血のみで全身のがんリスクを判定
マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで全身のがんリスクが明確になります。また、事前の食事制限や薬剤の投与、被ばくのリスクがないため、次の方におすすめです。
- 短時間で全身のがんを調べたい方
- 過去のがん検査でつらい思いをした方
- 体に負担がかからない検査を受けたい方
全身のがんを調べる場合、複数の検査を受ける必要があり、半日~1日の時間を要します。仕事や家事などで忙しい方にとっては受診のハードルが高いといえるでしょう。
マイクロCTC検査は1回5分の短時間で終了し、受付を含めても30分程度です。
検査時の痛み・不快感は一切なく、検査前に絶食や薬を投与する必要もありません。また、被ばくのリスクもないことから体に負担をかけず定期的に受診できます。
全国の提携クリニックで受診可能
マイクロCTC検査は、全国154件の提携クリニックで導入しています。
遠方の医療機関や検査施設が整っている大学病院などに出向く必要はなく、居住地や勤務地の周辺など、都合のよい場所で受診できます。
転勤先・引っ越し先でも同様の高精度な検査が受けられるため安心です。
マイクロCTC検査の流れは下記のとおりです。
- クリニック検索
- 検査予約
- 検査(採血)
- 結果確認
マイクロCTC検査の公式サイトから受診するクリニックと日時を選び、問診票を記入して支払い方法を選択します。
マイクロCTC検査は完全予約制です。当日は予約時間の10分ほど前に来院し、予約名を伝えて身分証明書を提示して受付を済ませましょう。
受付終了後は医療機関の指示に従い、検査(採血)を受けて終了です。事前にクレジットカード決済をすると、検査後すぐに帰宅できます。
検査結果は、7〜10日前後で確定します。登録先のメールアドレスに通知が届いたら、マイページにログインして結果を確認しましょう。
万が一、がん細胞が検出された場合には、医師による無料相談が受けられます。
皮膚がんとほくろ(ホクロ)に関するよくある質問

最後に、皮膚がんとほくろ(ホクロ)に関するよくある質問を紹介します。
足の裏のほくろはがんなのか、皮膚がんが転移する可能性はあるのか、ほくろの除去とがんの関係性について詳しく解説します。
同じ疑問を抱いている方はぜひ参考にしてください。
足の裏のほくろはがん?
足の裏のほくろ(ホクロ)は、がんではないケースが多いです。
しかし、悪性黒色腫(メラノーマ)が最も発症する部位は足の裏であるため、十分に見極めることが重要です。
悪性黒色腫は、下記のABCDルールに基づいて診断されます。
- A(Asymmetry):非対称性の病変
- B(Border irregularity):不規則な外形
- C(Color variegation):多彩な色調
- D(Diameter greater than 6mm):長径が6mm以上
- E(Enlargement or evolution of color change, shape, or symptoms):経過の変化
4つ以上当てはまる場合は悪性黒色腫が疑われ、2つ以下であれば普通のほくろの可能性が高いです。
皮膚がんは転移しやすい?
皮膚がんが表皮内に留まっている状態であれば、ほぼ転移しません。
しかし、真皮に浸潤するとがん細胞はリンパや血液の流れに乗り、全身を移動する恐れがあります。
とくに、皮膚がんのなかで最も転移しやすい悪性黒色腫(メラノーマ)には、注意が必要です。比較的早い段階からリンパ節に転移し、さらに肺・肝臓・脳などにも広がります。
転移した場合、生存率は著しく低下し、ステージ4に該当する末期の状態になると5年生存率はわずか10%程度です。※6
また、手術後3年以内に再発するケースが多く、ステージの再発率は50%を超えます。※7
悪性黒色腫の早期発見・早期治療には、セルフチェックが重要です。異変がみられた際は、速やかに皮膚科を受診するようにしましょう。
ほくろを除去するとがんになる?
ほくろ(ホクロ)を除去してもがんになることはありません。
しかし、ほくろが皮膚がんの可能性がある場合は、慎重に検討する必要があります。
とくに、自身で取り除こうとすると、傷跡が残ったり、再発したりなどのリスクを伴ううえに、医師が正確に診断する機会を失って治療が遅れる可能性があります。
ほくろを除去する際は、必ず医師による診察・検査を受けて良性・悪性の判断はもちろん、ほくろのタイプや仕上がりに応じた施術を提案してもらいましょう。
除去後の肌は非常にデリケートです。色素沈着や傷跡を目立たなくするために紫外線対策をおこない、患部に刺激を与えないよう優しいスキンケアを心がけましょう。
まとめ

本記事では、皮膚がんとほくろ(ホクロ)の見分け方を中心に解説しました。
皮膚がんのうち、悪性黒色腫(メラノーマ)と基底細胞がんは、ほくろと非常によく似ています。とくに初期は違いがわかりにくく、放置するケースも少なくありません。
しかし、皮膚がんで最も危険な悪性黒色腫は、進行速度が速く、浸潤・転移・再発が起こりやすいため、早期発見・早期治療が重要です。
ほくろの形が左右非対称である、輪郭がギザギザしている、色調が均一でない、大きさが6mm以上あるなどの症状がある際は、速やかに皮膚科を受診しましょう。
皮膚がんをはじめ、全身のがんリスクを知りたい方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は、血中を循環するがん細胞そのものをキャッチしてがんリスクを明示する血液検査です。
1回5分の採血のみで終了し、事前の準備は一切不要です。仕事が忙しい方はもちろん、家事・育児などで自身の時間が確保できない方でも気軽に受けられるでしょう。
また、体の負担がなく定期的に受診できることから、がんの超早期発見につながります。
〈参考サイト〉
※1:環境省|オゾン層等の監視結果に関する年次報告書
※2:厚生労働省|令和2年(2020)患者調査の概況
※3:国立がん研究センター 中央病院|診療について
※4:がん研有明病院 皮膚腫瘍科|基底細胞がん
※5:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査
※6:健康長寿ネット|皮膚がん末期
※7:新潟県立がんセンター新潟病院|悪性黒色腫の初回再発
