実際に男性は女性よりもがんになりやすく、また、高齢になればなるほど罹患数は増えていきます。※1
しかし、近年では女性のがんの発症率が増えており、若年化も進んでいます。とくに、女性特有のがんに関しては罹患数・死亡数が増加の一途を辿っているため、注意が必要です。※2
本記事では、女性特有のがんの概要をはじめ、がんになりやすい女性の特徴・主な原因・罹患数・死亡数ランキング、がんを早期治療・予防する方法などを詳しく解説します。
\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

女性特有のがんとは?
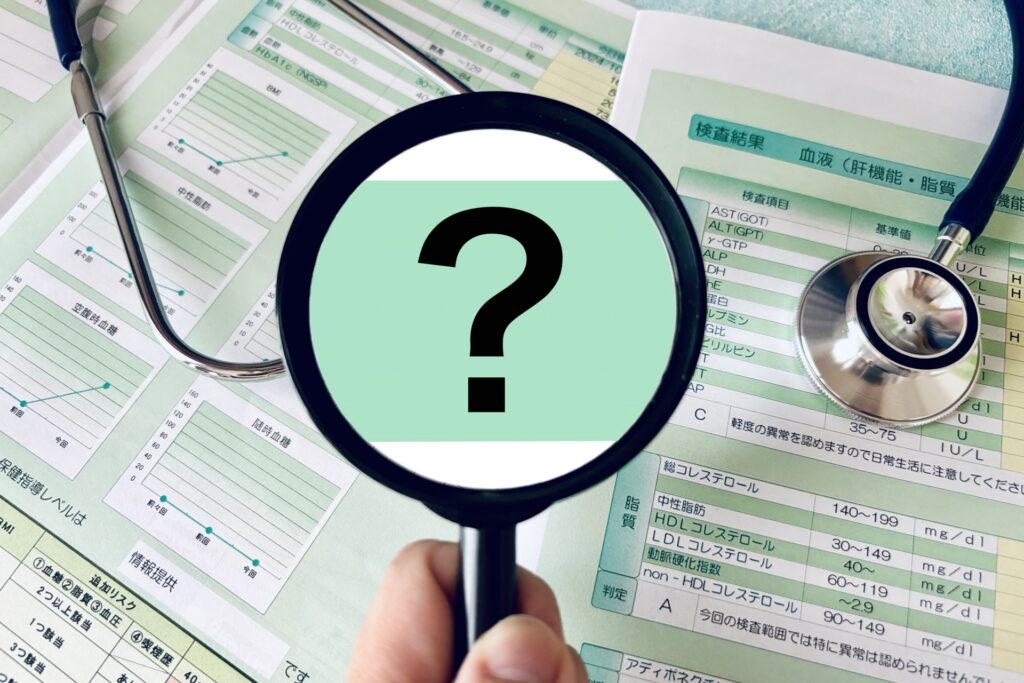
女性特有のがんとは、体の構造から「圧倒的に女性がなりやすいがん」、または「女性のみに発症するがん」を指します。
大半のがんは加齢とともに罹患数が増加しますが、女性特有のがんは比較的若い年代で発症するケースも少なくありません。
女性特有のがんには、下記の種類があります。
- 乳がん
- 子宮がん
- 卵巣がん
乳がんは、最も女性がなりやすいがんです。男性でも罹患する可能性はゼロではありませんが、割合は全体の1%未満と非常に稀です。※3
子宮・卵巣は女性のみがもつ臓器であるため、がんが発症した場合は女性特有のがんに分類されます。
次章では、乳がん・子宮がん・卵巣がんについて詳しく解説します。
乳がん
乳がんとは乳腺の組織にできるがんです。全体の約90%は母乳を乳頭まで運ぶ乳管に、約10%は母乳をつくる小葉に発生します。※4
乳がんは女性が最もかかりやすく、罹患数は30歳代後半から増え始めて45~55歳と60~69歳に2回のピークがあります。※5
乳がんの種類は、下記のとおりです。
- 浸潤がん
- 非浸潤がん
乳がん全体の約80%を占める浸潤がんは、がんが乳管または小葉の外まで広がっている乳がんを指します。※6
リンパ管・血管などに入り込み、周辺や遠隔の組織・臓器に転移を起こす可能性があるため、早期治療が重要です。
非浸潤がんは、がんが乳管・小葉のなかに留まっている状態です。転移・再発の危険性が低く、大半は根治が見込めます。
乳がんの代表的な症状は、乳房のしこり・へこみ、乳頭の分泌物、皮膚の腫れ・ただれなどです。
子宮がん
子宮がんには、子宮体がんと子宮頸がんがあります。がんが発症する場所や特徴、好発年齢は下記のとおりです。
| 発症部位 | 特徴 | 好発年齢 | |
|---|---|---|---|
| 子宮体がん | 子宮の奥にある体部 | 閉経後に多く発症する | 50~59歳 |
| 子宮頸がん | 子宮の入り口の頸部 | 10・20歳代でも発症する | 35~49歳 |
子宮がんの約60%は子宮体がんです。大半は子宮の奥にあたる内膜に発症し、稀に子宮(筋肉・間質)の細胞ががん化するケースがあります。※7
子宮体がんは閉経後の女性に多くみられるため、罹患数は40歳代後半から急激に増加し、55~59歳が最多です。※8
子宮頸がんとは、子宮の入り口である頸部に発症するがんです。多くの場合、CIN(子宮頸部上皮内腫瘍)やAIS(子宮頸部上皮内腺がん)と呼ばれる前がん病変を経てがんになります。
好発年齢は35~49歳ですが、近年では若い世代の罹患数が増加しており、全体の約38%は20~30歳代です。※9※10
卵巣がん
卵巣がんは、子宮の左右にある卵巣のがんです。大半は腺がんと呼ばれるタイプで、性質により下記の組織型に分類されます。
- 漿液性がん
- 明細胞がん
- 類内膜がん
- 粘液性がん
卵巣がんの33.2%は漿液性がんです。もともとの正常な組織・細胞に近い形態の低異型度のものと、進行が早く悪性度が高い高異型度のものが存在します。※11
次いで多いのが明細胞がんです。卵巣がんの24.4%を占めており、比較的進行が遅いとされる反面、化学療法が効きにくい性質があります。※12
類内膜がん・粘液性がんの発症頻度は全体の9~16%程度と、稀なタイプです。類内膜がんの進行は遅く、粘液性がんは進行する例が少ないといわれています。※13
卵巣がんは、40歳を超えたあたりから罹患数が急激に増加し、50~54歳でピークを迎えます。また、20・30歳代でも発症するケースがなくありません。※14
がんになりやすい女性は?主な原因は?

ここからは、がんになりやすい女性の特徴を紹介します。
主ながんの原因として下記があげられます。
- 女性ホルモン
- HPV(ヒトパピローマウイルス)
- ピロリ菌
- 生活習慣
次章では、それぞれの原因と発症リスクが高くなるがんの種類を詳しく解説します。
女性ホルモン
がんには、女性ホルモンの刺激を受けて発症するホルモン感受性のがんがあります。
女性ホルモンの一種である「エストロゲン」には、がん細胞を増やす作用があるため、エストロゲンが分泌される期間が長いほど下記のがんになりやすくなるといわれています。
- 乳がん
- 子宮体がん
- 卵巣がん
乳がんの約70%は、がん細胞がエストロゲンの影響を受けて増殖する「エストロゲン受容体陽性乳がん(ER陽性乳がん)」です。※15
そして、エストロゲンの分泌量が多い場合、子宮内膜増殖症を経て子宮体がんを発症するケースが少なくありません。
また、卵巣がんもエストロゲンによりがん細胞の成長が促進される、ホルモン感受性のがんの一つです。
初経から閉経までの期間が長い方や、妊娠・出産の経験がない方は、長期間エストロゲンに曝露した状態といえます。
そのほか、閉経後は卵巣ではなく脂肪からエストロゲンが分泌されるため、太りすぎの方も注意が必要です。
HPV(ヒトパピローマウイルス)
子宮頸がんの95%以上は、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因です。※16
HPVは、性的接触のある女性の半数以上が感染するとされる一般的なウイルスであり、多くは自然に消滅します。
しかし、13種類のハイリスク型と呼ばれるタイプに長期間感染した場合、子宮頸がんを発症する可能性が高くなります。
とくに、16型・18型は、前がん病変を経て子宮頸がんになる頻度が高く、進行スピードも速いため注意が必要です。
そのほか、中咽頭がん・肛門がんもHPV関連のがんといわれています。
ピロリ菌
胃がんの98%以上は、胃の粘膜に生息するヘリコバクター・ピロリと呼ばれるピロリ菌の感染によるものです。※17
ピロリ菌の感染ルートはまだはっきり断定されていませんが、免疫力が低い乳幼児へ食べ物を口移しで与えたり、親と箸やスプーンを使ったりなどの経口感染の可能性が高いです。
また、衛生環境が十分ではない井戸水や、ゴキブリ・ハエなどの害虫を介して感染するケースもあります。
50歳以上の約60%、40歳代の約45%はピロリ菌に感染しているといわれており、慢性胃炎や腸上皮化生細胞を経て胃がんを発症するケースが多いです。※18
ピロリ菌の感染が確認された場合、除菌治療をおこなうことで胃がんの発症を抑えることが可能です。
生活習慣
生活習慣のなかにも、がんに関与しているものが複数あります。
- 喫煙
- 過度な飲酒
- 食生活
- 運動不足
喫煙は、女性のがん全体の発症率を1.5倍高めます。とくに、子宮頸がんの確実な危険因子であることがわかっており、発症リスクは20.3倍です。※19※20
また、乳がんのリスクを1.9~3.9倍上昇させ、卵巣がんのリスクも増加させることが認められています。※21
同じく、過度な飲酒もがんの発症と深く関係しており、乳がん・大腸がん・食道がん・肝臓がんのリスクを高めます。
そのほか、動物性油脂や塩分が多く、野菜・果物の摂取量が少ない食生活、運動不足や肥満なども、がんの危険因子です。
生活習慣の改善は、女性特有のがんを含むすべてのがんの予防につながります。
女性の年代別で見るなりやすいがんの種類

罹患しやすいがんは、年代別で多少異なります。
次章では、女性がなりやすいがんを年代別で紹介します。現在の年齢や将来なる確率が高いがんを把握したい方は、ぜひ参考にしてください。
30代・40代
30・40代の女性に多いがんは、下記のとおりです。
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 30代 | 乳がん | 子宮頸がん | 卵巣がん |
| 40代 | 乳がん | 子宮頸がん | 子宮体がん |
30・40代の女性に多いがんは、1位が乳がん・2位が子宮頸がんです。3位は卵巣がん・子宮体がんと異なりますが、ともに女性特有のがんになりやすいことがわかります。
2つの世代の罹患数を合計すると、乳がんは全体の約22%、子宮頸がんは全体の37%を占めています。※22
卵巣がんは30代後半から、子宮体がんは40代後半から発症率が増加傾向です。
50代・60代
50代・60代の女性がなりやすいがんのトップ3は、次のとおりです。
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 50代 | 乳がん | 大腸がん | 子宮体がん |
| 60代 | 乳がん | 大腸がん | 肺がん |
30・40代と同様に、50・60代の1位も乳がんです。2019年では39,522人の方が乳がんと診断されています。※23
しかし、50・60代は生活習慣や加齢などにより、大腸がんや肺がんの罹患数が5~8倍ほど増えています。
また、50代は女性ホルモンのバランスが崩れやすいです。そのため、子宮体がんの罹患数が5,378人まで膨れ上がり、3位に位置しています。※24
女性のがん罹患数・死亡数ランキング

生涯の女性のがん罹患リスクは48.9%と、2人に1人は何らかのがんになる可能性があります。そのうち、17.2%にあたる6人に1人ががんで亡くなっています。※25
次章では、女性のがん罹患数・死亡数ランキングを詳しく紹介します。
罹患数
女性のがん罹患数ランキングは、次のとおりです。
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| がんの種類 | 乳がん | 大腸がん | 肺がん | 胃がん | 子宮がん |
| 罹患数 | 97,142人 | 67,753人 | 42,221人 | 38,994人 | 28,759人 |
女性の罹患数1位は97,142人の乳がんです。女性が罹患するがん全体の22.5%を占めています。
乳がんの発症ピークは45~49歳と60~70歳代の2回あり、生涯のうち、9人に1人の女性が罹患するといわれています。※26
次いで、罹患数の2位は大腸がんです。毎年60,000人以上が大腸がんと診断されており、食生活・肥満・飲酒などの影響から今後も増え続けると予測されています。
胃がんも同様に、喫煙率・飲酒率の上昇により罹患数が増えています。
3位の肺がん、4位の子宮体がんの発症には、女性ホルモンであるエストロゲンが関与しているケースが多いです。
そのほか、甲状腺がんも女性がかかりやすいがんの一つです。
死亡数
がんによる女性の死亡数ランキングを紹介します。
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| がんの種類 | 大腸がん | 肺がん | 膵臓がん | 乳がん | 胃がん |
| 死亡数 | 25,195人 | 22,859人 | 20,316人 | 15,629人 | 13,446人 |
死亡数ランキングの1位は、罹患数2位の大腸がんです。
大腸がんは、早期発見すれば9割程度根治が可能ですが、自覚症状が現れにくいことや、罹患者の多くが60歳以上の中高齢者であるため、死亡数のトップに位置しています。
また、肺がんや膵臓がんも症状が出にくく、早期発見ができずに進行した状態で見つかるケースが少なくありません。
乳がんは女性の罹患数1位ですが、進行スピードが比較的遅いことや、マンモグラフィ検査の普及などにより死亡数では4位に抑えられています。
胃がんは、1997年以前では死亡数1位でした。胃がんの原因であるピロリ菌の感染者が減少したことで、現在では5位まで下がっています。※27
がんを早期発見・予防する方法

女性特有のがんはもちろん、すべてのがんは早期発見が非常に重要です。
がんの早期発見は生存率を高めるのみならず、心身の負担が少ない治療が受けられたり、仕事や家事と治療を両立できたりと、メリットしかありません。
がんを完全に防ぐことは困難ですが、予防は可能です。
次章では、早期発見に有効な定期検診と、予防効果があるワクチン接種や生活習慣の見直しについて解説します。
定期検診を受ける
がんを早期発見するためには、定期検診を受けることが大切です。
国は、科学的根拠に基づいたがん検診の受診を推進しており、自治体が主体となって下記の検診を実施しています。
| 種類 | 検査項目 | 検診対象者 | 受診間隔 |
|---|---|---|---|
| 乳がん検診 | マンモグラフィ検査 | 40歳以上 | 2年に1回 |
| 子宮頸がん検診 | 視診、細胞診(一部、HPV検査単独法も実施) | 20歳以上 | 2年に1回 |
| 大腸がん検診 | 便潜血検査 | 40歳以上 | 1年に1回 |
| 肺がん検診 | 胸部X線検査、喀痰細胞診(対象該当者のみ) | 40歳以上 | 1年に1回 |
| 胃がん検診 | X線検査、または胃内視鏡検査 | 50歳以上 | 2年に1回 |
がん検診は、自治体が費用の多くを負担するため、無料または少ない自己負担での受診が可能です。受診票が届いた方は、忘れずに期間内に受けましょう。
ワクチンを接種する
子宮頸がんの予防には、HPV(ヒトパピローマウイルス)のワクチン接種が効果的です。
HPVワクチンを接種すればハイリスク型の16型・18型の感染が防げるため、子宮頸がんの80~90%が予防できます。※28
ワクチンの効果を最大限に生かすためには、性交渉の前に接種する必要があるため、国は小学校6年生~高校1年生相当の女の子にワクチン接種を推奨しています。
ワクチンの種類や年齢に応じて接種回数・スケジュールが異なり、また、対象年齢であれば原則自己負担なしで接種が可能です。
また、接種機会を逃した方に対するキャッチアップ接種も公費で受けられます。
性交渉後でも一定の予防効果が期待できますが、16歳以上の方は全額自己負担です。
生活習慣を見直す
がんの予防には生活習慣の見直しが必要不可欠です。
国立がん研究センターをはじめとする研究グループは、「科学的根拠に根ざしたがん予防ガイドライン」として、下記を推奨しています。
- 禁煙
- 禁酒・節酒
- 食生活の改善
- 身体活動
- 適正体重の維持
禁煙すれば肺がんのリスクは約50%まで低下し、また、乳がん・子宮頸がん・食道がんなどのリスクも下げることも可能です。※29
禁酒・節酒は、大腸がん・肝臓がん・食道がんの予防に効果的です。お酒がやめられない方は、1日のアルコール摂取量を23g程度に抑えるよう心がけましょう。
また、食生活の改善も重要です。塩分や肉類・加工品の大量摂取を避けて、野菜・果物を多く摂る食生活に改善しましょう。
そのほか、1日60分程度は歩行またはそれと同等の身体活動をおこない、BMI値21~25の範囲の適正体重を維持しましょう。
がんになりやすい女性にマイクロCTC検査がおすすめ

マイクロCTC検査は、女性特有のがんをはじめ、全身のがんリスクがわかる血液検査です。
血中に漏れ出したがん細胞を特異度94.45%で検出するため、がんの早期発見・早期治療に非常に役立ちます。※30
ここからは、マイクロCTC検査について詳しく解説します。
採血のみで全身のがんリスクを判定
マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで全身のがんリスクを判定するため、仕事や家事で忙しい女性でも気軽に自身のがんリスクを把握できます。
専門の医療機関へ出向く必要はなく、近隣の提携クリニックで検査できるため、通勤途中や買い物・用事のついでなど、都合がよいときの受診が可能です。
また、高い検査精度を実現していることも、マイクロCTC検査の魅力です。
従来の検査では、1cm未満の小さながんは発見できず、また、画像に写りにくい場所のがんを見落とすケースがありました。
マイクロCTC検査では、採取した血液検体を速やかに国内の自社検査センターで分析して、特異度94.45%を誇る高精度で血中のがん細胞そのものを検出します。※31
正確性に優れたがんリスク検査を受けたい方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
アフターフォロー体制も充実
マイクロCTC検査でがん細胞が検出された方には、マイクロCTC検査センター長および代々木ウィルクリニックの太田医師による、無料相談が受けられます。
無料相談は、9~12時・13~19時の間で最大30分です。検査結果の説明から受診すべき検査の詳細、専門医や医療機関の紹介まですべて無料です。
また、相談後に精密検査を受けてもがんが見つからなかった場合、再度相談ができます。
無料相談は、原則対面での対応となりますが、遠方の方はオンライン面談が可能です。
マイクロCTC検査は、万が一のときも安心して受けられる検査といえるでしょう。
費用・検査の流れ
マイクロCTC検査の料金は、1回198,000円(税込)です。※32
検査を希望する方は、公式サイトから受診するクリニックを選び、次の流れで予約を確定させましょう。
- 検査日時の選択
- 問診表の記入
- 支払い方法の選択
都合のよい日時を選び、ログインまたは会員登録をします。予約は最大12か月先まで可能です。
次に、既存歴を含む個人情報と問診表を入力し、支払い方法の選択と同意事項にチェックをすれば予約が確定となります。
検査当日は予約日時の10分前に来院し、受付を済ませたあと医師・看護師の指示に従って検査を受けましょう。
検査結果はWebで閲覧が可能です。検査結果の確定後、登録されているメールアドレスに通知が届きます。マイページにログインして検査結果を確認しましょう。
まとめ

本記事では、女性特有のがんやがんになりやすい女性の特徴を中心に、解説しました。
女性特有のがんには、乳がん・子宮がん(子宮頸がん・子宮体がん)・卵巣がんがあり、発症しやすい年齢が少々異なります。
がんの発症には、女性ホルモンをはじめ、HPV(ヒトパピローマウイルス)やピロリ菌の感染、生活習慣が深く関与していることがわかっています。
自覚症状がないうちから女性特有のがんのリスクを知りたい方には、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで血中に漏れ出したがん細胞を検出して、全身のがんリスクを判定します。
クリニック検索から受診予約、検査結果の確認まで、すべてWebで完結するため、手間をかけずに自身のがんリスクを把握したい方におすすめです。
がんの早期発見・早期治療のために、定期的にマイクロCTC検査を活用しましょう。
〈参考サイト〉
※1、※2、※10、※22、※23、※24、※27:国立がん研究センター|集計表
※3:済生会|男性の「乳がん」をご存じですか?
※4:日本医師会|知っておきたいがん検診 乳がんとは?
※5:国立がん研究センター がん統計|乳房
※6:一般社団法人 日本乳癌学会|患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2023年版
※7:がん対策推進企業アクション|厚労省が指針で検診を勧める5つのがん 子宮頸がん
※8:国立がん研究センター がん統計|子宮体部
※9:国立がん研究センター がん統計|子宮頸部
※11、※12、※13:日本癌治療学会|治療ガイドライン 第2章 卵巣癌・卵管癌・腹膜癌
※14:国立がん研究センター がん統計|卵巣
※15:乳がん.jp|あなたのがんの特徴 ホルモン受容体陽性乳がん
※16:公益社団法人 日本産科婦人科学会|子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために
※17:一般社団法人 日本癌学会|胃がんで亡くならないために何をなすべきか
※18:順天堂大学医学部附属順天堂医院|がん治療センター ピロリ菌と胃がん
※19:国立がん研究センター がん対策研究所|喫煙とがん全体の発生率との関係について
※20:国立がん研究センター がん対策研究所|喫煙と子宮頸がんリスク
※21:一般社団法人 日本禁煙学会|タバコと乳がんについての重要な情報
※25、※26:国立がん研究センター がん統計|最新がん統計
※28:厚生労働省|HPVワクチンについて知ってください
※29:禁国立がん研究センター がん情報サービス|煙による健康への効果
※30、※31、※32:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査
